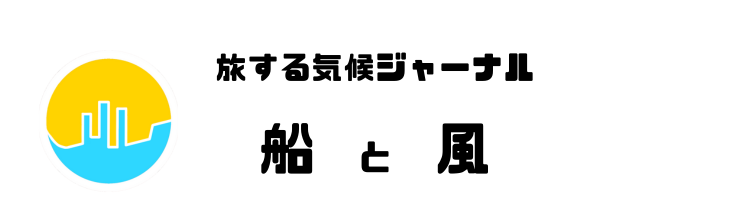妥協を排した抵抗:アンドレアス・マルムとの対話
ベルナルド・ジュレーマ、エリアス・ケーニヒ
『Protean Magazine』2025年6月3日

原文リンク:https://proteanmag.com/2025/06/03/uncompromising-resistance-a-conversation-with-andreas-malm/
イントロダクション
名指しでFBIの警告を受けたことがあるという現代の知識人は、ほとんどいない。ルンド大学の人間生態学の准教授であるアンドレアス・マルムは、少なくとも35回、そうした文書の対象となってきた。マルムのベストセラー著書『パイプライン爆破法――燃える地球でいかに闘うか』〔邦訳は箱田徹訳、月曜社 2021年〕が2023年〔正しくは2022年〕に映画に翻案されたとき、世界でもっとも強力な国内法執行機関〔FBI〕のいくつもの部署がパニックになったと報道され、『ローリング・ストーンズ』が「紛れもない不安のアルファベット・スープ」と呼んだもの――この映画が国内の決定的に重要なインフラに脅威を及ぼすことへの悲壮な警告の洪水――が放出されてきた。
実際に本を読んだ人間なら分かっているはずだが、マルムの著作が危険なのは、化石燃料インフラをいかに解体するかについての『アナーキスト・クックブック』〔爆弾の具体的な製造法などを記したウィリアム・パウエルの著書。1971年刊〕流の詳細な手引書だからではなく、批評という武器をものの見事に使いこなしているからだ。すなわち、化石資本の働きと、その帰結として世界が食い尽くされることについての、入念かつ容赦ない分析という武器である。彼の英語での最初の著作『化石資本――蒸気力の勃興とグローバルな温暖化の諸起源』にはじまり、『パイプライン爆破法』のような著書で行なった、気候運動がそのレパートリーを広げ財物破壊のような戦術的手段を考慮にいれることへの説得力ある論拠にいたるまで。2019年のグローバルな気候プロテストのあいだ、世界中で何百万という人々が気候正義を求めるさまざまな運動に参加したが、気候運動左派の多くにとってマルムをかくも欠かすことのできない知識人にしていたのは、まさしくこうした徹底的にマルクス主義的な分析と、時宜をえた戦略上の介入との組み合わせだった。
そうした抗議の波が引いた今、マルムの最新の刊行物はかなり寒々しい絵柄を描くようになっている。2024年秋、マルムはルンド大学の同僚ウィム・カートンとの共著で『オーバーシュート――世界はいかに気候崩壊に屈したのか』を発表した。この本が土台としている最新調査では、グローバル経済の急速な脱炭素化を想定したとしても、世界は産業革命以前の水準と比べて摂氏3~5度の気温上昇をたどる可能性が高いことが示されている。パリ協定の1.5度という限界は、ネットゼロのシナリオにおいてすら、世紀の半ばまでに超過される――オーバーシュートする――ことになっている。これは深刻な社会的、経済的、政治的な帰結をもたらすだろう。「地中から取り出された化石燃料は」とマルムとカートンは書いている、「人類に、そして何よりもグローバルサウスに生きる人々に向けて無差別に発射されるロケット弾――文字通りの意味での、炭素爆弾なのだ」。〔ふつう、累計で1ギガトン以上のCO2を排出することになる大型化石燃料プロジェクトのことを炭素爆弾と呼ぶ。世界中で425個の「爆弾」が存在するとされる。〕
とりわけグローバルノース――惑星的な限界を超える排出の92%に責任がある――で、引き金がひかれつづけている。二人が記しているように、「グローバルノースの五つの国々――アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ノルウェイ――が、世紀半ばまでに計画されている油田・ガス田の新規拡大の合計51%を占めている」。マルムは同じ数字を、また別の新刊のパンフレット『パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである』〔箱田徹訳、青土社から2025年7月に刊行予定〕のなかで引いている。このテクストは、西側の道徳的破産についての仮借なき告発であると同時に、パレスチナの破壊と惑星の気候システムの破壊の双方を駆動している同一の残忍な帝国的ロジックを描き出す試みでもある。
私たちとの対話のなかで、マルムは最近の著作における中心的なアイディアについて議論する。グスタボ・ペトロ〔大統領〕のコロンビアを、主要な化石燃料産出国のなかで「唯一無二の」存在にしているのは何なのか。ジオエンジニアリングの危険性。なぜフランクフルト学派が気候危機を理解するための批判的レンズを提供してくれるのか。パレスチナで行われているジェノサイドは、化石帝国というより長期的な歴史といかに繋がっているのか。そして、『長い熱――もう手遅れになった後の気候政治』と題された『オーバーシュート』の続編の近刊(今年の後半に刊行予定)が、どのような内容になる予定なのか。『オーバーシュート』のなかで、マルムとカートンはこう書いている。「これから行なうべき選択は明確だ――緩和されることのない破局か、システム全体の改造かだ」。
[編集部〔プロテアン〕注:このインタビューは長さと明晰さを目的に編集されている。]
♦♦♦
コロンビアへの訪問を終えて
ベルナルド・ジュレーマ:アンドレアス、ちょうどコロンビアから戻られたところですね。左派の大統領で元ゲリラ戦闘員であるグスタボ・ペトロ(Gustavo Petro)とお会いになって、『ジャコバン・マガジン』のためにインタビューをされたとか。ペトロは、あなたがウィム・カートンと共著で出した新刊『オーバーシュート――世界はいかにして気候崩壊に屈したのか』のなかにも登場します。そこで議論されているのは、主要な石油・石炭産出国として初めて化石燃料の完全な段階的廃止にコミットするという、彼の政権の唯一無二の試みです。コロンビアの事例をかくも特例的なものにしているのは、何なのでしょう? そしてあなたが現在の「オーバーシュート」局面と呼んでいるものについて、そこから何が分かるのでしょう?
アンドレアス・マルム:コロンビアには、二週間滞在していました――コロンビアだけでなく、そもそもラテンアメリカに行ったのが初めてのことです。きわめて緊密な旅程でしたが、これほど短い期間にこれほど多くのことを学んだことは今までにないと思います。ツアーを組織してくれたのはエネルギー省内のあるチームですが、数えきれないほどの会合に加えて、コロンビアの化石燃料の景観にとって決定的なサイトへの訪問も行いました。たとえば、石油産業の首都であるバランカベルメハ(Barrancabermeja)とその周辺、そして石炭産業の中心地である北部のセサル(Cesar)とラ・グアヒラ(La Guajira)などです。私たちは、数多くの驚倒すべき人々に会いました。ペトロ自身にはじまり、最近の環境大臣であるスサナ・ムアマー(Susana Muhamad)、元エネルギー・鉱業大臣であるイレネ・ベレス(Irene Vélez)、それから、バランカベルメハ近郊で自分たちの水がいかに石油によって汚染されてきたかを見せてくれた漁師の人々まで。
私たちの訪問によって確固たるものとなった印象は、完全な段階的廃止にコミットした唯一の主要な化石燃料産出国として、コロンビアが他に例のない国であるということです。アメリカのような主要な化石燃料産出国ですら、コロンビアが有しているほどの化石燃料への構造的依存――最近の数十年、化石燃料は輸出収入の半分以上を占めてきました――などどこにも存在していないことを考えれば、このことは、まったくもって例外的です。2022年にグスタボ・ペトロが権力の座に就いて以来、コロンビア政府は化石燃料の新たな埋蔵・設備の探査や開業のためのいかなるライセンスも認可しない、という路線をつらぬいてきました。政権をめざす政治家たちが過大な約束を行なうものの当選したらそんなことは忘れてしまう、というのはよくあることです。しかしこの場合、国内外の資本の利害からの極度に強い圧力があったにもかかわらず、コロンビアの政府はこの約束にしがみついてきており、そして実際、化石燃料の探査を行なったり新たな炭鉱を開山したりするライセンスを石油・ガス会社に対してただの一つも手渡しませんでしたし、おそらく最も重要なことに、国内における水圧破砕〔化学物質を含む高圧水で岩盤を破砕して頁岩からガス・石油を採掘する方法。深刻な環境への汚染を伴う〕の推進へのあらゆる動きを食い止めました。
私たちが何らかの仕方で気候危機を制御下に置くつもりなら、言うまでもなく、まさにこれこそが行われなければなりません。『オーバーシュート』における大きな主題はこういうものです――私たちは化石燃料を掘り出すための新規設備へ、新たな投資を行うことはできない。なぜなら、すでに存在しているものに加えて新たな投資を追加すれば、まさにそのことによって私たちは慣性を背負わされ、これらの新たな投資が回収され利益を生むようになるまで、ひたすら進みつづけることを強いられるのだから。
〔もっとも、〕コロンビアの状況がはるかに入り組んだものであることは明らかです。例えば、これからある炭鉱が開山され、カニャベラレス(Cañaverales)と呼ばれる共同体を破壊することになるかもしれません。この炭鉱はペトロ政権が始まる前に認可された契約に基づいているため、政府はこれを止めることに成功してきていません。しかし私たちの訪問中に印象だった大きな問題は、誰もが多かれ少なかれ、右派が来年には政権に返り咲くだろうという事実を諦めとともに受け入れているということです。というのも新たな大統領選、そして議会選挙が控えており、ペトロが再び勝利することはできませんから。憲法は彼の再選を許しておらず、〔選挙に〕勝利しプロジェクトを続ける勝算のある後継者が彼にいるのかは、はっきりしません。
また別の問題は、ペトロの旗印である労働法や医療に関する改革案が、国会の手綱をにぎる右翼勢力によって阻止されてきたということです。ですからコロンビアにおける普通の労働者たちの生活に本物の変化を生むと考えられている主要な改革はまだ実行されておらず、このことはもちろん、政府とその支持者にとって、大きなフラストレーションの源泉です。つまり、ペトロに投票した人々の多くは、おそらくこう考えるでしょう。自分の生活が現実には何も良くならなかったのに、どうしてまた同じようなプロジェクトへ投票しなければならないのか?
他にも数々の問題があり、したがって来年のコロンビアでは、反動の大波によって、石油やガスのために全力を尽くし国内の水圧破砕を解禁するような人物が権力の座につく可能性が、非常に高い。そうなれば、採掘が行われる場所の生態系に途方もない災厄が引き起こされ、そしてもちろん、より多くの化石燃料が地表に持ち出され、燃やされることになるでしょう。ですから滞在中に感じていたのはこういうことです――そう、たしかにこれは唯一無二の実験だ。でもすぐに終わりを迎えてしまう、短い一過性の挿話となる可能性が非常に高い。
「オーバーシュート・イデオロギー」の勃興
エリアス・ケーニヒ:コロンビア以外のほとんどあらゆる場所で、化石燃料産業は猖獗をきわめ、記録的な利潤をため込んでいるように見えます。あなたが『オーバーシュート』のなかで記しているように、グローバルな化石燃料生産は依然として拡大しつづけています。十年前、2015年のパリ気候協定に世界のすべての主要な政府が署名し、危険な気候変動に本気で制限をかけると誓った事実があるにもかかわらず。政府や金融機関がこの拡大を止めることができない――あるいはそうする気がない――ことは、何によって説明がつくのでしょうか?
マルム:シンプルな説明としては、化石燃料から生み出すことのできるお金がまだまだたくさんある、ということです。トランプの二度目の就任のなかで私たちが目にしているトレンドは、気候の領域における野心的目標の解体、あらゆる種類のコミットメントからの全面的撤退、そして気候政治の価値を貶め、さらには政治的アジェンダの外部にまで押し下げてしまおうとする試みです。これは、あらゆる種類のさざなみ効果を生み出します。化石燃料生産を後押しする国々が出てくるでしょうし、例えば、最も過大に宣伝されている二酸化炭素除去テクノロジーである直接空気回収(DAC)の業界は危機におちいっています。
この分野でこれまで最も競争力のあった企業はスイスの〈クライムワークス〉(Climeworks)でしたが、この会社はちょうど過去数週間、きわめて深刻な危機の泥沼に落ち込んでいます。それは部分的に、二酸化炭素除去のようなあれこれをめぐる規制や規則や補助金やインセンティブが、いかに〔減らされてきたか〕に関係しています。これは私たちがトランプの復活の結果として目にしている右翼的潮流、反気候的潮流全体の、間接的な副産物なのです。
ジュレーマ:著書『オーバーシュート』のなかで、「オーバーシュート」が気候の統治における支配的パラダイムになったことを主張していますね。「排出量はコントロールの及ばない場所にあり、私たちはそれをコントロールしようというプロジェクトを手にしていません。だから私たちは古典的な緩和とはちがう投機事業を試してみなければならない――これこそ私たちがオーバーシュート・イデオロギーと呼んでいるものの核となる教義なのだ」。オーバーシュート・イデオロギーとは何なのか、説明していただけますか? 誰がそれを促進し、何が私たちを今の地点まで導いたのでしょう?
マルム:オーバーシュート・イデオロギーとは、私たちの理解しているかぎり、グローバルな暑熱化の推進原因を攻撃し停止させることに対する支配階級の拒絶のうちに、その根を有しています。彼らはこう言います。実際に〔気候変動の進行の〕緩和を行なうことなどできない、必要なスピードで実際に排出量を削減することなどできない、だから私たちは、何らかの仕方でこの気候とうまく付き合うことを試す必要がある。緩和を除けば、気候危機について行えることは、主に三つあります。まず、適応という方法。単純に、可能なかぎり危機とともに生きてみようということですね。これは私たちの著書の最初のパートで議論しています。
第二のパートは、二酸化炭素の除去を扱っています。潜在的には、排出されたCO2を除去し地中に埋め戻すというのは可能かもしれません。しかしながら、それを何らかの有効なスケールで実行できるかどうかは、かなり入り組んだ問題です。第三に、ジオエンジニアリング〔地球工学〕という手もあります。地球と太陽のあいだに何らかの物体を注入することで、いくらかの太陽光線の入射を防ぎ、それによって地球を冷ますことができる、というわけです。
二酸化炭素除去がアジェンダのなかで順位を落としているように見える一方、私の感覚では、現在ジオエンジニアリングが非常に急速に上昇してきています。つい先週、イギリス政府が屋外テストのプロジェクトを始めようとしているというニュース記事が出ていました。これが意味しているのは、〔ジオエンジニアリングの段階が〕概念上のモデル化や理論的研究から屋外での実際の実験へと移行しているということです。明らかに、こうした実験はきわめて限定的なものです。実際に完全規模でのジオエンジニアリングの実験をするというのは、もはや本当にそれを実行するのと同じことですからね。完全規模で実際にそれをやってみるまで、それがどういう働きをするのかは分からないのです。
ジェット機による成層圏への実際のエアロゾル注入に関する最初の実験が、スターダスト・ソリューションズという名前のイスラエルのスタートアップ企業――イスラエル国防軍(IDF)をめぐる技術的なエコシステムのなかに完全に統合されている企業です――によって昨年二月に実施されたという事実は、きわめて多くのことを教えてくれます。実際の物理的実践としてのジオエンジニアリングを世界にもたらしたのが、それとまったく同時に、ガザを破壊しているジェット戦闘機だったのです――このテクノロジーの誕生の仕方としては、なかなかのものでしょう? ジオエンジニアリングがこれほど前景へとのし上がってきている一つの理由は、気候危機に取り組むためのこのテクノロジーが、潜在的には――これについてはまだ分からないのですが――ドナルド・トランプのような人物の政治とも両立しうるということです。大気中のCO2蓄積こそが問題であり私たちはそれに対して何かをしなければならない、という事実をいかなる形でも承認することなしに、ジオエンジニアリングを行うことが可能だからです。
支配階級の「精神病理」とフランクフルト学派の洞察
ケーニヒ:あなたは「オーバーシュート・イデオロギー」を「根本的な狂気」であり、支配階級の理性というよりもその「精神病理」の表明なのだ、と記述しています。オーバーシュート・イデオロギーの増殖と持続を推し進めているとあなたが考えている心理的メカニズムについて、詳しく説明していただけますか?
マルム:この主題については『オーバーシュート』でも書いていますが、今年のたまたま10月7日に刊行予定の続編『長い熱』のなかで、ふたたび、今度ははるかに詳しく説明しています。私たちは一章を割いてジオエンジニアリングのフロイト-マルクス主義理論について素描しており、同時にある長い章で、この手の気候危機の否認こそが現在の危機の進展にとっての完全なる基盤となってきたのだと主張しています——システム全体としての気候危機の否認がなければ、それは実際にどこかの時点で止まることになっていたはずだと。
否認はこの危機に燃料を与えているものであり、否認は多くのさまざま形態をとります。どこかある時点で、それは抑圧へとひっくり返ることがありえます。もし一度ジオエンジニアリングが始まり、こうした硫酸塩〔を散布するための〕飛行機が使用されることになれば、その仕事は、文字通りの意味でグローバルな温暖化を抑圧することとなるでしょう。そして私たちの議論によれば、ジオエンジニアリングは、テクノロジーとして問題の実際の抑圧のための手段となるとともに、厳密にフロイト的な意味での抑圧の一形態として作用することになるでしょう。
もちろん私たちは、なぜ特定の歴史的局面において支配階級が特定のタイプの精神症状(精神病理もふくむ)を発展させることになるのかを史的唯物論的に理解することによって、このことを究明しようとしています。結局のところ、私たちはフロイト-マルクス主義者なので。私個人に関していえば、批判理論が行ったこと、そしてフランクフルト学派が行ったこと――それはマルクス主義を精神分析によって豊かにする結果になりました――を根底的に行なうことなしに今日の世界を理解することはできない、ということをトータルに確信しています。
南アフリカの白人農園主たちに対するジェノサイドが進行していると述べた、ドナルド・トランプの最近の暴言を見てみれば十分です。これが完全なる幻覚であるのは言うまでもありませんが、しかし他方で、ガザにおいては現実のジェノサイドがいままさに起こっており、その計画・組織・実行にトランプは手を貸しています。ここで起こっていることについて、そして右翼一般について理解したいと望むならば、ある種の精神分析のツールが必要なのは明白です。あたかも経済や物質的要因だけが事態を説明できるかのような、どんな純然たる唯物論的な思考によっても、こうした出来事を理解することは不可能です。ともかくにも現在の状況を何らかの仕方で理解するつもりなら、その心理的な次元に綿密な注意を払うことがどうしても必要なのです。
『化石資本』を十年後から振り返る
ジュレーマ:『オーバーシュート』の刊行は、あなたの博士論文の十周年に当たるものでもありました。それはのちにバーソ社から『化石資本――蒸気力の勃興とグローバルな温暖化の諸起源』として刊行され、以来、気候危機の社会的起源についてのカノン的な著作となってきました。そのタイトルが示唆しているように、『化石資本』は資本主義的な社会関係の増殖について、こうした複数の起源をたどったものです。とりわけ、十九世紀イングランドにおける蒸気を動力とした化石燃料経済の出現について。現在の目から、どのように『化石資本』を振り返っておられますか? そして『オーバーシュート』は、そこではじめて展開された化石資本の仮説を、どうような仕方で土台とし、拡張し、あるいは改訂しているのでしょうか?
マルム:『オーバーシュート』はある意味で、『化石資本』のなかで行なった〈流れ〉――私たちが今日であれば再生可能エネルギーと呼ぶであろうもの――の比較的な安さと豊富さ、および化石燃料ないし〈蓄え〉の比較的な高価さをめぐる議論に立脚しています。大きな違いは、『化石資本』がほとんど専ら需要サイドにのみ焦点を当てていたことです。私の関心はこうでした――なぜ資本家たちは水力から蒸気力へと移行したのか? 『化石資本』のなかで焦点を当てた資本家たちは、石炭を必要としそれを燃焼した資本家たちであり、石炭を生産し販売する企業ではありませんでした。私の評価によれば、そうした企業は転換を引き起こすうえで非常に重要な働きをしたわけではなかったからです。ですが『オーバーシュート』はほとんど完璧に供給サイド、すなわち化石燃料を生産する会社に焦点を当てています。これが大きな違いです。
一冊の本として、いかに『化石資本』を振り返るかということですね? そうですね、二つの混ざり合った感情があります。最初の感情は、ここ数年、蒸気エンジンをめぐる物語全体にほとほとうんざりしてしまった、というものです。他方で、大多数の研究者がそうだと思いますが、博士論文の執筆期間へのノスタルジアを感じてもいます。当時は一つのプロジェクトに焦点をあてて調査を、とりわけアーカイブ調査を行なうだけの時間がありました。アーカイブ調査は、他のいかなる研究にもまして圧倒的に喜びと楽しみに満ちたものだと私は思っています。歴史学的な調査をふたたび行えないということに、私はつね日頃から欲求不満を抱えているのですが、もうすぐそうできるようになると期待し、祈っているところです。
私の仕事について言えば、ウィムと一緒に今年刊行するつもりの『長い熱』を、『化石資本』とともに始まったサイクルを締めくくるものと考えています。私の心情は、現在の気候政治についてはもう何も書きたくない、というものです。私は自分に言えることは言ってきましたし、自分が行える貢献はすでに行ないました。その代わりに私がいま行ないたいと思っているのは、真に歴史的な仕事です。もちろん、世界が燃えておりそれがこれほど急速に進行しているなかで、そこから目を背け、ただ過去だけを振り返るのだと述べるのは、簡単なことではありません。しかしこれこそが、次の十年ないし二十年の私の個人的な野心なのです。
ケーニヒ:あなたは著作全体を通じて、特徴のある叙述スタイルを確立されてきたことと思います。マルム流の散文の読者は、史的唯物論による鋭利な分析、明確な例え、的を射たメタファー、そして挑発的なパンチラインからなる火炎瓶を期待することができる。『オーバーシュート』も例外ではありません。この本にはウィットに富んだ一節がたくさん含まれています。主流の気候政策による「頭字語による病的饒舌」への非難〔頭字語(IPCCのような、綴りの頭文字による略号)を多用することで気候をめぐる議論から一般の人々を排除していることを指す。p. 53を参照せよ〕から、再生可能エネルギーと化石燃料に関連する道徳的害悪を「万引きとジェノサイド」の比較と同一視する記述〔p. 188〕まで。あなたの叙述スタイルのインスピレーション――知的な影響と文学的な技法の両方の意味で――となってきたのは、どういう人たちなのでしょうか?
マルム:叙述について言えば、うまく書くべきだという『ニュー・レフト・レビュー』やバーソ社の理想に、私はきわめて忠実です。多くの学者たちは極度につまらない散文を書いていますが、そんなことは避けようと努力すべきです。あるテクストを読み通すことが苦痛であるべきではありません。私は生まれながらの英語話者ではないので、16年前に博士論文執筆を始めたとき以来、ある種のまともな質にとどく英語の散文をつくり上げるための独自の方法は、英語のフィクションをひたすら読むこと、それも可能なかぎりたくさん読むことでした――同時代の小説も、古典的な小説も。不幸なことに、そうしたいと思うほどフィクションを読むだけの時間は、いまはとてもありません。このことは、つねに欲求不満の種となっています。この数か月そうだったように、ストレスを受けているときにはほとんどフィクションを読むことができません。気が変になってしまいそうです。フィクションを読むことは、私にとって信じがたいほど重要な行為であり、スタイル〔文体〕と呼べるようなものを生かしつづける、唯一の方法でもあります。ノンフィクションだけを読んで優れた文体を身に着けることはできません。よい散文は、文学のなかでのみ見つかるものだからです。
スタイルについて言えば、もうすぐ出る私たちの著書『長い熱』にも少し触れておかなければなりません。私たちは読者が一気読みをしてくれることを望んでいます。少なくとも部分的にはエンターテインメントでもあるからです。この本には多くのジョークが含まれています。あるいはジョークの試みが。うまくいっているかの判断は読者次第ですが。それは大抵、くそ、放屁、排泄物などに関係するものです――この本の主要なテーマ自体が、そうしたものなので。ですから、この本はあなたたちが言ったような要素を、ユーモアや風刺と結びつけることを試みています。結果は読んでもらわないと分かりませんが、ここで目指したのは、私たちがしばしば「マルクス主義による読みやすいIPCC報告書」と呼んでいるものです。私たちの著書と本物とを区別する二つの特徴(二つだけではありませんが)があります。というのも、IPCC報告書は、マルクス主義でもなければ、とても読めたものでもありませんから! ですがここでの私たちの試みは、それを読めるようにすることであり、メタファーやパンチラインやマルクス主義理論やユーモアやあれやこれやを付け加えることなのです。
パレスチナのジェノサイドと「化石帝国」
ジュレーマ:パレスチナで現在進行中のジェノサイドに向き合うことなく、このインタビューを終えることはできません。新刊のパンフレット『パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである』のなかで、あなたは化石帝国についての以前の仕事――そこにはこのテーマについての2017年のSOAS講演も含まれます――を土台として、気候正義をめざす闘争とパレスチナ解放のための運動のつながりをたどっています。パレスチナの従属化が化石帝国のより長期にわたる歴史とどのように結びついているのか、そして二つの闘争がなぜこれほど深く織りあわされているのか、説明していただけますか? より話を広げれば、こうした洞察をもとにして、帝国主義と今日のエネルギー移行の関係をどのように理解できるようになるのでしょうか?
マルム:気候災害とジェノサイド・占領・シオニズムのあいだの結びつきの考察は、現在、おおくの多様な視点から行なわれている最中です。私がブックレット[編集部注:『パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである』]のなかで行なったことは、またしても、実際にアーカイブ調査を行なう時間があった時期の発見に由来しています。2013年頭、博士論文のための調査を行なっていたときの次の発見は、信じがたいほど魅力的なものに思われました。すなわち、戦争行為に蒸気船が使用された最初の瞬間は、中東を標的にした戦争においてだったのであり、パレスチナの〔港湾〕都市アッカーで生じた大きな戦闘においてだったのです。その結果アッカーは、完璧なまでに粉砕されました。
そのすぐあとで、もっと有名な第一次アヘン戦争がおこり、そこでは古典的な蒸気船である〈ネメシス号〉が中国を従属化させるうえで同様の役割を果たしましたが、それはこれよりも後のことだったのです。パレスチナでのエピソードは、シオニズムがイデオロギーとして結晶化した瞬間と同時に生じました。それはユダヤ人のシオニズムではありませんでした――キリスト教シオニズム、そして/もしくは世俗的でリベラルな英国ヴィクトリア朝シオニズムだったのです。ユダヤ人たちをパレスチナに配置しなおそうというアイディアに至った男性たちは、おそらく唯一の例を除いて、自身はユダヤ人ではありませんでした。かれらはキリスト教徒であるか、イギリス帝国の利害を推し進めたいと望んでいた単なる世俗的なリベラルの帝国主義者たちでした。例えば、民なき土地に土地なき民を与えうるというアイディアそのものが出現し、シオニズム・イデオロギーの基本的な指針が形成されたのは、この瞬間のことだったのです。
このことは、「パレスチナ紛争」についての歴史記述が現在にいたるまで見逃してきた事柄だと考えています。シオニズムの物語は普通、十九世紀終わりから語りだされ、その後、バルフォア宣言がある種のビッグバンのように捉えられてしまうからです。しかしこうしたことが、バルフォア宣言の77年前に起きていた。ですからそれは、純粋に歴史記述の視点から興味深い。はじめ、こうした素材を『化石帝国』と題し、私の博論の続編として公刊したいと考えていましたが、資金調達に成功しませんでした。未来のいつかの時点でそれをしたいという希望はまだ持っているのですが、1840年に起こったこと自体についても、掘り返されるべき物語や細部が数多く存在しています。とりわけ、中東にあるアーカイブ内の一次資料が、まだ掘り出されてないように思われるからです。起こった出来事についての同時期のオスマン側やアラブ側の資料を調べてきた人は、誰もいないようです――少なくとも、そうしたアーカイブ資料に基づいた英語での著述は存在していません。
このパンフレットのアイディアは、化石燃料とパレスチナの植民地化のあいだのこうした繋がりが、そもそもの始まりからそこに存在しており、まさしく今この時まで継続してきたのだ、というものです。このテクストは、私がベイルートで行った講演のために二三週間かけて執筆した講演原稿をもとにしています。本当だったら述べることができたしそうすべきだったと後になって認識した論点がいくつもあります。例えば、シオニズム国家体への主要な石油の供給者は、アゼルバイジャンです。しかしそれが本当に意味しているのはブリティッシュ・ペトロリアム(BP)社のことです。石油は、BPとアゼルバイジャン国営石油会社(SOCAR)が力を合わせて送り出しているからです。トビリシ〔ジョージア〕からジェイハン〔トルコ〕まで続くパイプライン〔いわゆるBTCパイプライン〕によって石油を送っているのはBPにほかならず、そこから石油は1948年の占領地に位置する港湾へと輸送されます。BP社は言うまでもなく中東で最初に石油を発見したまさにその企業であり、イギリスによる〔パレスチナの〕委任統治の柱は、私たちが今日BP社として知っている企業〔当時はアングロ・ペルシアン石油会社(APOC)〕によって運営されていたキルクーク・ハイファ間パイプラインでした。〔BTCパイプラインとBPに対しては、イギリスに拠点を置く〈パレスチナのためのエネルギー禁輸〉(EEfP)などの運動体を中心に、調査やキャンペーンが行われてきた。日本の伊藤忠商事とINPEXもこのパイプライン事業の出資者である。〕
それが依然として「英国の」ものであり、依然として同じ企業体が植民地化を行なう国家体に最重要の化石燃料を供給しているというのは、まったくもって異常な事態です。私がパンフレットに書けたかもしれないおおくの論点のうち、これはただの一例に過ぎません。というのも、ジェット機の燃料についての状況もまるごと残っているからです。ガザに残っているものをジェット機が破壊するのに使われているジェット燃料がアメリカ合衆国に由来していることを示す、優れたNGOの報告書が複数あります〔たとえば、SOMOやオイル・チェンジ・インターナショナルとデータデスクによる報告書など〕。ジェット燃料はテキサス〔バレロ・エネジー社の施設が存在する〕で精製され、その後、海を渡って1948年の占領地に位置する港湾へと輸送されます。占領の根本的な構造は、イェシュブ期、委任統治時代、おそらくそれ以前からさえ、まったく変わっていません。ですから、それ以来ますます深くパレスチナに食い込んでいる侵略行為は、まさしく1840年にそうであったように、西側の帝国によって支援され維持されている化石燃料の回路によって燃料が与えられているからこそ生じてきました。
ガザでのジェノサイドはいまや、〔このパンフレットを執筆した当時よりも〕さらに高い段階へとギアを上げています。住民の全面的な飢餓が、さらに攻撃的な侵攻が、そして日々数百人のパレスチナ人がひたすら虐殺されることへの完全な正常化のプロセスが生じています。こうした加速は、ドナルド・トランプのホワイトハウスへの帰還によって可能になっています。バイデン政権時からすでに凄まじい状況でした。バイデン政権時に石油とガスが凄まじい仕方で開発されていたように。そこに何らかの質的な違いがあるわけではありません。ただトランプは、ありとあらゆるものを解き放っています。何かへの名目上の制約という感覚すらも消し去っている最中なのです。ネタニヤフと彼の国家体がひたすら突き進みガザのあらゆるものを破壊することにアメリカが青信号を出しているまさに同じ時期に、彼は湾岸へとツアーをしてきたばかりです。トランプはサウジとカタールへ行き、カタール〔王室〕から――精神分析的にきわめて意味深い――空飛ぶ宮殿〔トランプに贈られた豪華な飛行機の通称〕を与えられました。そしてアメリカと反動的な湾岸君主国との同盟関係を確認しました。
トランプと湾岸君主国の同盟関係で問題となっているのは、基本的に石油とガスです。もし両側の政権がかくも化石燃料を愛し、かくも多くの利潤を化石燃料から得ていなかったならば、こうしたことは決しておこらなかったでしょう。もちろんここには複雑な関係があります。ある重要な関係は、湾岸で生産されている実際の石油やガスはもはやアメリカにとってそれほど重要なわけではない、ということです。アメリカはかつてそうしていたように中東からの多量の輸入を必要としていないという意味で。アメリカ人たちは、すでに世界最大の石油とガスの生産者になっています。湾岸からの石油とガスのはるかに多くの部分が、その代わりに現在、東方のアジア市場へと向かっています。〔湾岸石油の「東方シフト」については、後出のアーダム・ハニーヤの記事に詳しい。〕
ここで想起すべきある大事な点は、アメリカ帝国にとっての重要な基盤が、グローバル通貨としてのUSドルの地位だということです。USドルは、今度はそれ自体が、石油とガスがドルで取引されているという事実のうちに根本的な基礎を有しています。こうしたことが合わさって、単一のものとしては間違いなく世界でもっとも重要なコモディティが形作られており、それがドルで取引されているという事実によって、ドルは世界通貨としての地位を保ちつづけ、それによりアメリカのためのあらゆる特権を生み出すことになっているのです。言い換えればアメリカの帝国的地位は、ドルで取引される湾岸地域や他の輸出国からの石油に基づいたものです。たとえその石油とガスが最終的にどこで消費されることになろうとも。湾岸君主国はアジアとの取引を増加させるかもしれませんが、その取引が依然としてドルで行われているかぎりは、事実上アメリカ帝国の支えとなり、世界通貨としてのドルの立場を強化していることになる。
というわけで、中東はアメリカの帝国的権力にとっての重要性をひとつも失ってはいません――反対に、湾岸の国々は、より重要なものになりつつあるように見えます。ここには明らかに複数の矛盾が存在していますが、それはサウジアラビアと友達になりたいという欲望と占領者〔イスラエル〕に望むがまま好きにさせたいとい欲望とを調停させることが、しばしば困難なためです。というわけで差し当たり、〔イスラエルとサウジアラビアのあいだの〕正常化プロセスは保留中のようです。これはサウジアラビアの人々がすくなくとも何らかの形でパレスチナの人々のことを気にしているからではありません。それはただかれらが、イスラームとその聖地の守り手としての役を演じるというイデオロギーを持っているからであり、みずからの行動の可能性について、いくらかのイデオロギー的制約を課されているからなのです。すでに述べたように状況はある意味では複雑で矛盾しているのですが、別の意味では、それはきわめて単純かつむき出しなものです。
これからの十年間をどう生きるのか
ケーニヒ:気候カオスの資本主義的起源の分析のほかに、あなたの著作で繰り返し回帰する主題として、抵抗というテーマがあります。『オーバーシュート』では、エクアドルの事例のような、比較的最近の抵抗の例に取り組まれていますね。2023年8月、エクアドルの人々は、民主的な投票によりジャスニ国立公園〔日本語では「ヤスニ」と表記されることが多い〕の化石燃料資産を座礁させることで、歴史に名を残しました。あなたとカートンが「徹底した錯乱」の年と呼ぶ時期における、ラディカルな不服従の行為です。同時に、あなたはアーダム・ハニーヤの素晴らしい著作『原油資本主義――石油、企業権力、および世界市場の形成』への最近の宣伝文で、こんなジョークを書いてもいます。読者は「これを読んで、さっさと逃げ出す」べきだと――化石資本主義の現在の布置における抵抗の見通しを、どれほど救いのないものとお考えなのでしょうか?
マルム:現在の趨勢と気候の状況を目にして、そしてこのジェノサイドを追いながら、どうして希望をもっていることができるでしょうか? 言うまでもないことですが、いくらかでも正気な人々にとっての圧倒的な心情は、痛烈かつ抑制不能な絶望だと思います。それでは、その絶望を抱えながら、何をするのか? 私たちが生きているこの社会の、可能な限りもっともラディカルな拒絶へとしがみつくことです。この社会で生きる個人として、こうした立場をとることが困難なのは言うまでもありません。それは単に社会から物理的に撤退し、何であれ自然がまだ存在しているどこか遠くの場所に落ち着くことを意味しているのでしょうか? 必ずしもそうではない。私の聖なる三位一体は、マルクス、アドルノ、そしてフロイトですが、近年では、彼なしでは間違いなく生きていられないと答えるのは、アドルノです。彼が最後にたどり着いたのはこういう言葉です。そうだ、確かに社会はトータルにいかれ切っており、私たちは社会が生み出す破局を止める立場にはない。しかし唯一の倫理的な立場は、抵抗という立場によって存在が許される。それはトータルな、原理的な、献身的な、そして妥協を排した抵抗という立場であり、そしてもちろん、それが私のいまの心情です。
それは、現実にはなにを意味しているのでしょうか? ニューヨークで起こったばかりのことから、ある種の政治参加的な撤退まで、おおくの多様で幅広い選択肢について議論することができるでしょう。フランクフルト学派の面々のおおくは、最終的に後者の道を選びました。次のように言うことは、魅力的な選択肢ではあります――このいかれた社会を心底から憎んでいるが、私は活動家として、オーガナイザーとして、できることはすべてやってきた。だからこれからの十年は、ただ本を書くことにのみ費やすつもりだ。社会がこれほど完璧にいかれ切ったものになったのはどのようにしてなのか、そして人々がいかにそれを止めようとしてきたのかについて、私の見方を差し出すために。
もちろん、そこにはスペクトラムが存在しています。可能なかぎり最も闘争的な自己犠牲の殉教行為が一方にあり、もう一方の端にはアドルノ流の政治参加的な撤退のような何かがある。後者の場合は、社会をとことん憎み、それに絶望しながらも、その立場をただテクストのなかで表明して終わることになります。多数の人々と同じように、私もこの両極のあいだのどこかで宙吊りになっているように感じています。ときにはその両方を試みることもありますが、そこにも難しさはある。
気候運動の未来
ジュレーマ:『オーバーシュート』で明らかにされているのは、資本家階級は依然として、数十年にわたる化石燃料の継続的な採掘と燃焼に深く投資したままであり、政治的状況がそのプロジェクトに好意的でありつづけるとかれらが予期している、ということです。一方で気候運動の側は――差し迫った崩壊によって突き動かされながら――しばしば非常に狭い地平のうえで行動しており、次のアクション、サミット、ないし選挙のための動員に焦点を当てています。その最大の勝利ですら、それが化石燃料の巻返しや反撃に対して防衛されないかぎり、不安定なものでありつづけます。このジレンマを、どのようにお考えですか? 気候運動は戦力的プランニングや制度構築を長期的に作り上げることで、その成果を維持するべきなのでしょうか?
マルム:まさしくこの手の議論を行なえるような気候運動が、現に存在していればよかったのですが。ヨーロッパの気候運動は現在、それが数年前、2018年と2019年の抗議のサイクルのあいだにとっていた姿の、完全なる影でしかありません。当時の運動が『パイプライン爆破法』の背景をなしていました。どのような戦術が活用されるべきなのか。そして私たちはより長期的な戦略やその手の何かを形成することができるのか。私たちはいまや、どちらかといえば真空のなかにいる言うべきです。ですから、気候運動がこうすべきでありこうすべきでないと考えている、と発言するのは非常に難しい。なぜならそれは勢力としてはもはやほとんど存在していないからです。このことはまさに途方もない敗北の一つのサインです。しかし、あちらこちらで予兆に目を留めている人々も存在します。少し前に書かれたもので、今もまだ気候のことを気にしている人々は、よりラディカルな戦術を採用しようとしている、と主張する記事が『ガーディアン』に出ていました。
イギリスは特殊なケースです。平和的な市民的不服従が、XR[絶滅への反逆]のような諸運動で完全に支配的になっているからであり、なにかサボタージュを行なおうと思った人間は、イギリスでは超異常な存在とみなされることになります。フランスでは、人々はそれをずっと行ってきました。だから状況が全然ちがうのです。フランスは、私自身の住むまったく意味を持たない国スウェーデンを除いて、ヨーロッパで唯一、私が近年いくらかの時間を過ごしてきた国です。他の国々とは非常に状況がちがっていて、比較的に言って、とても躍動的な環境運動が存在しています――まずなによりも、〈大地の蜂起〉があります。しかしかれらは、例えばエンデ・ゲレンデがそうであった(あるいは今もそうである)ような、狭いないし正確な意味での気候運動ではありません。はるかに幅の広い運動なのです。〔大地の蜂起については箱田徹氏の紹介によるこの記事やこの記事に詳しい。〕
ヨーロッパについて話すなら、どこかの時点でふたたび事態が動きだすことを期待している、という以上のことは言えません。私はそうなってほしいと思っているのですが、次なる気候災害の季節には、人々は路上に出て、単に――昨年のバレンシアの恐ろしい洪水のあとに起こったように――自分たちを守ってくれない地方自治体を攻撃するだけにとどまらず、実際にみずからの怒りを問題の根源へと向けることになるでしょう。すなわち、化石燃料企業に。これは私はつね日頃くり返しがちなことですが、気候運動にとっての大きな課題は、事態が熱くなっているタイミングで一撃を与える能力を発達させることなのです。〔同様の議論は、たとえば『パイプライン爆破法』の補論(邦訳218-225頁)などで行なわれている。〕
ですから実際に気候災害が起こったときには、外に出て、そうした災害の根源を標的とした闘争的な行動をとることです。何が災害の根源なのかを、人々に明確するために。もしこれが良くないと考えるなら、メッセージを発すること。もし私たちが根源を放置し、災害のもっと奥深くまで私たちを追いやりつづけることをただ許しておくなら、状況は悪く、ますます悪くなるばかりなのだと。そしてこれこそが現在の状況です。これまでのところ、私たちはまだそうした行動を目にしていません。しかし、これはどうしても起こらなければならない、質的なブレイクスルーなのです。そのあとにはもちろん、長期的なプロジェクトの構築が必要になるでしょう。
最初に話を戻せば、コロンビアに関するある心惹かれる事柄は、私が人生で本当に一度たりも見たことのないものが、そこには存在していたということです――国家装置における権力の(少なくとも名目上は)最中枢の座、すなわち大統領府・大臣・省庁と、国の周辺部の路上で闘争を繰り広げている社会運動とのあいだに、関係が存在しているのです。そしてこれらの運動と国家とは、実際にことを成し遂げようと力を合わせています。
これはある意味で、夢のシナリオのようなものですが、この夢は、左派が国家権力を失った場合、コロンビアでは非常にはやく終わりを迎えてしまうかもしれません。しかし言うまでもなく、こうした種類の権力の長期的な投射は、必要なものなのです。どこかの時点で、国家権力を勝ち取らなければなりません。これはコロンビアで実際に起きたことであり、コービンのイギリスで、そしてサンダースのアメリカで起きそこねたことです。もしそれが起こっていたら、イギリスとアメリカという二つの国家は、現在見せているのとはまったく別の姿をしていたはずです。■
ベルナルド・ジュレーマ(Bernardo Jurema)は、ベルリン在住の政治学者・気候研究者。ブラジルのヘシーフィ(Recife)出身。エリアス・ケーニヒ(Elias König)はオランダのトゥウェンテ大学の博士課程学生(人文学)。研究テーマは気候正義、および化石リベラリズム以後の政治理論。
翻訳:中村峻太郎
©Protean Magazine, reprinted with permissions by editorial team and authors.
使用写真:Mural of Theodor Adorno by Justus Becker and Oğuz Şen. Senckenberganlage, Frankfurt, via Wikimedia Commons
公開日:2025年7月21日
最終更新日:2025年7月23日