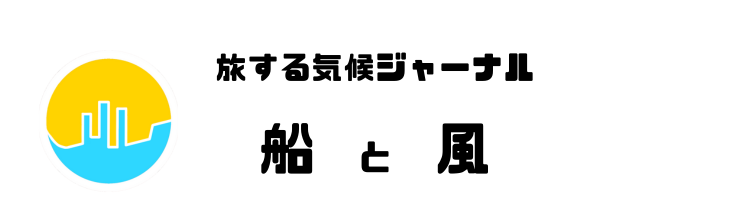海岸線におけるハイドロフェミニズム
Hydrofeminism on the Coastline
サラ・べザン、アストリダ・ネイマニス
Sarah Bezan (University of York, UK), Astrida Neimanis (University of British Columbia, Canada)
海岸線という海と陸が出会う場所について
サラ・ベザン(以下、SB):『水とともに考える』(セシリア・チェンとジェニン・マクラウドとの編著。2013年にMQUPから出版)から『水の身体:ポストヒューマン・フェミニスト的現象学』(Bloomsburyより2017年に出版)まで、あなたの仕事は、クリティカル・セオリーにおける水文学的転回 hydrological turnのうちに確固たる位置を占めてきました。例えば、『水とともに考える』への共著のイントロダクションにて、あなたと共著者は、私たちを取り巻く水との関係、権力、そして関与の流れについて水文学的転回が新しい思考法をいかに促すものであるかを論じています。これは身体を包含しています。この身体とは、開かれていて常に循環する惑星的な水の再生と常に関わり続けている、そうした多孔的で不安定な存在としてあなたが捉えているものでもあります。海岸線についてのあなたの今の省察をとても魅力的なものにするのは、まさにこの関係の流れへと向かう転回です。私たちの多くにとって海岸線とは、ゆらぐことはない明確な領域、あるいは境界線です。境界線とは、満ち引きする潮汐によって画定される目印を持ち、また境界の交差が種と共同体、陸と海を越えたあいだで起きるものだと想像される空間です。しかし、あなたにとって海岸線は何を意味するのでしょうか? あなた自身のポストヒューマン・フェミニスト的現象学の枠組みを通して考えることで、海岸線との出会いはどのようなものになるでしょうか?
アストリダ・ネイマニス(以下、AN):
第一に、私は、海岸線はすでに抽象、平均、あるいは標準であると思っています。海岸は、あなたが絞りを合わせたときにのみ、「線」となります。それに従えば、あなたは海岸を「線」として人為的に固定させます。線は、時間の流れから海岸を抽象化するスナップショットであり、そこでは風雨に当てられて風化することもなければ、浸食されることもありません。しかし、時間の厚みのなかでは、線は実際、ぼやけていきます。線は、物事が起きる場所なのです。推移、変遷、生成、異なる形への変貌、これらは海岸の領域によって生産されるものthe laboursなのです。
言い換えれば、海岸線とともに考えることは、水が私に教えてくれた他の二つのことを思い浮かばせてくれています。第一は、膜的な論理 membrane logicです。私が「ハイドロフェミニズム」というエッセイにおいて示した水を具体的なかたちに表すことという観点から見ると、接続は、水が特に浸透性のある膜を横断し、あるいは通過したときに生じます。視覚中心的な文化のなかでは、これらの膜のいくつか、例えば人間の皮膜は、非浸透性の幻想を見せます。これは、私たちが汗をかき、水を摂取し、放尿をし、血を流し、といった事実によって、偽りだとわかるのですが。私たちは、世界を部分的に取り入れ、またそれを再び洪水のように放出しています。他の世界に存在する膜は、あまりにも儚く、あるいはあまりにも途方もないために、このように認識することはできません。そうしたものとして例えば、重力的な閾値、気象における前線、悲しみの壁、冬のコート、死などが挙げられます。しかし、同じように膜的な論理で機能するものもあります。それは水がつねに異なるものへと生成する、そうした選択的で部分的な水の推移の働きによってです。推移のなかで差異は生じます。私たちは、私たちの具体化における横断的身体 transcorporeal(ステイシー・アライモの用語を使えば)であり、しかし、私たちは全面的な溶解から私たちを保ち続けるためには膜を必要とします。
第二に、あなたの疑問はエコトーン的思考を思い起こさせてくれます。エコトーンは二つの隣接するエコシステムのあいだで推移する場所です。エコトーンは、接続また/あるいは分離という目印として考えられているだけではなく、生態学的用語では、豊饒性、創造性、変化、増加、多様性、そして再編成も意味しています。例えば、河口、潮間帯、湿地帯は、すべて境界的な空間 liminal spaceであり、ここではカトリオーナ・サンディランドの言葉に従えば、「二つの複雑なシステムがお互いに出会い、含み合い、衝突し、変化します」(2004)。それゆえ、エコトーンもまた膜の一種なのです。くわえて、私たちは一本の線ですらひとつの領域、場所、あるいは環境であることに気づくでしょう。境界的なエコトーンは、あるものが他のものへと変わる境界であるだけではなく、それ自体が重要で素晴らしい水の身体でもあります。「物体」と「プロセス」、「動詞」と「名詞」、あるいは「身体」と「生成」といったあいだのいかなる差異もぼやけていきます。
膜とエコトーンとともに考えることは、境界が存在しないと主張することと同じではありません。私たちは、絶滅に抵抗するために境界を必要とします。水の身体であることは、水であることとは大きく異なりります。水の身体であることは、水が存在するだけであたかもそれ自体で特定のかたちを作り上げることができると考えることではありません。この安易な感覚のもとでは、水であることは形作られていることを意味しません。それは意味のない物質性なのです。水の身体であることは他の水の身体への出入りする流れでもありますが、それはしかしながら、関係から意味を産み出すことです。水の身体として、私たちは、時間、場所、関係からの抽象化への誘惑に抵抗します。私たちはすべてを崩落から防ぐためにある種の膜、ずた袋(訳注1)、あるいは境界を示す領域ないしは線を必要とします。世界のなかで存在するためには、水は身体を必要とし、また他者に影響を与え、他者から影響をうけるような身体であるためには―いかに儚く、多孔的で、一時的であれ―ある種の囲いを必要とします。
そのため、こうした水の存在論の内側から海岸線を考えることは、線あるいは境界は実際に、一方では海、他方では陸、他なる身体がこれらを一緒にすることを可能にするものを生み出していること、この考え方に沿っていくことを意味します。しかし、線は物事が起こる領域であり、この出来事は反響し、回折的なもの(訳注2)であることも私たちに気づかせてくれます。線は、他の身体、あるいは関係性、身体それ自体の領域における関係性の運動なのです。
協働的な実践としての水の物語
SB:
第13回上海ビエンナーレで行われたPower Station of Art(PSA)との近年のあなたの共同プロジェクト、「水の身体」(2020-2021)で、あなたは起源と終焉が固定され、安定してきた哲学的伝統に対して、水の流れがいかに挑戦できるかを考察していました。このイベントでのあなたの執筆の一部や協働の芸術作品、「河川は海となって終わる」は、河口がいかに主体の位置を不安定にするかを考察することにより、この伝統を押し返しています。この企画の背後にある動機を説明してもらってもいいでしょうか? どのようにしてあなたたちの協働が様々な場所の水のインフラストラクチャー、例えば黄浦江や長江デルタ、あるいは他の水の身体に寄与するのでしょうか? そして最終的に、批判的-創造的な協働に参加することは、あなたにとってどのような価値をもつのでしょうか?
AN:
「河川は海となって終わる」は、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州シドニーで行われた共同プロジェクトで、ガディガル/ビッジガル/ダラグの長老であり、シドニーの「ワラネ」沿岸地域の昔ながらの子孫であるロンダ・ディクソン・グロヴナーおばさん、シドニーを拠点とするアーティストのクレア・ブリトン、そして私の三人で、2020年から2021年にかけて行われました。その後、本プロジェクトは(異なる形で)上海ビエンナーレにも出展しました。ビエンナーレのキュレーターであるアンドレス・ハケは、ビエンナーレのカタログに私に寄稿するよう誘ってくれましたが、私は何か実践を支えにしたものも提供できるかもしれないと提案しました。私がまだシドニーにいたとき、アンドレスの誘いがパンデミックの始まりのころに届きましたが、すでにご存じの通り、その年の終わりには私はブリティッシュコロンビア大学オカナゴン校の新しい職につかなければなりませんでした。私は終わりについて多くのことを考え、当時借りていた家のそばを流れるクックス川沿いを一日のうち何時間か(COVIDの「ソフトロックダウン」のもとで)歩いて過ごしていました。私の同僚であり、今や友達となったクレアは、実践に基づいたゆっくりとした実験的手法でクックス川に取り組み、博士論文のプロジェクトを完成させつつありました。そこで、私は、私たちが何か一緒にできるかもしれないと考えました。クレアは、彼女の友達であり、時として共同制作者でもあるロンダおばさんを私に紹介しれくれました。ロンダおばさんのことは、気候変動や脱植民化をめぐる集会やイベントで強烈な存在感を示していたことから、以前から離れてはいたものの知っていました。
川沿いを歩き、草むらに座り、私たちの生活で起きていることを共有する、そんなことを何時間もしたあとに、散歩に関するアイデアを思いつきました。ロンダおばさん、クレア、そして私は、潮の引きの循環(おおよそ7時間)に合わせて公開の散歩に参加したらどうか、地域の人々に提案しました。この散歩は、一日の終わり、潮の終わり、季節の終わり、十年の終わりを記すための時間として設定されました。当日、ロンダおばさんによる非常に感動的な「ウェルカム・トゥ・カウントリー」(訳注3)とともに散歩は始まりました。私たちはそこから歩き始め、シドニーのクックス川という水の身体を辿りました。クックス川は、インナーウェストゴルフ場にある名もなきコンクリート水路から始まり、別の水の身体であるボタニー湾、そして太平洋へと流れついて終わります。私たちの目的は、ワンガル、ガディガル、そしてガメイガルといった地域を流れるものとして河川自身の物語(そして特に、いかにロンダおばさんの生存 survivanceの物語の一部となっているか)を補足し合うように他者を招くことであり、また同時に、終わりと推移についても話し合うための機会を設けるためでもありました。結局のところ、2020年と2021年は、はっきりとしたかたちで現れているように見えたありとあらゆる種類の終わりに私たちの多くがもがいていた年でした。その終わりとは、パンデミックのために失われた命、気候変動によって失われた種、そして植民地主義によって失われた生活のあり方があるでしょう。私たちは考えました。何かとして終わり、何かへと変化する河川のリズムに合わせてリズムをゆっくりとすることによって私たちは何を学びうるのでしょうか? どの終わりもまた始まりであります。また河川の終わりは河口 the mouthとも呼ばれています。
散歩が企画のメインイベントでしたけれども、「河川は海として終わる」は他の様々な形態を取りました。クレアの研究に触発されて、織り込んだテキストをクレアと私が読むこと、ビエンナーレでの総会がその一つです。あとは、クレア、ロンダおばさん、そして私による共著でのエッセイであるアコーディオンのように開くことのできるリソグラフ印刷による本、これは散歩と河川そのものとの反響でした。さらに、河川沿いで見つけた些細なものから鋳造された小さな銀の彫像、散歩を記録した写真、そしてビエンナーレやその後も様々な場所で公開された「ロンダおばさんの散歩」というショートフィルムなどです。しかし、こうした成果以上に、この企画の中心は、河川、クレア、ロンダおばさん、私とのあいだの対話にありました。つまり、知識や視点、教え、疑問、疑い、警戒、ぬくもり、美しさ、これらの共有です。これらを言葉にするのは私にとって難しいことです。
この類の実践は、身体的な哲学です。身体としての感覚装置が物事をあなたに明らかにしてくれるがゆえにのみ理解できる物事があります。ここで私が言っているのは、河川のリズムや物質的な細部だけではなく、河川が保持し、育んでいる関係性のことでもあります。たとえ、私たち(ここで私が意味するのが入植者としての「私たち」)が、その河川の保持や関係性への責任を満足に果たせていなかったとしてもです。この企画は公共の散歩として、フェミニズム的であり、反植民地主義的な社会的インフラの実践的な実験でもありました。異なる身体が互いに一時的に集まり、共有し、支えることができ、またこれらの交換のなかで何かを学ぶことのできるつかの間の儚いシェルターとしてのインフラです。散歩それ自体が、この種のインフラでした(テッサ・ゼッテル、ジェニファー・ハミルトン、そして私は、このことについてAustralian Feminist Studiesで書きました)。私にとって、この種の批判-創造的協働の価値は、それゆえあなたが文化理論家あるいは哲学者として提起し、さらに実験を通して発展させ、精緻化させる理論を試す場となっていることにあります。私の興味を引いたことは、私自身の方法と私が一緒に仕事をしていたアーティストの方法とのあいだに共鳴が見られたことです。アーティストの方法において、作品はその物質性のなかでのみ現れうるのです。アイデアは、それを試してみるまでは、何ものでもありません。私自身の仕事が徐々に協働的な実践に依拠した研究手法に合わせられていくに伴って、私は自分の叙述のなかで概念の背後に隠れるのが不可能だと思うようになりました。実際、私は徹底した正直さを求められるようになっています。「これは哲学的に洗練されているのか?」、と10年前であれば私が自分自身に投げかけられていたであろう品質管理についての問いは、「世界のうちでこれは耐えられるのだろうか?正直なのか」という問いへと変わっています。つまるところ、試してみよう、と。文化理論においては、正直であることは賢くあることよりはるかに難しいのです。
人新世という石質的なものへの執着
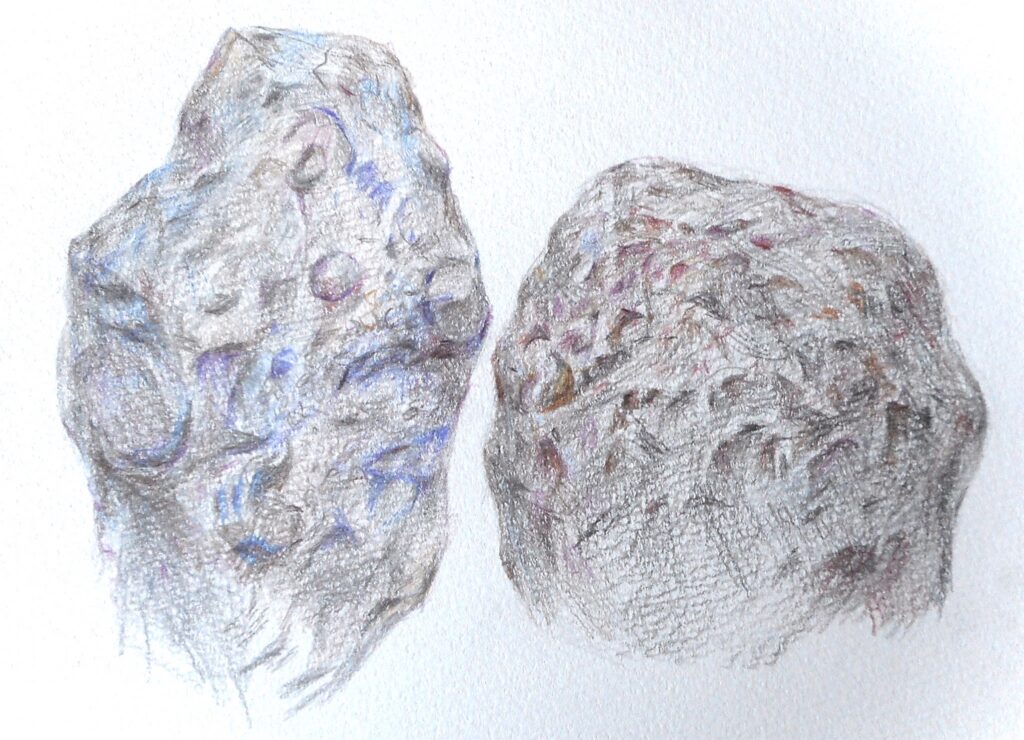
SB:
起源と終焉についてのさらなる議論を進めるために、人新世の研究における地質学的転回に対して、水文学的転回がいかに寄与したのか、さらにどのように分岐したのか、これらについてより知りたいと思っています。地質学的転回は、悠遠な時間 deep timeを横断する地形=地層を作り変える geomorphicアクターとしての人間について思考する方法として理解できるでしょう。しかし、いくつかの方法におけるこうした地質学的アプローチは、男性中心主義的、植民地的思考の連続性に資するものでもあります。リチャード・グルージンが『人新世におけるフェミニズム』(2017, ix)において指摘したように、「人新世」という用語の命名に関与した科学委員会はほとんど男性で構成されています。同様に、キャスリン・ユソフによる『無数の黒人の人新世、あるいは何も存在しない』(2018, xii)における採掘主義的経済についての分析は、採掘主義的資本主義についての堆積した理解がいかに人新世を支える人種的、植民地的遺産が今も続いていることを覆い隠してしまう、その危険性を明るみに出しています。ダナ・ハラウェイの論じる触手的 tentacularであり、水のような概念であるクトゥルー新世は、そうした堆積的 sedimented思考と戦うための一つの方法です。同様に、ブルー・エコロジーという興隆しつつある領域におけるステイシー・アライモ(2017, 89)の仕事もこれらの点に狙いを定めており、彼女は「男性と岩という荒涼とした大地的表象 terrestrial figurationsにおいて他の生命の形態や生物学的プロセスが奇妙にも欠如している」と論じています。あなたのエコフェミニズム的、また水文学的枠組みは、地質学的転回へのこの批判の一部をまさになしているかと思います。海岸線が陸地的空間であり、水の空間でもあることを考えるならば、水文学的転回は、海岸線の想像力についての私たちの理解に何か付け加えることができると考えていますか?
AN:
それでは、「人新世への執着 Anthropocenomania」に少し戻ってみましょう。あるいは、新千年紀の第二の十年期〔つまり、2010年代〕とでも呼んでもいい時代、これは「人間=男性の時代」についての新しい提起に無我夢中で取り組むようなさらなる会議、さらなる論文、さらなる賢い議論、そうしたどのような学術関係の話をしても出くわすことになる時代のことです(たしかに、私もしばらくその熱に取りつかれていました)。人新世への熱があったことはたしかですが、特に興味を引く事柄は、岩石の物質性です。つまり、「地質学的転回」は他の何よりもまして、堅固さと測定いう石質的な lithic想像力に関するものでした。
人新世は、根本的に時間や状況、感情に対する人間の関係性の索引であり、そのようなものとして、男性=人間の時代が始めた新しい類の時間に取り組むように要求するのです。いわゆる近代的世界における人間存在として、私たちは、個人の人生のスケールにおいてだけではなく、私たち自身よりも広大な道徳的行為者としての人間の歴史のスケールにおいても、生の困難な取り組みに直面してきました(e.g. Chakrabary 2009; Clark 2012)。
人新世は、その始まりにおいてこの二つの要求をさらに悪化させてきました。それはつまり、西洋的な宇宙観に染まった人間が、人間自身を人間の時間のスケール以上のもののうえに表さなければなりませんでした。もちろん他の「私たち」は、この点についてはるか昔から理解していました。人間の時間を超えた時間性についての理解は、他の非西洋的な宇宙観の一部でしたが、西洋近代の人々は多くの場合、この教訓を見逃していました(ダーウィンによる進化の発見は、私たち人間自身が人間の時間を超えていることを理解するのを助ける重要な仕事だったのですが)。個人と歴史との衝突は、すでにある種のスケール的眩暈でした。いまや、私たちは人新世の挑戦を付け加えるべきです。つまり、悠遠な時間という観点から見たときの私たち人類という種としての全くの無意味さと、人類による地質学的時代の創始、これら二つのあいだのスケールの矛盾です。私たちの時間に対する情動的な関係は、安定したものではありません。すなわち、私たちは本当に、そんなに小さいのか、あるいは大きいのか? 私たちはどのように感じるべきなのか?
言い換えれば、人新世の不安定さの一部は、時間的な支えを失ったことにあります。私たちは、世界において私たちが問題=物質となるようなスケールに対する支配力を失っています。結局のところ、想像されるポスト人新世的未来において、私たちは自分たちがいた場所を見つけたい、自分たちの記録が残っているところを見つけたいと思っています。フェミニスト哲学者であり、文化理論家であるクレア・コールブルックは、「ナルシスト的原-喪 proto-mourning」という身振りとしてこの欲望を論じていました。この欲望は、「死と欠如が私たち自身の断片の非可読性を通して表象されるものとして、ポストヒューマン的未来の悲劇を想像する」ことを意味します(Colebrook, 40-41)。人新世は謙虚さへの誘いかもしれませんが、存続したい、読み解かれるものでありたい、という切迫した欲望を伴っています。ここで、私が指摘したいことは、人間のナルシシズムを非難することではありません。人間自身の存続への関心は、めずらしくもなければ、倫理的にも問題でもありません。より興味深いのは、時間的な大変動もまた情動的であるということを欲望が浮き彫りにする点です。私たちはここにいた、私たちは不可能な未来の読者に私たちに伝えてほしい、そして切望と後悔が伴っているのですが、少なくとも私たちがまだいることを私たちのアーカイブに主張してほしい、そう思っています。言い換えれば、人新世のトラウマとは、私たちが知っていたものとしての時間との同期がずれてしまったことへの感覚についてだけではなく、この非同期性が到来することについての「悪い感覚」、この両方に関わるのです。
それゆえ、地質学的転回が重要となった背景が整ってきます。なぜならば、人新世は生物圏、大気圏、そして水圏(無数の社会文化的諸世界に言及せずとも)に重大な帰結を引き起こすとはいえ、その解釈や翻訳は地球科学、特に層位学における適切な対象として生じてくるからです。結局、論争的なゴールデンスパイク(訳注4)の発見を担っているのは、人新世作業部会のホストである国際層位委員会なのです。
この点が私の好奇心を駆り立ててくれます。なぜ層位学なのか、なぜ今なのか?人新世における時間的な錯乱を考えれば、地質学は、時間を管理し、時間や時間との私たちの関係を管理するための安楽にしてくれる方法を与えうるのでしょうか?私たちは、これらの層位学的視覚化について見てきました。そこでは、それぞれの地質学的年代あるいは、「~世」が、地球という〔スポンジを何段も重ねたような〕ケーキのスポンジの層にその幅を割り当てられています。すべての「~世」の記録は、始生代、原生代、古生代、カンブリア紀から古第三紀、始新世、漸新世、中新世…と続いて、比例して積み上げられています。私たちが自分自身を悠遠な時間のこれらのページへと書き込むことは、人間の小ささを強調することになるでしょう。そうだとしても、これと同時に、あるひとつの層位学的スナップショットのなかへと世界におけるすべての時間を捉えることによって、〔人間との〕宇宙的な無関係さを反転させることに安堵するのです。もし岩石圏が記録の媒体だとするならば、私たちが思うに、岩石は、壊れることのない銘板を私たちに与え、私たちの正確な場所をそれでも印してくれる基準も与えてくれるでしょう。もし私たち人間自身の持続性が不確かになったとき、私たちがしがみつくことのできるいかなる露頭を探し求めることは驚くべきではありません。言い換えれば、時間的なジレンマとしての人新世という文脈において、私たちは層位学と地質学的転回を、この時間的なねじれ、さらにそのねじれが引き起こす不安までも統制しようとする試みとして理解できるでしょう。
こうした地球を管理する想像力 geomanagerial imaginaryは、時間を測定可能で、進歩的で抑制可能なものとして捉えられるようにするかもしれません。しかし、この抑制、そしてある特定の可読性を記録しようとする努力が何を覆い隠しているのかを私たちは問わなければならないでしょう。おそらく、私たちは違った種類のアーカイブを必要としています。これが、地質史的記録を読むための別なる方法として、すべての「別なる時代 alter-cene」が入り込むところです。私にとって、これが水とともに考えることの転回へと誘ってくれます。水は記憶します(アーカイブ)が、水はまた忘れもします(溶解や浸食)。物語の刻銘や石質的な繋がりを通してではなく、かわりに水に浸り、沈み、繋がりをほどくことによって、人新世における時間や感情との私たちの関係性を理解しようとすることは何を意味しうるのでしょうか?
この提案の一つの問題は、石質的なものと水的なものが互いに分けられていると提案していることであり、それはあたかも私たちは一つを選んだら、もう一つを拒絶しなければならないかのように考えていることです。私たちの日常の世界では、岩石と水は、内的-行為 intra-active (訳注5)の関係のうちで密接に結びついています。さらに、石質的なものは、人新世における想像力において時々なされる主張よりも、より情動的であり、変化に富んだものであります。ユソフが『無数の黒人の人新世、あるいは何も存在しない』において、「白人の地質学」への対抗として黒人の詩学に着目しようとした点がまさにそうです。彼女は、石質的なものを唯一の選択肢ではないと示すことによって、植民地的で白人至上主義的な関与を脱自然化しています。それゆえ、地質学的転回への批判的な評価は、岩石、あるいは地球=大地から離れることと同じではありません。これはむしろ、エレメントに基づいた感情の新しい可能性を開くこと、さらに水はこのための触媒となりうるのです。
これらすべての議論は、海岸線的想像力への私たちの理解に何か付け加えうるのでしょうか? この疑問は、最初の疑問の私たちを引き戻してくれます。私たちはエコトーン、つまり物事が出会い、推移し、異なる何かへと生成する沿岸帯に戻るのです。
もし私たちが上手くやれたら? 破局の物語に抵抗する
SB:
出来事と推移の場所である沿岸帯に戻るために、または「人新世への執着」という抽象的な時間性からどうにか離れるためには、私たちは海岸地帯の洪水について考えてみる必要があるかと思います。こうした洪水は、気候変動が抑制されなかった結果として、まさに今起きつつあることです。私は特に、南アフリカ東部クワズール・ナタール州の沿岸地域ダーバンで今まさに起きている洪水、あるいは世界の平均海面上昇率を上回るペースで進行しているインド沿岸部の海面上昇について考えています。多くのアーティストが、水没した都市の描写を通じて、沿岸部における洪水よって引き起こされた気候難民危機に関与し始めています(例えば、ユリア・ドツェンコによるデジタル・ペインティングとして「水没都市 2100」、あるいはキプロスのアヤナパなどの沿岸地域に設置されているジェイソン・デ・カレス・テイラーによる水中彫刻公園があります)。海岸線をめぐるポストヒューマン的な水の想像力としてこれらの事例は、沿岸地域に対する気候変動の不均衡な負の影響を厳しく予示していると思われるかもしれません。しかし、特にデ・カレス・テイラーの作品のように、海の生命の繁栄へと繋がる水による人間の溶解という創造的実験として見ることができるかもしれません。あなたはこれをどう考えますか?

Aphrodite Among the Corals (Sunken Cities 2100), by Yulia Dotsenko, 2020. (https://www.instagram.com/yuliadotsenkoart/p/CKEAPPxDyin/ 2025/7/8アクセス)

Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa (MUSAN), by Jason de Caires Taylor, 2021.
(https://underwatersculpture.com/projects/ayia-napa-musan/ 2025/7/8アクセス)
AN:
まずもって第一に、私たちはそれ〔水による人間の溶解〕を人為的な破局と見なすべきです。なぜならば、この破局は、すでに生命やそれを取り囲む世界を犠牲にしており、またより多くのものを犠牲にし続けるからです。これらの事柄について理論化するなかで、私たちは(あなたが指摘しているように)あるコミュニティにおいてはるかに高い頻度で経験されている物質的な破壊とトラウマについて語っているのだ、という事実を見失うべきではないです。気候変動が海岸の水文-地形 hydro-geomorphologyを侵食、あるいは「風化 weather」させ続けている以上、私たちはこの「風化」をつねに気象的である以上のものとして理解する必要があるでしょう。ジェニファー・ハミルトンと私は短いエッセイである「風化=摩耗 Weathering」(Feminist Review, 2018)でこの点を説明しています。私たちが、植民地的、ヘテロ家父長制的、あるいは他なる社会的暴力を比喩的な意味においてのみ「風化」を理解しそうになったとしても、これらの政治的構造あるいは権力は「大気条件 atomospheric condition」を生み出しています。この「大気条件」とは、いかなる気象学的な風化の出来事がそうであるように、私たちが一日をうまく過ごせるかどうか、あるいは生き延びられるかどうかを左右しています。言い換えれば、「抑制されない気候変動」の用語のもとで湾岸部の洪水について語ることは、気候変動が権力の社会的、文化的、経済的構造から切り離せないものであると理解するときにのみ、意味をなします。私はときどき、気候変動を理解する(そして対処する)最も良い方法は、それを歪められた人間関係の症状のように捉えることだと話します。物事そのものではなく、症状なのです。私たちは、海岸における洪水、浸食、海面上昇を含めた気候変動に対処するためには、この場所にもたらされる暴力的な権力構造や悪しき関係に同時に対処することが必要です。エリートによる地球工学だけが私たちを救うのではありません!
もちろん、「私たちを救うこと」、この目的自体もまた問われる必要があります。気候変動への適応とその抑制において、私たちの最終的な目標はなんでしょうか? それはたんに生き延びることなのか、あるいは私たちはいかに生き延びるか、つまり誰として、何になり、そしてどのような異なる、あるいは変化した世界へと向かっていくのでしょうか? この点は、あなたが提起してくれた芸術的想像力に関わってきます。特に私たちがデ・カイレス・テイラーを水による人間の溶解として読むものであるとするならば、ドツェンコ、あるいはデ・カイレス・テイラーが私の追求したい想像力であるかどうかわかりません。ただ私はそれ〔デ・カイレス・テイラーの作品を人間の溶解として読むこと〕は、責任逃れだと思います。海は諦めていません。森林は諦めていません。動物は諦めていません。そして人間である私たちが諦めること、つまり私たち自身の溶解へと向かってよいのでしょうか? それは火星を植民地化することと変わりません。しかし、私は次の点に全面的に同意します。すなわち、種である人間として、また、非常に異なる状況に置かれた個人の人間として、この二つの側面を持つ人間として異なる責任や義務を持ち、私たちは誰であり、誰になる必要があるのか、再び想像するべきです。また疑いもなく、現在におけるアーティストの仕事は、重要なものでしょう。芸術家の仕事は、単に現在を診断するだけではなく、変化した状況のなかで、生、さらには繁栄の新たな仕方を想像することを助けることにもあるのです。この意味で私は、「持続可能性」という言葉に幾分疑念を抱いています。何を私たちは維持したいのでしょうか? 私たちは何を手放さないでいるのでしょうか? むしろ、もし私たちはより多くの私たちにとって全くより良く、より健やかで、より公正でより喜びのある何かを想像出来たらどうでしょうか? こそが、私が海洋生物学者であるアヤンナ・エリザベス・ジョンソンの刊行予定の書籍『もし私たちがうまくやれたら?』(Tippett and Johnson, 2021参照)というタイトルが大好きな理由です。私は、破局から単に生き延びることが最善のシナリオではない、ということを想像するための誘いとなる点で大好きです。私たちが夢見ることのできるような驚きよりもすごい何かがあると思います。そのため、ジョンソンが私たちに伝えてくれているように、私たちは最良の選択肢を増やしていくために必要なあらゆるものが、実際にすでにここにあるのだ、ということを、あたりを見渡し、見つけていくのです。そして、私たちはそれを生きるのです。
海岸線の現在と未来のために
SB:
あなたは、白人フェミニズムの「部分的な溶解 partial dissolution」(Neimanis 2019)を論じるために、クリスティーナ・シャープ(2016)やアレクシス・ポーリン・グンブス(2020)の文献を引用しながら、海中の気候における自然-文化的な現象について執筆していました。あなたは、シャープやグンブス、他の黒人フェミニズムの思想家が、海洋的な関係が「白人新世 White Anthropoceneの道具立ててでは推し量ることができない」(Neimanis 2019, 503)ということを明らかにしていると主張しています。あなたの論考では海岸というよりも、海中が主題となっていますが、私はこれらの知見は海岸的思考においても実りあるものになるだろうと思っています。例えば、この領域におけるあなたの仕事は、アイシャ・ゲリンの制作中の映画”Submerged”にも関わっているでしょう。この映画は、黒人と先住民の捕鯨者たち、そしてその人々が海岸や沿岸地域から追いやられてきた歴史を追うものです。ゲリンについての私のレビュー(この特集に寄稿されている’Coastal Methodologies’を参照)では、私は音響と視覚による記録が、反-静水的な映画 anti-hydrostatic cinemaを生み出していると論じています。つまり、音響的・視覚的語りが、捕鯨事業の人種化された種差別的な歴史を「落ち着かせること settling」あるいは静水的に均衡させることに対抗しているのです。アイシャ・ゲリンや他の研究者、アーティストの仕事は、海岸線という滑りやすい境界への関与において求められる革新的で応答的な理論的枠組み、そして創造-批判的な実践を提示しています。そこで、海岸線の議論においていまだに大きな影を落とす白人の人新世についてどのように考えていますか?
AN:
この点は、とても多くの繋がりや考えをもたらしてくれる素晴らしい質問です。まず第一に、これは先への問いを補ってくれるものでもあります。クリスティーナ・シャープによる仕事は、気候についての私自身の最近の思考に寄与してくれました(彼女の著書、『余波のなかで In the Wake』のある章は「気候」というタイトルであり、そこでは、上記の風化=摩耗についての私の議論を深く形成した「全体的な気候 total climate」として反黒人性が論じられています)。同様に、アレクシス・ポーリン・グンブスの仕事は、私たちが今すぐにでも必要なある種の想像力を示してくれています。それは、単なるサバイバルや黙示録という想像力を超え、未来の異なるあり方を代わりに想像するものです。あなたが書いていてくれるように重要なこととして、私はグンブスを、「白人フェミニズムの部分的な溶解」へと誘うものとして読んでいることです。つまり、私が先に批判した「人間たちが自らを諦めてしまうこと」ではなく、むしろ何かを放棄しなければならない、そうした考え方です。「世界の終りの後、あるいは世界の終わりとともにあること」において私がグンブスから学んだことは、私が手放さなければならない何かがあるということです。この何かとは、白人の特権の自然化や「人間」の基準としての白人性の自然化に関わっています。これは、人類全体ではありません。この放棄において、私は何か驚くべきもの、美しいもの、今まで決してその一部としては存在していなかったもの、そうしたものになりうるのです。これは人間の異なる概念を示しており、実際、シルヴィア・ウィンターのような人から学んでいます。ある世界は、異なる世界が繫栄するために終わる必要があります。グンブスは、これらの可能性を生み出してくれています。
アイシャ・ゲリンの仕事も取り上げてくれて感謝します。最近、ゲリンから学んだところです。この仕事を、「反-静水的なもの」として読むことは説得力があります。私にとって、ゲリンの議論は、グンブスの議論の見方と非常に沿うものです。つまり、時間の線型的な観念に対抗している点です。グンブスにとって、過去は未来を可能にするものです。すなわち、過去は現在であり、未来もまた現在なのです。海は、異なる時間とのあいだの親密性を感じさせてくれるようなタイムマシーンです。異なる時間は感情を動かし、互いに形作りあいます。異なる歴史、場所、身体、時間を親密性のかたちに落とし込むゲリンの視聴覚的な仕事は、過去についての私たちの理解を保ち続け、また未来への可能性を開くための別なる方法です。明確にしておきたいのは、これは植民地や他の暴力の歴史について修正主義に立とうという誘いではありません。むしろ、これから到来するものは、まだ決まっていない、ということです。他の時間、揺らぐ過去、こうしたなかでの他の人々との親密性は、これからも解き明かされていく物語を形作るのを助けてくれるでしょう。
私たちが水(あるいは湿地、特定の植物や動物種)について、生態系サービスという観点のみ話すとき、白人の人新世は依然として海岸線の現在と未来を支配しています。私たちが、喪失について財政的、経済的な意味においてのみ話すとき。私たちが関係性よりも財に価値を置くとき。私たちが人間といい、それによってただ唯一のことを意味しているとき。あなたは写真を撮ります。しかし、より陸と海、それもつねに変わりゆくようなより大きなエコトーンの一部として、移り行く海岸線を考えてみたらどうでしょうか?また、「静水的」に管理されていると考えるのではなく、推移について、変化について、時間について、均衡について、関係性について、いつも最も思慮あるとは限らないことについて、共に生きる異なる方法について、過去と未来の親密性について、支配する意志を捨て去る必要があることについて、互いに専心することについて、エコトーンが私たちに教えてくれる場だったとしたらどうでしょう? そして、私たちがそれを上手くやれていたならば?
訳注
(1) 「ずた袋 carrier bag」とは、ダナ・ハラウェイがアーシュラ・K・ル=グウィンを参照して用いている概念だと推測される。ハラウェイはずた袋について物語を語り伝える実践としている。ここで支持される物語とは、「光り輝く対象を追い求める英雄によって獲得される秘密を明るみに出す物語」ではなく、「予期せぬパートナーと還元不可能な詳細を、ほつれて穴のあいたずた袋にいれこむことによって進んでいく」物語だと論じられている(”Oterworldly Conversations; Terran Topics; Local Terms,” in Haraway Reader, London and New York: Routledge, 2004, pp.125-150, p.127)。
(2) 回折的 diffractiveとは、元をたどるとひとつはハラウェイに典拠を求めることができる。ハラウェイは、フェミニスト的概念・方法論的道具として回折を、二元論を超える差異を再考するために用いている(“The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others,” in Haraway Reader, 2004, pp.63-124)。だが、ここで直接的な典拠は、カレン・バラドの『宇宙の途上で出会う』にあるだろう。バラドは、量子力学の発展のなかで明らかになった光の回折に依拠し、これを自身の議論に持ち込んでいる。光の回折とは、光が波としての性質を持ち、光が障害物に到達したとき、波のようにその陰に回り込んだり、反射して広がったりする現象を示している。回折はバラドの議論においては、認識論と存在論の相互不可分性を示す概念となっている。これらの議論については、バラドの著作だけではなく、Birgit Mara Kaiser and Kathrine Thiele (eds.) Diffracted Worlds ― Diffractive Reading, London and New York: Routledge, 2018.を参照せよ。
(3) 「ウェルカム・トゥ・カントリー」は、行事の開催時に行われる歓迎の儀式であり、行事が開かれる土地の伝統的な所有者によって取り仕切られる。ここで「カントリー」とは、土地や水路、空などの自然環境を表すだけではなく、人生や家族といったものとの繋がりも含む概念である。
(4) ゴールデンスパイクとは、地質年代を区切る境界を示すものとして、国際地質化学連合の同意のもとに定められた層序断面、つまり国際標準模式断面に目印として打ち込まれる金色の杭やプレートである。
(5) 内的-行為は、バラドが提起した概念であり、「関係は関係項に先立つ」という枠組みに要約することができる。このとき、対置される概念は、相互-行為 inter-actionである。相互-行為は、諸個人が関係に先立って存在し、関係とはその諸個人が築き上げるものでしかない。これに対して内的-行為は、すべての存在や物事が関係というプロセスから生成すると想定する概念である。例えば、主体と客体を私たちは当然の概念だと思っているが、実際、何が主体/客体であるかは、特定の文脈、場所において築かれている関係において、一時的に定まるに過ぎないものである。それゆえ、物事は「あれか、これか」と排他的に考えるのではなく、それが位置付けられている関係や文脈、場所のうちで考える必要がある。
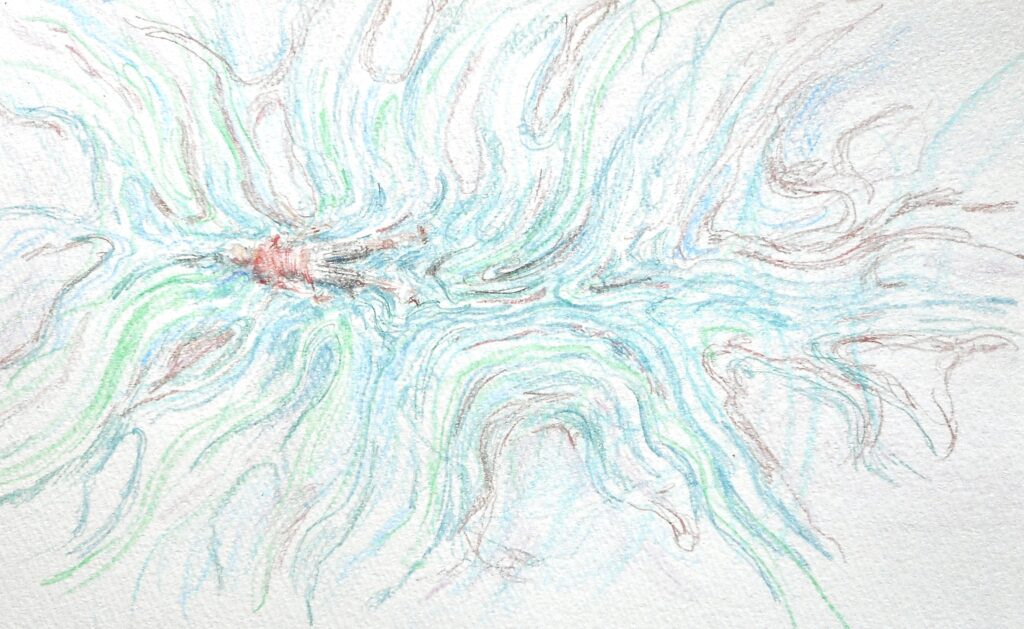
参考⽂献
1 Alaimo, S. (2010). Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self.
Bloomington: Indiana University Press.
2 Alaimo, S. (2017). Your Shell on Acid: Material Immersion, Anthropocene Dissolves. In
Anthropocene Feminism (Ed). (pp. 89‒120). Minneapolis: University of Minnesota Press.
3 Chakrabarty, D. (2009). “The Climate of History: Four Theses.” Critical Inquiry, 35(2), (pp.
197‒222).
4 Clark, T. (2012). “Scale: Derangements of Scale” in Telemorphosis: Theory in the Era of
Climate Change, Vol. 1, (ed.) Tom Cohen. Open Humanities Press.
5 Colebrook, C. (2014). “Archiviolithic: The Anthropocene and the Hetero-Archive.” Derrida
Today, 7(1), “Special Issue: Derrida Today Conference Edition I.” (pp. 21‒43).
6 Grusin, R. (2017). Introduction. Anthropocene Feminism: An Experiment in Collaborative
Theorizing. In Anthropocene Feminism (Ed). (pp. vii‒xix). Minneapolis: University of
Minnesota Press.
7 Gumbs, A. P. (2020). Undrowned: Black Feminist Lessons from Marine Animals. Chico;
AK Press.
8 Hamilton, J., Zettel, T., & Neimanis, A. (2021). “Feminist Infrastructure for Better
Weathering.” Australian Feminist Studies, 36(109), (pp. 237‒259).
9 Haraway, D. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham:
Duke University Press.
10 Neimanis, A. (2012). “Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water.” In Undutiful
Daughters: Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and
Practice. (pp. 85‒99). Ed. Henriette Gunkel, Chrysanthi Nigianni and Fanny Söderbäck. New
York: Palgrave Macmillan.
11 Neimanis, A. (2017). Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology. London:
Bloomsbury.
12 Neimanis, A. (2019). “The Weather Underwater: Blackness, White Feminism, and the
Breathless Sea.” Australian Feminist Studies, 34(102). (pp. 490‒508).
13 Neimanis, A., & Hamilton, J. M. (2018). “Weathering.” Feminist Review, 118(1), (pp. 80‒
84).
14 Sandilands, C. (2004). “The Marginal World.” In Every Grain of Sand: Canadian
Perspectives on Ecology and Environment. (pp. 45‒54). Ed. J. Andrew Wainwright. Waterloo:
Wilfred Laurier University Press.
15 Sharpe, C. (2016). In the Wake: On Blackness and Being. Durham: Duke University Press.
16 Thinking with Water. (2013). Ed. Ceclia Chen, Janine MacLeod, Astrida Neimanis.
Montréal: McGill-Queenʼs University Press.
17 Tippett, K., & Johnson, A. Y. ʻWhat if We Get This Right?ʼ On Being [Podcast], June 9,
https://podcasts.pple.com/us/podcast/ayana-elizabeth-johnson-what-if-we-get-thisright/
id150892556?i=1000565830760
18 Yusoff, K. (2018). A Billion Black Anthropocenes or None. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
Bezan, Sarah and Astrida Neimanis (2022) “Hydorofeminism on the Coastline: An Interview
with Astrida Neimanis,” Anthropocenes- Human, Inhuman, Posthuman, 3(1).
https://www.anthropocenes.net/article/id/1363/
ⓒ2022 Authors, reprinted under Creative Commons Attribution 4.0
翻訳:佐藤⻯⼈(東京⼤学⼤学院総合⽂化研究科・助教)
カバー写真:訳者撮影
挿絵:ミヤサカ リサ
公開日:2025年7月28日