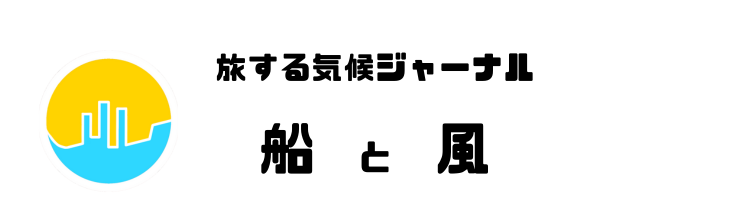ラフィア・ザカリア「帝国と高架道路」

カラーチー[1] では、海が動くようになって久しい。何十年にもわたって、この都市は縫い目を破って広がっていき、それにつれて海はますます遠くへと離れていった。朝、それもとても早い時間に都市部から一番近い海岸へ向かって、道路が終わる地点まで車を走らせたなら、こうした海の追放がどのように行われてきたか見て取ることもできるかもしれない。砂利や土砂を積んで重く沈んだトラックばかりが何列にも並び、積み荷を空けては湿地を土で埋めていく。そうして作られた土地は高い値段で売却され、富裕な人々ばかりが住む地域がそのうえに出来る。高い塀で囲まれた気取った高層家屋が、自分たちがはるか遠くへと追いやった海を高圧的に見下ろしている。彼らには恐れというものがない。
恐れがないのは貧しい人々も同じだ。あるいは、恐怖心は貧しい人々には手が出ない贅沢品だと言ったほうがいいかもしれない。カラーチーは人口数百万人の都市から一千万都市、そして今や二千万都市へと拡大してきたが、それにつれて毎週末になると、住民たちはぞろぞろ群れをなして都市海岸へ下りてくるようになった。イードの祭日や独立記念日には、その人数はさらに増える。モーターバイクの擦れてぼろぼろになった座席から二人、三人、四人と飛び降りるかと思えば、小さなスズキのトラックから十人、十一人とあふれ出てくる。誰もが一番のおしゃれをしており、明るい花柄の服や黒いブルカをまとった女性たちが、言うことを聞かない子どもたちにむかって叫ぶ。夫や父親たち、あるいは一家の後見人である伯父たちに見守られて、母と子らは渚へと向かっていく。男ばかりの一団がやってくることもある。なかには手をつないでいる同士もいて、あご髭や裾の長いズボンが撥ねかかった塩水で濡れる。誰もが水に飛込んでは波の飛沫を足や顔に浴びる。自分たちは都市をあとにしてきたのであり、都市から生まれる汚物ともいっとき別れを告げてきたはずだ、と水浴者たちは思っている。
しかしそれは間違っている。海のもっとも近くに位置する邸宅や高層マンションは、都市の下水システムとはつながっていないからだ。そうした地域から発生するごみは、処理もされず規制もされないまま、海へと流れてくる。オーシャンサイドに住まう富裕層への仕出しを目的に開店した高級レストランも、あらゆるごみを海に投棄する。結婚披露宴で提供された何千食分もの油脂のすべて、カラーチーの砂漠に作られた何エーカーもの芝地の水撒きに使われて殺虫剤まみれになった地下水のすべてが、海に流される。
どちらも同じ海に流れ込むリヤーリー川(Lyari)とマリール川(Malir)も、それぞれの贈物を運んでくる。街なかへとずっと遡っていった二つの川の川岸には、多くの工場が立ち並んでいるのだ。皮なめし工場、製紙工場、そしてあらゆる種類の医薬品や化学製品の製造過程がそこにはある。合法のものも、非合法のものも。そうした工場で余分になったもの、製品を作る過程で発生したものは、すべて海へと押し付けられる。カラーチーの貧しい水浴者たちが海に身を浸すということは、この有毒物質で発酵する液体に直接さらされるということだ。ちいさな子供たち、妊娠した母親たち、歳を取った女性たち、しかめ面の厳格な父親たちが、みな。そして彼らもまた、自分たちの贈物を残していく。毎週末には、彼らが捨てていった発泡スチロールのカップ、ソーダのボトル、スナックのプラスチック袋、失くした靴、そしてあらゆる種類の生ごみが海岸中を埋め尽くし、都市の周縁部に押し寄せた何トンもの有毒物質の一部となる。
***
都市から出る廃棄物や排泄物で悪臭を放っている海にこれほど熱烈に飛込みたがっているカラーチーの貧しい住民たちのことを、ナオミ・クラインならば私たちの惑星の「犠牲区域の人々」と呼ぶだろう。[2] 彼らのなかには、国じゅうに点々と散らばる小さな村から仕事を求めて大都市へとやってきた経済移民たちがいる。その多くは独身男性で、これまで海を見たこともなく、毎日を閉じ切った工場のなかで過ごしては、稼ぎがほとんど無きに等しい労働で骨身を削っている。その無に等しいなかからなにがしかがあとに残ると、彼らは海にやってくる。
そしてまた、パキスタン北部での紛争から逃れてこの都市にやってきた人々もいる。彼らが住んでいた村々は、まずはじめにターリバーンによって、それからアメリカの無人機によって、そして最後にはパキスタン軍が実施した「清掃」作戦によって蹂躙されつくした。そこから逃れてきた人々も、カラーチーへとやってくる。都市の周縁部で、そうした多くの家族が、親戚の家に身を寄せ合って暮らしている。他の何百万人と同じく彼らもまた職を探し、職が見つかると(あるいは見つからなくても)彼らは海にやってくる。
こうした二つのグループのうちでもっとも幸運な人々は、もっと別の海へと出ていくことを望む。経済的な理由から、あるいは戦争で疲弊してカラーチーへとやってきた移民たちの多くは、ふたたびどこかへ移住することを望む。願いが叶った幸運な人々は、化石燃料の採掘という経済領域に足を踏み入れ、ペルシャ湾の荒涼とした油田掘削装置のもとに向かう。彼らは、その身体を犠牲にして必死に働かされる。世界中の紛争の中心に位置している石油を、地球の内部から取り出すために。家を建て、息子たちに教育を与えたいという彼らのささやかな夢の実現が、石油の採取に懸かっているのだ。こうした男たちの物語はどれも生き残りについての物語であり、そうした差し迫った要求のただなかから見れば、(エドワード・サイードがそうしたように)環境主義の懸念を「ブルジョワの気まぐれ」として切り捨てるのは容易なことだ。だが、容易なことがつねに真実であるわけではない。
***
マーイ・コラーチー(Mai Kolachi)は、かつてインダス・デルタに暮らしていた女性の漁師である。今日では、彼女の名前を冠した高架道路が、にぎわうカラーチーの港をいくつかの高速道路とつないでおり、その道路はパキスタンの残りの地域へと蛇行して伸びている。眠りをさそうような漁村であったカラーチーの起源を呼び起こさせる女性の名前が、きわめて重要な生態系の一部を破壊する開発プロジェクトにつけられているのは、物事というのは往々にしてそういうものだが、とりわけ奇妙な皮肉だ。高架道路の建設には、スラム居住者の立ち退きやマングローブ林の開拓が必要だったが、そうした建設を緊急に行わなければならないと考えられた理由が戦争であったということも、驚くには当たらない。2001年にNATO軍がアフガニスタンでの戦闘に参加するためその近隣地域に動員された際、カラーチーの港は、軍が必要とするあらゆる物品を船で輸送するための結節点となった。国境を越えて戦争に必要な資材——何千人もの人々を殺害するものだ——を輸送するためには、NATOの輸送タンカーが市内の交通を迂回してすばやく高速道路にアクセスできるような高架道路が、どうしても必要だったのだ。こうして、数百万ドル規模のマーイ・コラーチー高架道路プロジェクトが誕生した。
つまり、アフガニスタンで殺戮を行うためにまず必要になった要素が、パキスタンでの生態系に対する環境破壊だったのである。高架道路のルート上には、チナー湾(Chinna Creek)ぞいに青々と茂ったマングローブ林も存在していたが、その天然の排水溝も建設によって破壊された。雨水がはけていた場所に高架道路を通した結果として、直接海へ流れていく雨水の容量が減少した。それによって何が起きたのかと言えば、この都市のなかでもっとも歴史が古く、今やもっとも貧しい地域にも数えられるいくつかの区域が、モンスーンが来るたびに洪水で水没するようになってしまったのだ。どこにも行き場所がない悪臭のする水が何日ものあいだ通りや家々にとどまり続け、蚊や蠅がはびこるようになる。そして今度はこうした蚊や蠅が病気を生みだし、何百人もの人々がコレラやマラリアやデング熱で苦しむことになる。
かつて存在していたマングローブ林が消えてしまったという点では、高架道路につながる数多くの高速道路ぞいでも事情は同じだ。保水効果がなくなったのと同時に、近づいてくるハリケーンやサイクロンに対する防護林としての機能も失われてしまった。鶴やペリカンといった渡り鳥たちは、中央アジアから南下する際に毎年その林に立ち寄っていたが、いまでは羽を休める場所がなくなってしまった。かつて生きた美しい自然があった場所には、今や戦争の部品を運ぶことを第一の目的とする道路があるだけだ。
マーイ・コラーチー高架道路の建設が行われていた時期の古い新聞に一通り目を通していると、ある人物の言葉が引用されているのを発見した。その人物は計画に対するもっとも声の大きい反対者の一人であったペルウィーン・ラフマーン(Perween Rahman)という女性で、彼女は都市プランナーであり、オランギー・パイロット・プロジェクト(Orangi Pilot Projekt)[3]を率いる環境活動家でもあった(このプロジェクトはカラーチーのもっとも大きなスラムに拠点を置いている)。「あらゆる土地の改造は、ただちに停止する必要がある」。ラフマーンの意見にはくもりがない。「大雨で水位が上がって逆流する川も、時間が経てば自然な状態に戻る。それと同じように、建設された高架横断道路も水に流されるべきだ。なにしろ、マーイ・コラーチー高架道路は天然の排水管のうえを通っているのだから。それに、すくなくとも魚やマングローブのためにも高架横断道路を作ってやらなければならない。どうして自動車のことしか考えないのだろう? だって、魚たちも別の側に渡る必要があるし、私たちはこれまでかれらを殺し、殲滅してきたのだから」。
当然のことながら、彼女が言ったことは何ひとつ実現せず、その代わりに起こったのはさらなる悲劇だった。7億ドルをかけたマーイ・コラーチー高架道路建設の犠牲となってきた魚や樹木と同じように、ペルウィーン・ラフマーンもまた、殺害されたのだ。それは彼女が新聞のインタビューに答えてから10年あまり経ってからのことで、その間も彼女は、生態系の環境を破壊し、カラーチー市民の抗議の声をスケープゴート化し、市内の権力者に土地の強奪を許すさまざまなプロジェクトに反対し続けていた。ペルウィーン・ラフマーンは、2013年3月13日、何人もの襲撃者たちによって銃殺された。三年後の今になっても事件は未解決であり、これまで殺害の罪に問われた者はひとりもいない。
マーイ・コラーチー高架道路は、NATOのアフガニスタン侵攻以後の15年間で、何十万トンもの軍需品を輸送してきたはずだ。いまでは、この高架道路はカラーチーの都市輸送システムの欠かせない要素となっており、それがなかった時代を知らずに育ったという世代も存在する。2011年には、高架道路から直角に突き出すように、新しい鋭角のビルが出現した。新聞が吹聴するところでは、アメリカの新しいカラーチー領事館が「最新のテクノロジー」を用いて建てられた、とのことだった。その落成式で当時のアメリカ総領事であったウィリアム・マーティンが述べたのは、新しい建物は「アメリカとパキスタンのあいだの持続的な関係を明確に反映するものであり、アメリカ国民と政府が今後も長らくパキスタンの味方であるという約束でもある」ということだ。マーティン領事は、とくに新しい建物の位置に言及しながら、こう続ける。「これは歴史的で重要な快挙だ。シンド州やバロチスタン州の人々にも我々の新しい領事施設をお目にかけるのを楽しみにしている。領事館の移設は、引き続きアメリカ国民とパキスタン人のあいだで強力かつ相互に利益をもたらす関係が築かれることを可能にするだろう」。
***
テロとの戦争について、そしてそのなかでパキスタンが果たす役割について、これまで多くのことが書かれ、語られてきた。しかしながら、テロの物語が生態系やスラム居住者への暴力、貧しく絶望した人々やその支援者達への暴力と結びつけられることは、めったにない。ナオミ・クラインの次の言葉はまさにこの事情に触れている。「専門技術者によって解決されるべき単体の問題として気候変動に立ち向かうことは不可能だ。気候変動は、緊縮政策や民営化[私有化]、植民地主義や軍国主義といった文脈において捉えられなければならない」。マーイ・コラーチー高架道路の物語が明らかにしているのは、カラーチーにおけるあくなき土地改造への衝動、破壊的なショートカットを要求するさまざまな外的な力、そしてその航路のあとに残された荒廃した生態系という三者のあいだの結びつきである。
マーイ・コラーチー高架道路のような物語は、温暖化しつつある私たちの世界のなかの、あらゆる傷ついた領域に散らばっている。パキスタンの南部で、港や海岸が輸送供給ラインのために明け渡されなければならなかったとするなら、パキスタンの北部では、上空を無人機が飛び交った。こうした遠隔操作の爆撃機が巡回した多くの地域においてもまた、資源採掘のために生活の基盤が劇的に変容させられてきた。「部族の土地」としてフェティッシュ化され徹底的な爆撃を受けてきた土地である北ワジリスタンの多くのコミュニティは、かつては持続的な農業によって暮らしを立てていた。しかし鉱山会社がやってきて石膏鉱山ができ、男たちがそこで働きはじめると、人々は農業を捨て、自分たちを産んだ土地とのあいだに新しい搾取的な関係を築いていった。鉱山の操業が閉鎖され必要な労働力が減少すると、そこでは仕事が見つからなくなってしまった。男たちはカラーチーへ、あるいは湾岸諸国へと去っていった。父親がいない息子たちを待ち受けていたのは、パキスタン・ターリバーン運動(Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP)の陰謀だけだった。その運動は、巨大な力によって自分たちの土地がレイプされ蹂躙されてきたことに対して、荒々しく容赦のない復讐を行うチャンスを約束していたのだ。
これからの気候活動家の仕事は、こうした物語、つまりナオミ・クラインが言う「切断を乗り越え、共通する糸をより強く撚りあわせ、私たちが抱えるさまざまな問題や運動を互いにつなぎあわせる」ような物語を伝えていくことだ。そうした物語はカラーチーの高架道路に体現されている喪失の悲劇に満ちているが、それを伝えることによってこそ、気候変動に対する真に包括的でラディカルな運動への希望が生まれうるのだ。こうした批判が真剣に受け取られるときにこそ、より思いやりのある未来という希望が生まれうる。すなわち、いにしえの女性にちなんで名づけられてはいるものの、昔からある多くのもの、大切にされてきたもの、そして多くの生き物たちを殺害した道路の物語をとおして、私たちの相互の結びつきや緊急の行動のための根拠が形作られるようなときにこそ。
(翻訳:中村峻太郎)
出典:Rafia Zakaria: Empire and the Overpass. In: Vijay Prashad (ed.): Will the Flower Slip through the Asphalt. Writers Respond to Capitalist Climate Change, New Delhi: LeftWord Books 2017, pp. 66-74.
©Rafia Zakaria 2017, used by permission of the author.
URL: https://mayday.leftword.com/blog/post/empire-and-the-overpass
使用画像:Hira Farooq, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons
[1] [訳注]アラビア海沿岸に位置し、2000万人以上の人口を抱えるパキスタン最大の都市。シンド州の州都。
[2] [訳注]このエッセイは、ナオミ・クラインが2016年に行ったサイード記念講演「奴らは溺れさせておけ:温暖化する世界における他者化の暴力」(邦訳は中野真紀子、関房江訳『地球が燃えている』大月書店に収録)への応答として書かれており、引用もすべて同講演からである。そこでクラインは、気候危機の原因をつくっている化石燃料の燃焼は必然的に「犠牲区域」を生み出すものであり、そこにはエドワード・サイードの言う「他者化」の暴力が深く関わっていると論じた。
[3] [訳注]カラーチーのオランギー地区に拠点をおくNGO。1980年の発足以来、衛生や住宅、教育、水不足といった問題に取り組んだり、地域でのマイクロクレジット(小口融資)を行ったりしている。ペルウィーン・ラフマーンは、発起人のアフタル・ハミード・ハーン(Akhter Hameed Khan, 1914-1999)とともにそこで中心的な役割を果たした。http://www.opp.org.pk/