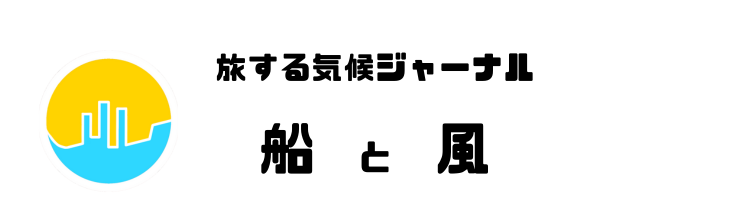アラブ文学における気候をめぐる思弁的未来
Speculative Climate Futures in Arab Literature
マルシア・リンクス・クエイリー
Marcia Lynx Qualey
『MERIP』311号(2024年夏)
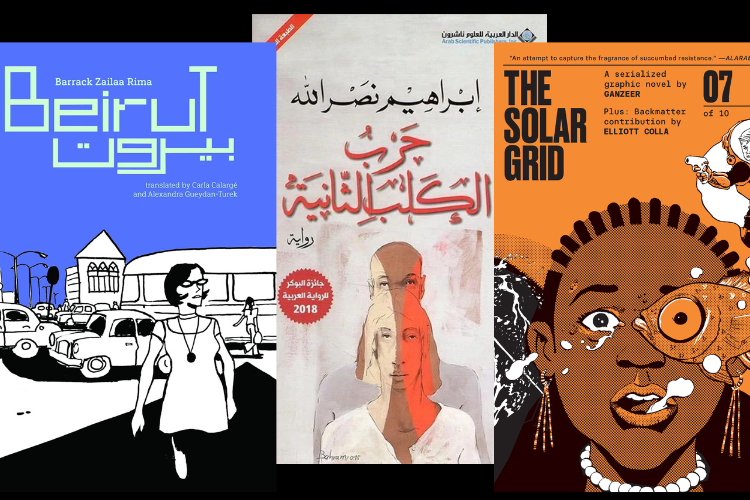
原文リンク:https://merip.org/2024/07/speculative-climate-futures-in-arab-literature-2/
訳者前書き:本記事はアラブ文学の翻訳に焦点を当てたウェブサイト、雑誌、書籍を制作する『Arablit』の創設者であるマルシア・リンクス・クエイリーによって2024年に発表されたエッセイ「Speculative Climate Futures in Arab Literature」の日本語訳です。クエイリーは、「気候変動」や「環境破壊」を取り扱うアラブ文学作品が、英語圏でいう「クライメート・フィクション」のように固定的な枠にとらわれずに、現実に起きている政治的・経済的問題と深く絡められながら、多様なかたちで展開されてきた様子を概観しています。
はじめに
英語の大衆小説には、出版界および学術界のなかで厳格に定められている境界の固定性がある。それはアラビア語の大衆小説においてはほとんど存在しない。
英語圏の出版界は、比較対象となる作品や、小説が文芸界のどこに位置付けられるのかに非常に関心を持つのに対し、現代アラビア語の出版界ではそうした関心はあまり見られない。そのため、アラビア語には「クライファイ」(クライメート・フィクション)として括る固定的な用語が存在しない。ただし、英語のクライファイとよく似た作品——人為的な気候変動の影響、特に温室効果ガスの排出によって引き起こされた長期的な気候パターンの変容を扱う作品——は存在する。こうした作品は「気候変動の文学」(adab taghayyur al-munakh)や「環境文学」(al-adab al-biʾi)と呼ばれるほか、「クライメート・フィクション」(klaymat fikshun)とそのまま音訳されることもある〔アラビア語の転写表記は原文ママ〕[1]。
このジャンルはアラビア語圏ではそれほど人気がない。エジプト人ジャーナリストで短編作家のアフマド・アル=ハミースィーのように、そのことを嘆く批評家もいる。しかし、SF作家のイマード・エッディーン・アイシャは、西洋のディストピアへの愛着は一種の贅沢ともみなせるのではないかと示唆する。彼は、「日常のあらゆる場面における現実の不安」に直面している人々は、わざわざそれを想像で作り出す必要があまりないと言う[2]。一般に、アラビア語圏では、気候変動を扱った作品は、グラフィックノベルや短編アニメーションの形でより多く見られるようだ。これは部分的には、こうしたプロジェクトが国際的な資金を得やすいという事情もあるが、それ以上に、実験的な表現を可能にする形式だからでもある。
近未来をめぐる思索から少し視野を広げると、人間の行為が自然界にもたらす影響を主題とするアラビア語小説は数多く存在する——例えば、アブドゥルラフマーン・ムニーフの『塩の都市』(Cities of Salt、1984年)は石油の影響を、イブラーヒーム・アル=クーニーの『石の出血』(The Bleeding of the Stone、2013年)など多くの作品は人間による砂漠環境への影響を扱い、イスマーイール・ファハド・イスマーイールの『老女と川』(The Old Woman and the River 、2017年)は戦争が自然環境をどう変えるのかを年代記的に描いている。
2023年にオマーン人作家ザフラーン・アル=カースィミーが現代を舞台とした小説『水脈を聴く男』(The Water Diviner)〔訳注1〕で「アラブ小説国際賞」を受賞した際、審査員数名が気候変動の問題に言及した。この小説自体は気候災害を前面に押し出しているわけではない。しかし、多くの読者は、村の灌漑システムが社会的な関係や制度の基盤になっているこの物語に、気候変動の要素を読み取っているようだ。同様に、クリスティーン・アンナ・ギルモアが論じるように、アスワンダムの影響を年代記的に描いたヌビア人作家たちによる小説や短編作品も、気候変動を扱った作品として読むことができる[3]。
醜くも美しいディストピア
環境の破局は、多くのディストピア的作品にとって欠かせない起源の物語をもたらす。2018年にアラブ小説国際賞を受賞したイブラーヒーム・ナスルッラーの『犬の第二の戦争』もその一例である。歴史小説で知られる同作家によるこの近未来ディストピア作品は、テクノロジーの発展と権力の腐敗との交差に焦点を当てている。作中で最も顕著なのが、人間の「偽造された」コピーである——機械がある人間を別の人間のドッペルゲンガーに変換するなかで、人々が互いを操作し、搾取する能力を加速させながら、個人のアイデンティティを保つ余地を縮小させていく。この小説の背景には人間を困難に陥れる気候の破局があり、大気や農業の変化、空から落ちてくる死んだ鳥が描写される。ここでは、気候災害は社会的・政治的恐怖を加速させる増強装置として機能し、人間の進歩という物語への批判にもなっている。
ムハンマド・ラビーウの『ウターリド』(Otared、2016年〔アラビア語で水星を意味する〕)やアフマド・ハーリド・タウフィークの『ユートピア』(Utopia、英訳:チップ・ロセッティ、2012年)など、他の近未来ディストピア作品でも政治制度に主眼を置きつつ、環境〔問題〕がすぐそばに存在している。テリーザ・ペペが指摘するように、特に『ユートピア』では、経済学的・生態学的災害が小説のディストピア的世界観の根幹にある[4]。これらの破局は、化石燃料生産の崩壊によって引き起こされ、富裕層と貧困層との間に暴力的な断絶が生まれている。物語の舞台は、国家の国境のように軍事化された未来の郊外住宅街の内部と周辺である。その壁に囲われた住宅街の内側では、米軍に守られながら、富裕層がエジプトのほぼ全ての資源を独占しており、旧市街にいまも住むエジプト市民にはほとんど何も残されていない。
アフマド・ナージーの小説『そして虎たちが私の部屋へ』(And Tigers to my Room, 2020年)は、現在ブルックリンのハムサ・プロダクションによって映画化が進められており、物語は遠い過去から近未来に至る数千年の歴史をまたいで展開される。この小説は、いかに現在計画されている壮大でユートピア的なプロジェクト——サウディアラビアの水上産業複合体や線状都市からなる「NEOM」のような——が、『ユートピア』に登場するような採取主義的で権威主義的な飛び地と本質的に同じであるかを突きつける。人々は、カイロのような何千年もかけて築かれた都市ではなく、資源を吸い上げて見せかけの壮麗さを生み出す、人工的につくられた新都市に住んでいる。中心人物の一人がNEOMに到着すると、彼女の目に映るのは「ラクダのための緑の巨大牧草地、さらに巨大なゴルフ場、背の順に並ぶ牧畜民たち、三つのマギの星、文明化を示すが如く幾何学的に整備された道路、ガラスドームの下に広がる南国庭園、巨大なレーザー光に照らされた広場に並ぶ芸術作品や彫刻作品」であった。そこにあるのは、約束された、輝かしくも実現不可能な環境的・社会的理想郷である[5]。
注目すべきクライメート・フィクションは、コンマ・プレス社が刊行する「フューチャー・パスト」シリーズに見られ、その作家たちはある決定的な歴史的事件から100年後の世界を舞台にした物語を任じられている。『パレスチナ+100』(Palestine + 100、2019年)〔訳註2〕では1948年のナクバが、『イラク+100』(Iraq + 100、2016年)では2003年の米国主導のイラク侵攻が〔100年の〕起点となっている。『パレスチナ+100』(バスマ・ガラーイーニー編)所収のサリーム・ハッダードによる『鳥たちの歌』では、住民を従順にしておくため、気候ディストピアのうえに偽りのユートピアが塗り重ねられている。また、『イラク+100』所収のハサン・ブラースィムによる『バビロンの庭園』(英訳:ジョナサン・ライト)では、バビロンの街に水を供給するため、中央及び北ヨーロッパから「水の列車」が運行されている。物語のなかで「水の反乱者」たちは、この資源の分配方法に反発している。なぜなら、「割り当て分を支払うeクレジットすら十分に持てない人がいるなか、裕福な地域では特別車両がプールや噴水を満たしているのを目にするから」である[6]。
最新の作品集『クルディスタン+100』(Kurdistan + 100、2023年、オルソラ・カサグランデとムスタファー・ギュンドウドゥ編)にも、生物多様性が崩壊する未来を記した注目すべき小説がいくつか収録されている——それはまた、クルド人がさらに周縁化され、自らの過去から切り離されていく物語でもある。
めでたし、めでたし——気候を修復する物語
アラビア語のクライファイ全てが陰鬱でディストピア的というわけではない。破滅的な制度に対して登場人物たちが打ち勝つ道を見出す、希望成就型の物語も存在する。レバノン人小説家ガッサーン・シバールーの『2022』(2009年)における物語の中核は、気候活動家ディヤーナ・ファーリスと気候破壊者マンスール・カーシューシュとの闘いである。最終的に、ディヤーナはレバノン国会の議席を獲得し、環境目標の達成を目指すことになる。
この物語の結末は、レバノンの気候〔問題〕を扱うほかの多くの作品——例えば、作品集『二つの惑星の物語』に収録されたリーナー・ムンズィルのダークな喜劇『ウェイスト・アウェイ』(Wasting Away、2020年)——に比べてはるかに明るい光景を描いている。バッラーク・ザイラア・リーマーによるタイムトラベルを扱ったグラフィックノベル『ベイルート三部作』(Beirut trilogy、2017年、英訳:カーラ・カラージェとアレクサンドラ・グウェイダン=トゥレク)でも、ごみに溢れるレバノンが描かれている。かたや、レバノンの廃棄物危機を不幸な結末として捉えたのがムーニヤー・アクルの映画『潜水艦』(Submarine、2016年)である。この映画では、若い女性が自宅で美を生み出し、環境崩壊からの逃走を拒むことで、大惨事を食い止めようとする。この映画は思索上のフィクションであるが、制作チームはディストピアと今の現実との薄い狭間を演出するため、〔実際のごみ山である〕舞台設計の場と〔ごみ山として〕再現された場を繋ぎ合わせた、とジョーイ・アイユーブとのインタビューのなかでアクルは語る。例として、アクルはベイルート川に実在するごみ投棄地を取り上げる[7]。
しかし、より良い架空の未来を作ろうとするのはシバールーだけではない。2022年にはヨルダンの小説家スブヒー・ファフマーウィーによる『アレキサンドリア 2050』(Alexandria 2050、2009年)もまた『2022』と同様に、修復された気候を提示している。海面上昇によって消滅しなかった未来のアレキサンドリア〔訳注3〕を舞台にしたこの小説では、テクノロジーが本当の喜びをもたらす明るい未来が描かれる。物語では、パレスチナ人老技師が2050年、ドバイからアレキサンドリアに戻り、遺伝子工学を専門とする息子のブルハーン、(遺伝子操作の施された)「グリーンな」孫のカナーンに出会う。そこでは、遺伝子工学によって善良で「グリーンな」人間が創り出され、そこには大量虐殺や植民地主義的搾取のないより優しく、穏やかな未来が予感されている。
マーリヤ・ダアドゥーシュの『黄金の目が欲しい』(I Want Golden Eyes、2019年)では、テクノロジーが持てる者と持たざる者の隔たりをさらに広げる。しかし若年層向けに発表された『ガラス玉の謎』(The Mystery of the Glass Ball、2021年)では、物語の舞台は、優れた管理とテクノロジーの活用によって人々がアラビア半島の砂漠を保全する未来となっている。この小説では、ある少年が、オアシスに毒を撒き、砂漠の保護区で動物を全滅させようとする二人の犯罪者に出くわす。もちろん、少年は彼らの企みを見逃さない。
グラフィックノベル、フォトグラフィー、アニメーション映画における実験
アラビア語文学における気候変動への最も興味深いアプローチのいくつかは、グラフィックノベルやその他のハイブリッドな手法で展開されている。ラワーンド・イーサーの『巨大な魚のなかで』(Inside the Giant Fish、英訳:エイミー・チニアラ、2023年 [アラビア語版は2019年])は、リーマーの『ベイルート三部作』と同様に、現代のドキュメンタリー手法と魔法のような表現とを融合させている。
気候変動は、アフマド・ナージーの実験的なハイブリッド・グラフィックノベル『人生を使いながら』(Using Life、2017年)においても、物語を動かす背景の一部となっている。本作はアイマン・ズルカーニーのイラストで彩られ、英訳はベン・クーバーによってなされた。作中では、津波のような砂嵐がカイロを覆い、その後に地震が起きる。そして、歴史的カイロがほぼ壊滅し、「ニューカイロ」が郊外に出現するなか、ナージーはディストピアの陰にある親密な関係性とともに、グローバルな権力への風刺を織り交ぜている。
エジプト人アーティストのガンズィールが執筆・作画を手がけた連載型グラフィックノベル『ソーラーグリッド』(The Solar Grid)もまた、荒々しく広大な未来世界の冒険譚であり、企業に引き起こされた気候破局に一貫して焦点が当てられている。ここでは砂嵐の代わりに、大洪水がエジプトを含む世界の大部分を水没させる。そして、破滅に対抗するはずの技術的解決策として登場するのが、作品名にもなっている「ソーラーグリッド」である。そこから展開する複雑に絡み合った物語は、空間と時間を横断しながら、人間のレジリエンスと、より多くのテクノロジーとコーポレート・キャピタルが必ずや人類が直面する気候災害を解決するという果てしない執念の両面を描き出す。この絡み合った物語のシリーズは広範で国際的な視点を保ちつつ、社会の一側面を切り取るだけでなく、過酷なほど搾取的な関係性が富裕層と貧困層、グローバル・ノースとグローバル・サウスの未来に何をもたらすのかを問いかけている。
サイフ・クスマートによる写真と詩のプロジェクト『ワーハ』(Waha、アラビア語でオアシスを意味する)は、水という不可欠な資源が蒸発していく過程をリアルタイムで観察する、本質的な探究を提示している。彼は2022年、このプロジェクトを書籍化すると発表した。『ワーハ』の一環として、クスマートはモロッコのオアシスの変化を写真に収めるだけでなく、住民たちの詩や証言を収集している。この試みを、彼は「詩的ドキュメンタリー写真」と呼んでいる[8]。
ムハンマド・サラーの『8分間』(8 Minutes)は、アレキサンドリアにあるスウェーデン・インスティチュートとマズグ財団のコラボレーションによる気候変動展のために制作された漫画作品である。アレキサンドリアを舞台に海面上昇をテーマとして、スブヒー・ファフマーウィーの『アレキサンドリア 2050』よりもはるかに暗い未来像を描いている。サラーの描く世界では、海面上昇が暴力的で機会主義的な無法状態の到来を告げる。そうした背景のなか、サラーは描くべき美の一瞬を探し求め、ついに見つけたのは、その危険に満ちた世界へと8分間だけ身を投じ、夕日を見にいく男女の姿だった。
気候〔変動〕によって荒廃した未来のなかにもやさしさや驚きが宿ることは、ムハンマド・ウマルの短編アニメーション映画『ケノプシア』(Kenopsia)においても核心をなしている。物語では、もぬけの空となったカイロが舞台となっており、一人の老人男性が幼少期の自宅を探しにやってくる。本作品は暗い未来像を表現する。タハリール広場には、アレキサンドリアの水没後に避難してきた人々を保護するための多くの仮設キャンプが放棄されたまま残る。人々は呼吸するためにマスクを着用しなければならない。そうした静かな風景のなかで、観客は主人公とともに、かろうじて息ができる今日のカイロの混沌を懐かしむことになる。
マルシア・リンクス・クエイリーは『ArabLit』および『ArabLit Quarterly』の創設編集者である。
出典: Marcia Lynx Qualey “Speculative Climate Futures in Arab Literature,” Middle East Report 311 (Summer 2024). サムネイル画像は原文より引用(https://merip.org/2024/07/speculative-climate-futures-in-arab-literature-2/), translated and reprinted with permission of the author.
翻訳:中鉢夏輝
訳者後書き:訳者は最近、海面上昇や地球温暖化による被害やリスクが一層深刻化している地域で、人々と交流する機会を重ねるなかで、内発的かつ現実的に創作活動を行う人々に関心を持つようになりました。こうした地域が被害にさらされているのは、多くの場合単なる地理的要因ではなく、一部の人間による政治的思惑や政策の不備に起因しています。そこで交わされる語りは、そうした現実を踏まえたもので、かつきわめて生活に根ざしたものであり、彼らの創作もまたその延長線上に位置してます。それらに触れていると、温帯圏で表現される「危機」や「破滅」の物語にはどこか違和感を覚えることも少なくありません。そんな折、同じ感覚を示していた人がいたことを思い出し、紹介できればと思った次第です。紹介した記事には英語・日本語の作品もあるので、読まれた方がいたらぜひ感想をお聞かせください。
[1] Teresa Pepe, “Climate Change and the Future of the City: Arabic Science Fiction as Climate Fiction in Egypt and Iraq,” Middle Eastern Literatures 26/1 (2023), p. 100.
[2] Emad El-Din Aysha, “Double Trouble: Moataz Hassanien’s ‘2063’, charting a course for today, from the world of tomorrow!,” Liberum, January 15, 2019.
[3] Christine Anna Gilmore, “Dams, Displacement and Development in Narratives of the Nubian Awakening,” PhD Thesis, The University of Leeds, June 2016.
[4] Teresa Pepe, “Climate Change and the Future of the City: Arabic Science Fiction as Climate Fiction in Egypt and Iraq,” Middle Eastern Literatures 26/1 (2023), pp. 99–118.
[5] Ahmed Naji, “Excerpt from Naji’s Novel And Tigers to my room” (translated by Robin Moger), Pen/Opp, February 25, 2022.
[6] Iraq + 100: Stories from a Century after the Invasion, ed. Hassan Blasim (Comma Press, 2016), p. 13.
[7] Elia J. Ayoub, “In Conversation with Mounia Akl, Director of ‘Submarine,’” Hummus for Thought, July 17, 2018.
[8] “Degradation through Aesthetics and Poetry: An Encounter with Seif Kousmate on ‘Waha’,” AFAC Arab Fund for Arts and Culture, June 10, 2022.
訳注
訳注1 2025年には、山本薫、マイサラ・アフィーフィーによる日本語訳も刊行された。詳しくは書肆侃侃房による紹介ページを参照のこと(https://www.kankanbou.com/books/kaigai/0674)
訳注2 SFマガジン『Kaguya Planet』2024年第2号ではパレスチナ特集が組まれ、岸谷薄荷訳、佐藤まな監訳のもと、本アンソロジー所収のタスニーム・アブータビーフ『継承の息吹』が紹介されている。詳しくはKaguya Planetウェブサイトを参照のこと(https://kaguya-books.square.site/product/kaguya-planet-palestine/10)
訳注3 アレキサンドリアはエジプト北部にある地中海沿岸の都市。以前から建物の倒壊が問題となっていたが、近年の洪水や暴風雨の多発、そして海面上昇による土地の侵食がそれに拍車をかけている。