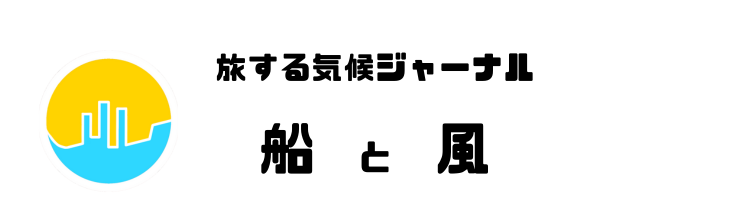ペトロフィクション、再訪
アミタヴ・ゴーシュ
まだ皇帝によって支配されていた時期のことだが、私が石油の持つ変容的な力を意識するようになったのは、イランにいるときのことだった。
私のイランへの訪問が生じたのは父親のおかげで、彼は当地でインド大使として働きながら数年を過ごしていた。それは1970年代前半のことだ――私は当時インドの学校に通っていたが、一年に二度、家族を訪ねてテヘランへ向かうことになっていた。
インドとイランの国境線は千マイル[約1600km]と離れておらず、二つの国々は古代にさかのぼる言語的・文化的なつながりによって結び合わされていた。[しかし]このことが、両国のあいだの差異を私の若い目にひときわ強く映し出させることになった。ニューデリーからテヘランへと移動することは、あたかも石油という地の裂け目を飛び越えるかのようだった――渡った先には、きらきらと光る高速道路が、スピードの出る自動車が、アメリカ式のピザ・レストランが、そして多局放送のテレビジョンがあった。これらすべてが私には新鮮だった。そして、石油による繁栄の不可視の対価であるかのような、つねに現前しいつでも触知することができる政治的抑圧の感覚もまた。
私は家族と一緒に、国の南部へと何度か小旅行をした。私たちはペルシャ湾北岸に位置するいくつかの町を訪ねた――ブーシェフル(Bushehr)や[バンダレ・]アッバース(Abbas)のような港町だ(そこからはホルムズ海峡が見晴らせた)。私がとりわけよく思い出すのはアーバーダーン(Abadan)の町への訪問で、それはイラン南部とイラクとを分けるシャットルアラブ川(Shatt al-Arab)の東岸にあった。その川はどちらの岸もさまざまな種類の石油施設で一杯になっていた――それらが夜空を照らし出すさまを驚嘆とともに眺めたことを、私はまだ憶えている。
私のなかのイランの記憶が、中東との持続的なつながりを生み出すことになった。それから何年かして、いくつもの運のよい偶然が積み重なってオクスフォード大学で人類学の博士課程を開始できることになったとき、中東地域に立ち返ろうと私に思わせたのはイランでの昔の経験だった。しかしイランはイスラーム革命による激震のあとで混迷の時期を経験している最中だったから、私はそのかわりにアラビア語を話す世界を専攻することに決めた。
1979年夏、チュニジアでのアラビア語のコースを履修し終えると、私はヒッチハイクで西に向かい、アルジェリアとモロッコを横断した。アルジェリアで私は何度か、石油世界とのなかば超現実的な出会いを果たした。なかでももっとも記憶に残っているのは、グラン・エルグ・オリエンタル(Grand Erg Oriental)(東方大砂丘群)の月面的な風景の端に位置する、アル=ワーディー(El-Oued)というごく小さな町への乗車の終わりに起こった出会いだ。私がリュックサックの上に座って今夜をどこで過ごそうかと思案していると、一人のサリーをまとった女性が砂塵の雲のなかから現れた。現地の病院が(サハラの多くの場所でそうであるように)大勢のインド人の医師や看護師を雇っているのだ、ということが後で判った。かれらは私に泊まる場所を与え、すばらしい家庭料理の御馳走でもてなしてくれた。
私のオクスフォードでの博士課程の指導教員は、ピーター・リーンハート(Peter Lienhardt)という名前のアラビストだった。彼は1950年代に、ラアス・アル=ハイマ首長国の風変わりなシャイフのアドバイザーとして仕えていたことがあり、そうした立場から、ブライミー・オアシス(Buraimi Oasis)をめぐる係争[1] においてちょっとした役割を果たしていた。ピーターは偉大な話し上手で、彼の物語によって、のちに私が「石油をめぐる出会い」と表現することになる現象とのあいだに個人的なつながりを持っているという感覚が与えられた。
私が最終的にフィールドワークの調査地として向かったエジプトの村では、湾岸で働いていた何人かの男たちと出会ったが、彼らは[そこで]インド人たちと出会った話をしてくれた。かれらの多くは、インド南部のケーララ州の出身だった。
そしてたまたま、私の最初の就職先はケーララ州の研究所だった。湾岸とのつながりを持っていないケーララ人は稀であり、私はほどなくして、湾岸のさまざまな石油国家におけるインド人とエジプト人ないしその他のアラブ人との出会いの物語を、数えきれないほど打ち明けられることになった。
私が最初の小説『理性の円環(The Circle of Reason)』を書き始めたのはケーララ州でのことであり、この小説がそうした出会いを題材として用いることは(おそらく)避けがたいことだった。小説の舞台はペルシャ湾岸に位置する架空の産油首長国であり、書き進めるプロセスのなかで私は、石油の景観が、慣れ親しんだフィクションの技法にいかに抵抗してくるのかを意識するようになった。こうしたこと全てが私の心に重くのしかかっていたときに、私は腰を据えて『ペトロフィクション(Petrofiction)』として結実する書評を書き始めた。[2]
そのエッセイにおける私の狙いは、石油をめぐる出会いを文学が無視してきた理由を特定する、というものだった。その当時、この主題を扱ったフィクションは本当に希少だった。しかし二十五年の歳月を経た現在、私たちはまったくもって別の時代に生きており、その始まりは(きわめて正確に)2001年9月11日にさかのぼることができる。攻撃につづく日々、元に戻るものは何もないだろうとしばしば語られた。このことは文学の景観にも当てはまるということが、確実に証明されてきた。過去十五年にわたって、さまざまな仕方で石油をめぐる出会いに関係する主題のフィクションやノンフィクションが、膨大に溢れ出てきた――イラクでの戦争、テロとの戦争、9.11、アメリカでのムスリムの経験、などなど。
しかしながら少なからぬ点で、石油をめぐる出会いは相変わらずつかみ損ねられている。なぜならそれについての現在の著作のほとんどが、そもそも〈出会い〉についてではなく、現象の片方の側面についてしか書いていないからだ――すなわち、西洋の側のみを。この意味で今日のペトロフィクションは、依然として振り捨てるべき過去の重荷を背負っているのである。
2018年4月16日
翻訳:中村峻太郎
出典:Amitav Ghosh, Petrofiction, Revisited, in: Stacey Balkan and Swaralipi Nandi (ed.): Oil Fictions: World Literature and Our Contemporary Petrosphere, Pennsylvania: Pensylvania State University Press, 2021, pp. 19-21. https://muse.jhu.edu/pub/2/oa_edited_volume/chapter/3639020
©2021 The Pennsylvania State University, reprinted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).
使用画像:Abadan the city of Oil, via Wikimedia Commons
[1] [訳注]石油が豊富なブライミーの土地の領有権をめぐってサウジアラビアとオマーンおよびトルーシャル・オマーン(現アラブ首長国連邦)のあいだで争われ、1952年~55年にサウジアラビアの侵攻により交戦状態に入った。https://en.wikipedia.org/wiki/Buraimi_dispute
[2] [訳注]Amitav Ghosh, “Petrofiction: The Oil Encounter and the Novel,” New Republic, March 2, 1992. この書評は、これまで文学が扱えてこなかった〈石油をめぐる出会い〉を描いた作品として、アブドゥルラフマーン・ムニーフ(Abdelrahman Munif)の小説『塩の町Cities of Salt』および『掘割The Trench』を評価したもの。気候変動のリアリティを文学が捉えられえてこなかった理由を探求する2016年の著書『大いなる錯乱:気候変動と〈思考しえぬもの〉』(邦訳は三原芳秋、井沼香保里 訳、以文社、2022年)では、ムニーフの作品に対するジョン・アップダイクの論評を批判的に検討することで、「ペトロフィクション」で指摘した問題への考察をさらに深めている(邦訳122-137頁)。