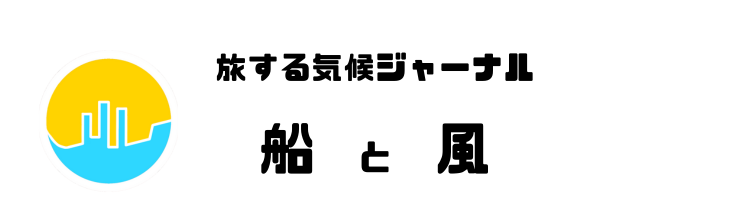トランプによるベネズエラの作戦で問題なのは石油だけではない
マシュー・ヒューバー(Matthew Huber)
『Jacobin』2026年1月8日
原文リンク:https://jacobin.com/2026/01/trump-venezuela-oil-power-economics
ベネズエラの重質原油の採掘は高コストであり、意味のある生産を開始するまでには、何年間もの持続的な投資が必要となるだろう。そのうえ、現在の石油価格ではそれが利潤を生まない可能性さえある。現在の攻撃は、経済というよりも権力をめぐるものなのだ。
アメリカが恥知らずにもベネズエラを攻撃し、ニコラス・マドゥーロを権力の座から取り除いたあと、左派の多くは次の基本的な説明に落ち着くようになった――これはすべて石油が目的なのだ、と。こうした説明は、資本主義国家の第一の役割とは資本家階級の意のままに行動することであるという、マルクス主義におけるお馴染みの「道具主義」理論に依拠している。
たしかに、第一次・第二次トランプ政権による石油・ガス産業の極端な規制撤廃のことを考えれば、多くの人々がこうした類の解釈を取ってきたのも無理はない。そして言うまでもなく、侵攻後の記者会見においてドナルド・トランプ自身が、この作戦は実際のところ石油を目的にしたものだったのだと述べた。つまり、これで一件落着というように見える。だが、実際に石油産業の政治経済学に目を向けてみると、この石油の説明はいよいよ意味をなさないものになりはじめる。
ベネズエラの石油を生産することは、そもそも利潤を生むものなのか?
石油市場は、価格の上昇と下降をともなうコモディティ循環によって作動している。価格が上昇しているときには、石油資本は新たな掘削への投資を熱心に行なう。価格が低いときには、投資もそれだけ少なくなる。現在の価格水準は、どちらとも言えないもの (現在の取引は五六ドル/バレルで、低下しつつある)であるいっぽう、全体として見れば価格は下落しており、過去十年間の大半がその傾向にあった(二〇二二年のロシアによるウクライナ侵攻と関連する好況は除く)。
ベネズエラの「重い」瀝青質原油の採掘が、きわめて困難かつ高コストであることを考えれば、六〇ドル/バレル以下の石油価格で生産した場合、そもそも収益性はないのではないかと私は考えている。ベネズエラ石油の損益分岐価格を見出すことは、おそらくデータの問題から難しい。だが、ある業界推計によれば非常によく似た条件であるカナダ石油の損益分岐価格が六五ドル/バレルであることは、記しておく価値があるだろう。
ベネズエラは世界最大の「確認済み埋蔵」を有していると耳にしたかもしれない――だがこうした言い方は、その「埋蔵」を生産することが経済的であるかどうか次第である(そして実際にそうであるかははっきりしない)ということに注意してほしい。
したがって、すでに多額の資本をベネズエラに埋没させているシェブロンを除けば、主要なアメリカ石油会社のあいだに、新たな掘削に投資をするという利害関心はそれほど存在しないはずだ。実際のところ、このことがいよいよ明白になるなかで、トランプさえもが、アメリカの石油会社は、その投資について〔国家予算からの〕「弁償」を得ることもありうるとの考えを漏らした。アメリカ議会が、アメリカの納税者がベネズエラの荒廃した石油部門の再建に支払いをするという考えに接近することなどあるのだろうか? さらに胸をざわつかせるのは、トランプによる「ギャング帝国主義」の火遊びが、二〇一六年以来すでに約二一億ドルを投資してきた中国企業に、どのような影響を与えるかということだ。
とはいえ、主要な石油会社のほかにも、この侵攻から利潤を生み出すことに何らかの利害関心を持つ資本の分派は存在する。たしかに、少なからぬ石油企業の株価は上昇している。だが私の読みによれば、これは一九七〇年代の国有化、そしてウーゴ・チャベスによる二〇〇〇年代の再国有化の波のなかで接収された財産や投資への「補償」をついに受け取れるかもしれない、という期待にもとづいたものだ。
ヘッジファンドのような金融企業においても利害関心は存在している――とりわけベネズエラの困窮状態の負債の状況のために――が、これらの企業はすでに存在している資産や負債から利潤を得ようとしており、石油生産への大きな新規投資にとりかかるつもりはない。
アメリカの精製企業のなかにベネズエラの重質石油を利用しうる企業があることもまた明らかだ。だがこれらの精製企業はすでに多量の石油をカナダのオイルサンドから得ていた。ベネズエラの重質原油がこの市場に参入することは、これらの精製企業が支払っている価格を数ドルだけ削減することになるかもしれない。だが、それがこうした企業の収益性を大きく変更させることはない。
ベネズエラの石油を解き放つことはアメリカの生産を危うくする
ガソリン価格を下げることで「アフォーダビリティ〔価格の手ごろさ〕」の問題を解決する(その甲斐あって、価格は下がっている)というトランプの矛盾した目標や、アメリカ合衆国における「掘って掘って掘りまくる」という彼の欲望については、多くのことが議論されてきた。合衆国におけるシェールオイルの生産企業が、高コストで複雑な水圧破砕技術を利用しており、それゆえ収益性を維持するために〔石油の〕高い価格を必要としている、ということも同様によく知られている。「掘って掘って掘りまくる」ことついて言えば、『スタティスタ』は合衆国内を動くさまざまなシェールオイルについての複数の試算を行なっており――どの試算も、収益を確保するためには六〇ドル/バレル以上の価格を必要としている。
言い換えれば、ベネズエラの生産が増加することになれば、グローバルな石油価格をさらに押し下げ、MAGA連合の中核にいるアメリカの石油資本家たち(および労働者たち)に損害を与える結果になりかねない。だがどのみちここでも、近い将来においてベネズエラで石油生産が増加するということには、私は懐疑的だ。
石油の政治経済学について最も鋭い分析のひとつを与えているのが、左翼コレクティブ「リトート(Retort)」と彼らの二〇〇五年の著書『悩める権力(Afflicted Powers)』だ――「二〇世紀の石油の歴史とは、不足やインフレーションの歴史ではなく、常態的な脅威、[…]過剰容量と価格の下落、余剰と供給過多の歴史である」。
元来、この脅威と闘っていたのは資本主義のカルテル――「セブン・シスターズ」の石油会社――であり、かれらはグローバルな規模で石油の生産と販売を注意深く仲間内で分割していたのだが、この役割はその後、高い価格(それは高いレント/税金に翻訳される)を維持することに関心を持っていた石油輸出国機構(OPEC)の国々によって引き継がれた。それはともかく、一般に流布する語り口とは裏腹に、石油産業はつねに切歯扼腕してありとあらゆる石油を採掘しようとするわけではない。
ティモシー・ミッチェル(Timothy Mitchell)が論じているように、石油会社のより切実な利害関心というのは、必要な稀少性を維持し再生産することで、収益性のある蓄積を行なうに十分なほど、石油価格を高く保つことである。今日の下落した価格という文脈では、石油会社は、新たな油井を掘削するのとは反対に、みずからの持つ石油を汲みだし、かつての投資を取り戻すことに、はるかに大きな関心を持っているはずだ。
「政治的なリスク」
ここで石油会社を投資から遠ざける可能性が高いまた別のカギとなる要因は「政治的なリスク」である。とりわけ採掘企業や石油企業は、政治的・法的な状況が安定しており、ねがわくば民間投資家に有利である(例えば、使用料や税率が低い)ような国に投資をすることをはるかに好む。明らかに、これはベネズエラの場合には当てはまらない。文字通りの意味で、当面だれが責任者となるのかが不明瞭であるからだ。
レイモンド・バーノン(Raymond Vernon)による一九七一年の『多国籍企業の新展開 : 追いつめられる国家主権(Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises)』〔霍見芳浩 訳、ダイヤモンド社 一九七三年〕は、「効力を失う取引(obsolescing bargain)」という力強い理論を定式化している〔邦訳:四九-五八頁〕。価格が低いときには、採掘企業は影響力を有しており、ホスト国において低い使用料と税率で好条件の取引を行なうことができる。しかしながら価格が(不可避的に)増加すると、ホスト国は、かつての協定を取り消し、使用料と税率を引き上げ、それどころかそれらをまとめて接収することさえできる。実のところ、これこそが二〇〇〇年代のチャベス政権で起こったことだと言える――石油価格の好況と結びついた左翼社会主義という環境である。
それを措いても、もし石油会社が今日有利な条件でベネズエラでの投資を行なうつもりであるなら、いまよりはるかに安定した政治状況が必要となることだろう。その点に関しては、私たちは待って様子を見ることになるだろうと思う。この分析について一つ言っておかなければならないのは、トランプ自身が投資の車輪に潤滑油を差す(すなわち特定の会社にたいして、ベネズエラ石油に投資することが別の政治的優遇を生み出すことになるとはっきり伝える)つもりがあるのかどうか、という問題である。その可能性はある。だが、低価格の時期に沈静化するという石油資本の投資パターンの歴史的な記録を克服するには、なされなければならない仕事が多くあるはずだ(とりわけベネズエラの劣化したインフラの状況においては)。
国家の絶対的な自律性
私たちは、この侵攻がアメリカの石油資本に益するために行われたとする、「道具主義的」であることを隠さない資本主義国家の説明に反論し、それを押し返すべきだ。トランプがより興味を持っているのは「軽率なリアリティショーのコスプレとしての資源帝国主義(feckless reality TV Cosplay resource imperialism)」であるとするアダム・トゥーズの記述は、はるかに真実の近くを射抜いているように思われる。侵攻ののちホワイトハウスが「FAFO」(「調子に乗ると痛い目を見るぞ」)という言葉とともにミーム画像を投稿したという事実は、彼とその政権が、いかにこうしたあらゆる下劣な素人芝居に関心を持っているのかということを、まざまざと示している。
この侵攻が、南北アメリカにおける支配を明示するというトランプ政権側の一貫した戦略(つぎはキューバとグリーンランドかもしれない。国務省は脅すような口調で「これは我々の半球だ」と主張するミーム画像も投稿した)にぴったりと収まることは明白であるように見えるいっぽう、明白でないのは、資本の利害関係――石油資本は言うまでもなく――が、どのようにこのネオ帝国主義のアジェンダと適合するのか、という点である。
もしあえて推測するとしたら、私は、この侵攻を直接的に後押しした石油会社の幹部や投資家たちが一人も存在しなかったとしても、驚くことはないだろう。マルクス主義の国家理論は、国家の「相対的な自律性」について多くのことを語ってくれる。だが、トランプによる統治という形をとった自己愛という形態が真に提起しているのは、私たちが話しているのが国家の絶対的な自律性なのではないか、という問題である。この政権が、ブルジョワジーの執行委員会として想像されるようなものと連携しないような仕方で行動するのは、これがはじめてではない。このことがグローバル資本主義全体にとって、そしてそれを監督するうえでのアメリカ帝国の中心的な位置にとって何を意味するのかということは、まったくもって不明瞭であり、今後の展開に任されている。
翻訳:中村峻太郎
©Jacobin 2026, reprinted with recognition by the author.
使用画像:Tanque de refinería Amuay en llamas.jpg via Wikimedia Commons
公開日:2026年2月3日