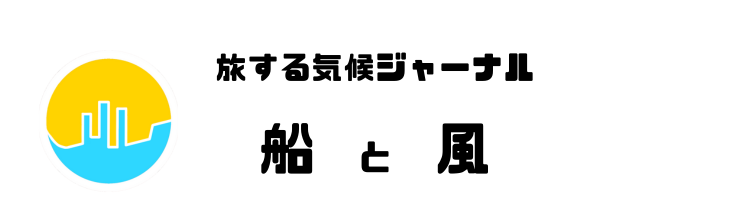概要
本論考は、Gabi Kirk, “Confronting the Twin Crises of Climate Change and Occupation in Palestine,” Arab Studies Journal XXX. 2 (2022): 90–95.の日本語訳である。
パレスチナのヨルダン川西岸地区北部にあるジェニン県は、野菜やオリーブ、アーモンドなどの農産物生産地として有名であり、西岸地区にある農地の約26%を占めている。ジェニンには主な水源として地下水、表流水、貯留水があるが、イスラエルによる水利用の制限やインフラの破壊によって水不足が長期間発生している。そのこともあり、ジェニンの農民の多くは天水農業、つまり雨水に依存した農業を行ってきた。イスラエルによる暴力がジェニンの農業を脆弱にするなかで、気候変動の影響も、その問題の悪化に拍車をかけている。本記事の筆者ガビ・カークは、ジェニンの農村地帯に約14年間通い、農民や村民たちの声を聞いてきた。カークは、ジェニンで起きている危機を、世界中で起きている植民地主義と気候変動とが結びついた問題の一部として普遍化することに反対する。むしろ、パレスチナ人が形作ってきた土地との関係の歴史、そこに向けられるイスラエルからの暴力の歴史を中心に据えることで、植民地主義と気候変動の接合的な問題に対処するためにいかにしてグローバルな連帯を導き出すことができるのか、探求の道筋を提示している。
筆者について
ガビ・カーク(Gabi Kirk)はカリフォルニア大学デービス校の博士候補者。専門は地理学、ポリティカル・エコロジー、フェミニスト地理学。研究対象として、パレスチナにおける農民や持続可能な開発制度のほか、パレスチナとイスラエルの「先住」概念の環境主義的考察、また農業・インフラストラクチャーに関する専門知識のカリフォルニア・イスラエル間の国家横断的循環など。
ジェニンの農業と双子の危機
2021-22年の秋から冬にかけてパレスチナ西岸地区でフィールドワークを行っていたとき、私と農民たちとの会話は何度も天気の話題に戻った。単に小話にちょうど良い話題だからではない。雨季の最初に降る大事な雨が11月末になるまで降らなかったのである。最初の雨のあとにオリーブを収穫する、という伝統は守られなかった。代わりに、少なくともジェニン周辺の村に住む農民たちにとって、2021年のオリーブの収穫は例年よりも早く始まり、収穫期は短く終わった。私はジェニン周辺の村に、博士論文の研究のため4年間通い、教師やボランティアとして10年近く訪問し続けている。雨量だけでなく、雨の強さと時期も心配事であった。農民や村民たちはこの年だけでなく過去数年間にわたる収穫パターンの変化について、しばしば気候変動を非難した。
ジェニン地域における2021年のオリーブの収穫は平凡だった。私はパレスチナ最大のフェアトレード・オリーブオイル会社に供給しているフェアトレード協会のスタッフと多くの時間を過ごした。私が話した農民のなかには、木々からの収量が50%から60%だったことで、良い感触を得た者もいる(これは平均的な量である)。しかし、全体の収穫量は予想を下回っており、そこには2021年冬に始まった気象パターンの影響が考えられる。アーモンドとオリーブは、発芽から葉の休眠、開花まで一定の気温(通常は摂氏7度ほど)を下回る時間と日数において似たような低温要求量を持つ。ジェニン地域のパレスチナ・オリーブの主要品種–––ナバーリー・バラディー、スーリー、ルーミー–––は4月から5月初頭にかけて花を咲かせる。ただし、オリーブの木は、春に15度以上の日があまりにも続くと開花せず、32度を超えると花は焼けてしまう1。
アーモンドは最初に開花する核果類であり、パレスチナでは概して2月にピークを迎える。2021年2月の季節外れの陽気と夏の猛暑によって、実が小さくなったり発育率が低下したり、アーモンドとオリーブの果実の発育に問題が生じた。アーモンド農家は歴史的に、暑さによる花の破壊や落果よりも、凍害を懸念していた。しかし、2021年には多雨や凍害ではなく、冬の熱気が果実の発育に問題を起こした。その渦中でも、イスラエル軍によるパレスチナのオリーブの木の破壊は止むことなく続いた。2021年10月には、2020年全体の2倍を超えるオリーブの木が根こそぎにされ、傷つけられたが、それはとりわけ入植者による攻撃の数と過激さが増大したからである2。2021年10月、ナブルスの南に位置するアワルターで、私はある家族のオリーブ収穫を手伝った。その前日、入植者はブーリーンにある、家族が収穫したオリーブを持ち込むオリーブオイル製油機を攻撃した。2022年1月、入植者たちは再びパレスチナ人と、彼らと共にいたイスラエル人を襲撃し、石を投げつけ、金属棒で殴った。彼らがオリーブの木を植えようとしていたためである。入植者は友人の車に火をつけた。イスラエルはこの攻撃に関して入植者を逮捕しなかった。2005年以来、イスラエルは80%以上の入植者によるパレスチナ人への攻撃に関する捜査を終了しているが、3%の捜査結果しか有罪判決に至っていない3。2021年の収穫期における、気候変動と入植植民地主義の両方の影響は、パレスチナ、特に占領下の西岸地区における農業生産と農業生態系の健康に甚大な被害を及ぼす、まさに双子の危機であった。
パレスチナからの気候正義研究
パレスチナの農業に対する気候カタストロフィと入植植民地主義的占領の接合的な影響は、マックス・アジルが提起した問題を中心的に考えるようグローバルな環境研究をつき動かしている4。すなわち、いかにして「帝国主義者的戦争が土地、労働、生態系、社会的再生産といった農業の問題を、不平等な開発の症状と原因(の両方)に変容させているのか」という問題である。数十年にわたる西岸地区の占領と100年以上にわたる歴史的パレスチナの入植植民地主義を「危機」と捉えることは、それが即時的で、集中的で、短命の出来事であるというイメージを喚起させるため、不適切だと感じられるかもしれない。パレスチナ、ひいては世界的な帝国主義的暴力が起きる場所では、イスラエルによる国家的暴力の即時的で目を引く瞬間–––占領下のパレスチナ全体で日常的に起きているパレスチナ人の殺害、家屋の破壊、木々の抜根–––のみで「戦争」を捉えるべきではない。戦争はむしろ恒常的に日常に潜みながら、人間と非人間に影響を及ぼす軍事化された占領の構造でもある5。イスラエルの直接的な軍事侵略と入植者による非合法な暴力、そして占領によるパレスチナ人の経済的・生態学的適応を通じた気候変動に対する闘争能力の絞殺こそが、パレスチナ農業生態系と農村コミュニティに対して仕掛けられた戦争なのである6。
グローバルな気候変動は、ローカルな影響と、国際的な原因・効果との双方を通じて理解されなければならない。近年のパレスチナは、気候変動の影響と植民地主義的簒奪の交差性の可視性の高さから、反帝国主義的な左派によって気候変動のミクロとマクロの両側面を理解させる主要地点と捉えられている。そうした分析の多くは、占領下のパレスチナ人の生活と、入植国家による土地の収奪と環境レイシズムに直面する様々な先住民との、明確な政治的つながりを導き出すために国家横断的な手法を採っている訳注1。しかし、この国家横断的手法によるイスラエル人入植者の捉え方は、様々な問題–––とりわけ、その地域や世界の物理的な場所からパレスチナを抽象的、あるいは知的に切り離すという問題–––を抱えている。パレスチナを入植植民地主義的な環境レイシズムが起きる現場と結びつけるうえで、その諸生態系、諸民族、そして諸経路を南西アジア・北アフリカの幅広い景観から切り離さないよう注意する必要がある。帝国主義的な戦争と気候変動は、爆撃や爆発による直接的な生態系への被害から野火や旱魃の激化に至るまで、連結したかたちでパレスチナとその周辺に影響を及ぼしている。
パレスチナからの理論化は、地域研究に対して批判的な気候正義研究の機会を提供する。そのことによって私たちは、旱魃や火事、汚染が矢継ぎ早に引き起こされる実際のプロセスを分析すると同時に、国際機関や専門家、そして興りつつあるエコファシズムの勢力によって常態化されている悪質な環境オリエンタリズムを分解、打開することが可能になる訳注2。知識人や環境活動家は、極めて多様な生態系やそれらとの生き方が火事や旱魃に多種多様なかたちで適応している、そのあり方を曲解してはならない7。例えば、気候変動はこれまで東地中海の降雨パターンと降水量に影響を与え続け、熱気と旱魃が増すなかで農業の忍耐力についての不安をもたらしてきたし、これからもそうだろう。だが、パレスチナの旱魃にかんするいかなる会話の際にも、イスラエルによる占領政策が地表と地中の水を吸い上げることで水不足を悪化させ、基本的ニーズを満たすには不十分な量しか残らないことを考慮しなければならない。加えて、パレスチナの農業の多くが、少なくとも100年以上は天水農業であり、乾燥農地の作物は変化する降雨パターンに適応することが求められている。パレスチナの農業生態系に対する気候上のストレスは、占領と入植植民地主義–––ひいてはグローバル化された商品市場からの圧力–––のような、小規模自作農民による農業生態系の改変を通じた気候変動への適応を妨げる体系的障壁と闘うことで緩和されるだろう8。
さらに、気候変動と入植植民地主義を国家横断的に捉えることで、知的にも政治的にもより適したかたちで、これらの危機に立ち向かうことができる。イスラエルの入植植民地主義の構造は物質的にも、言説的にも、遠く離れた複数の場所と多くの共通点を持つ。言説的には、イスラエル人たちはパレスチナ人の土地を不毛だとみなし、パレスチナ人よりも良い管理者になれると主張することで土地の剥奪を正当化してきた。それが特に悪質になるのは、イスラエルが自らをグローバルな気候の管理者であり「グリーンな」開発のモデルだと主張し、水消費を抑えた農業技術や再生可能エネルギー(特に太陽エネルギー)の研究開発を売り込むときである9。少なくともイギリス委任統治時代から、植民地主義的な科学者たちはパレスチナの気候をオーストラリアやカリフォルニア、南アフリカといった他の入植植民地と「類似のもの」と見做していた。このプロセスは、パレスチナの環境が「普遍的な景観」であるという言説を形成し、パレスチナを農業技術・工程の輸出入の対象地にするという植民地主義および帝国主義の勢力と一致した10。今日、主流メディアや欧米シンクタンクの見出しは気候変動を中東・北アフリカにおける「脅威の増幅器」であると喧伝している。こうした主張は、その地域を、西洋に飛び火するかもしれない紛争を回避するために開発の介入地とすべきだという抽象的な普遍性と同質化する。評論家は昨今のイスラエルによるアラブ首長国連邦とバハレーンとの国交正常化交渉を地球全体の利益として歓迎した。イスラエルがグリーン・テックを輸出することでアラブ世界を気候変動の最悪の効果から守るという約束を聞いたからである。その一方で、イスラエルはそうした技術へのアクセスや未来について徹頭徹尾計画を立てる能力を、パレスチナ人から奪っている11。
パレスチナにおける環境不正義を、どこかで生じる社会経済的な破滅についての早期警告として捉えるように訴える者もいる。とはいえ、こうした見方はイスラエルのアパルトヘイトのなかでパレスチナ人が被ってきた明白な過去と現在の痛みを曖昧にすることもある。どうすれば、これらの異なるスケールの分析を両立できるのだろうか。アラスカでの活動をもとに、ジェン・ローズ・スミス(dAXunhyuu)がこの問題に有効な分析ツールを提供している。それは「温暖規範性」といい、「農業実践による耕作に依存する温暖地帯を植民地化することで「より適切な」文明が生まれる、という見方が生まれる様子を説明する」ものである。農業実践を通じた定住は、文明化の普遍的な指標や基礎になっている12。スミスは、19世紀末から20世紀初頭にかけて環境決定論を構築したヨーロッパの科学者が北方の気候の過酷さをもってして白人の優位性を科学的な理由づけた、そのやり方を説明している。東地中海のような乾燥・半乾燥地域も同様に「非文明的」景観のモデルとして利用されたうえに、今日でさえ、革新的な環境活動家や知識人ですらそれを利用している。ネイティブ・アメリカンと在来環境の研究を手がかりに、パレスチナにおける入植植民地主義のもとで気候カタストロフィを理論化し、戦っていくうえで、私たちはパレスチナにおける特定の土地関係の社会史とイスラエルの入植植民地計画の詳細を中心に据えつつ、それらをグローバルな苦闘に結びつける必要がある。北極の氷冠が溶けるさまをグローバルなカタストロフィと描写することは、将来の海面上昇の見込みに話題を逸らせて、現地民族と氷との特定の関係、そして気候変動がそれらに与えている危害を見落とすことにつながる。また、気候変動と占領によるパレスチナの農業コミュニティや世帯への影響についての物語は明白で、数多くある一方で、彼ら自身も、世界中の小作農民が直面する環境破壊と経済的搾取に連帯し、共鳴している13。このような接合的危機に対する私たちの理解を結びつけ、体系化すると同時に、接合的危機の影響を普遍化したくなる衝動に逆らうことは、パレスチナや他の場所でより公正で持続可能な世界をつくるうえで不可欠になるだろう。
出典:Gabi Kirk, “Confronting the Twin Crises of Climate Change and Occupation in Palestine,” Arab Studies Journal XXX. 2 (2022): 90–95.
Reprinted in translation with permission of the authors and Arab Studies Journal.
サムネイル画像:パレスチナ、2017年(翻訳者撮影)
(翻訳:中鉢夏輝)
- Nasir S. A. Malik and Joe M. Bradford, “Is Chilling a Prerequisite for Flowering and Fruiting in ‘Arbequina’ Olives?,” International Journal of Fruit Science 5, no. 3 (2005): 30. ↩︎
- Applied Research Institute-Jerusalem and Land Research Center Jerusalem, “Unholy Communion between the Israeli Settlers and the Israeli Army to Wage War on Palestinian Olive Groves,” 2021. ↩︎
- Yesh Din, “Data Sheet, December 2021: Law Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank (Settler Violence),” https://www.yesh-din.org/en/data-sheet-december-2021-law-enforcement- on-israeli-civilians-in-the-west-bank-settler-violence/. ↩︎
- Max Ajl, “Does the Arab Region Have an Agrarian Question?,” Journal of Peasant Studies 48, no. 5 (2021): 959. ↩︎
- Bridget Guarasci and Eleana J. Kim, “Introduction: Ecologies of War,” Cultural Anthropology (2022), https://culanth.org/fieldsights/introduction-ecologies-of-war; and Caren Kaplan, Gabi Kirk, and Tess Lea, “Editors’ Letter. Everyday Militarisms: Hidden in Plain Sight/Site,” Society & Space (2020), https://www.societyandspace.org/articles/ editors-letter-everyday-militarisms-hidden-in-plain-sight-site.を参照のこと。 ↩︎
- Benjamin Pontin, Vito De Lucia, and Jesus Gamero Rus, “Environmental Injustice in Occupied Palestinian Territory: Problems and Prospects” Al-Haq (Ramallah, 2015); Sophia Stamatopoulou-Robbins, “An Uncertain Climate in Risky Times: How Occupation Became Like the Rain in Post-Oslo Palestine,” International Journal of Middle East Studies 50, no. 3 (2018): 383–404.を参照のこと。 ↩︎
- Diana K. Davis, The Arid Lands: History, Power, Knowledge (Cambridge: MIT Press, 2016).を参照のこと。 ↩︎
- Omar Imseeh Tesdell, Yusra Othman, and Saher Alkhoury, “Rainfed Agroecosystem Resilience in the Palestinian West Bank, 1918–2017,” Agroecology and Sustainable Food
Systems 43, no. 1 (2019): 21–39.を参照のこと。 ↩︎ - Irus Braverman, “Nof Kdumim: Remaking the Ancient Landscape in East Jerusalem’s
National Parks,” Environment and Planning E: Nature and Space 4, no. 1 (2021): 109–34; and Sara Salazar Hughes, Stepha Velednitsky, and Amelia Arden Green, “Greenwashing in Palestine/Israel: Settler Colonialism and Environmental Injustice in the Age of Climate Catastrophe,” Environment and Planning E: Nature and Space, (2022), 1–19.を参照のこと。 ↩︎ - Jessica B. Teisch, Engineering Nature: Water, Development, & the Global Spread of American Environmental Expertise (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011). ↩︎
- Stamatopoulou-Robbins, “Uncertain Climate”; and Benjamin Kaplan Weinger, “Scripting Climate Futures: The Geographical Assumptions of Climate Planning,” Political Geography 88 (2021): 1–13. ↩︎
- Jen Rose Smith, “‘Exceeding Beringia’: Upending Universal Human Events and Wayward Transits in Arctic Spaces,” Environment and Planning D: Society and Space 39, no. 1 (2021): 159. ↩︎
- Saturnino M. Borras Jr. et al., “Climate Change and Agrarian Struggles: An Invitation to
Contribute to a JPS Forum,” The Journal of Peasant Studies 49, no. 1 (2022): 1–28. ↩︎
訳注1. 環境レイシズムとは、環境破壊・汚染による被害やリスクが社会的・民族的マイノリティが住む地域に集中して現れやすい状況を指す言葉である。1970年代から1980年代にかけてアメリカの環境正義に関する社会運動のなかで提起された。たとえば、アメリカでは放射性物質の開発、廃棄物投棄の場所がネイティブ・アメリカンの保留地に集中するほか、有害廃棄物の処理施設が黒人コミュニティが多く住む貧困地域にばかり設けられた状況が、環境正義運動のなかで問題提起された。このような恣意的な環境格差は世界各地に存在する。ただし、イスラエルによるパレスチナ人居住地域への環境リスクの押し付けと、アメリカにおける環境レイシズムの構造とを並べて論じるうえでは、パレスチナ特有の歴史や生態などの条件を加味する必要がある。
訳注2. エドワード・サイードは『オリエンタリズム』のなかで、「東洋」を表象する学者たちの見方を通じて、時間と空間、歴史と地理が「何よりも想像的」であることを訴えている。サイードは、いわゆる専門家や科学者による主体/客体の社会的構築が、”客観的で自然なもの”で演出された想像上の知識であることを説明している。西洋の特権的な学者たちが生み出した特殊で、現地の人々にとって歪な環境、人間自然関係の捉え方は環境オリエンタリズムのいち形態と言えるだろう。植民地支配が始まる以前から、西洋の行政官や科学者は、ヨーロッパの「正常で生産的な」環境と比較して、西アジア・北アフリカ地域を「奇妙で欠陥のある」環境によって描写してきた。その描写は、環境を「改善」、「回復」、「正常化」するための開発計画や技術導入を正当化することに大きく貢献してきた。さらに、「手に負えない」遊牧民への攻撃や、「過放牧」防止策としての定住化政策が正当化されてきた。こうした想像的な環境言説は、国際機関や先進国による技術中心的な開発と相互に支え合っている。さらには、この想像上の環境を口実に、エコファシズム、すなわち自集団、あるいはその環境を保護するためにある人種やマイノリティに対する差別や暴力を正当化する事例が見られることを筆者は指摘している。