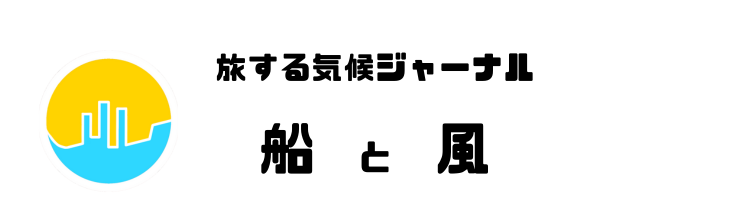レバノン・ベイルート生まれの人類学者ガッサン・ハージは、現代世界におけるレイシズムや多文化主義、植民地主義などについて、人類学や民族誌の見地から議論を展開してきた。ハージはWhite Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society(1998)(『ホワイト・ネイション——ネオ・ナショナリズム批判』(2003年、塩原良和訳))やAlter Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination (2015)(『オルター・ポリティクス——批判的人類学とラディカルな想像力』(2022年、塩原良和・川端浩平監訳))などの著書を残しており、多文化主義研究や批判的人類学の分野で国際的に広く知られている。ハージはシドニー大学、メルボルン大学を経て、2023年からはドイツのマックス・プランク社会人類学研究所を拠点に研究活動を行ってきたが、同年10月7日以降のパレスチナ・ガザにおけるイスラエル軍によるジェノサイドに対して批判的な発言をしたことから、同研究所を解雇されている。
本記事はハージが2017年にPolity Press社から出版したIs Racism an Environmental Threat?『レイシズムは環境にとっての脅威なのか?』のIntroductionを日本語に翻訳したものである。ハージは本書において、レイシズムがいかにして人間や自然環境に対する支配的な関係を再生産しつづけて、さまざまな主体が存在するこの世界を危機に晒しつづけているのか、「一般化された飼いならし」*という概念的枠組みから論じている。ハージはこれまで、レバノンやイスラエル、オーストラリアにおける多文化主義的な言説や実践から、ホワイトな主体が利用できる他者のみが包摂され、それにそぐわない意思を持つ他者は排斥される「飼いならし」の構造を捉え返してきた。本書は、飼いならしの構造を世界と関係する存在様式一般にまで敷衍させながら、飼いならしによって過剰に支配されることのない、人間と自然的他者との関係様式のオルタナティブについて提案している。
*「一般化された飼いならし」という表現については鈴木赳生さんの論文「多文化主義思想における他者性の否認」『ソシオロジ』63巻3号(2019年)を参考にしました。
レイシズムは環境にとっての脅威なのか?
イントロダクション
ガッサン・ハージ
Ghassan Hage
今日、ある社会現象がエコロジーの危機に関係していると主張するのは難しいことではない。エコロジーの危機は人類が直面する最も重大な危機である。危機が「生態学的」や「環境的」なものとみなされるとしよう。それはもはやxやyという特定の対象との関係についての危機ではない。それは、私たちがxやyとの関係を持ちうる、まさにその場が危機に陥ることなのだ。この危機を象徴するのが、2015年のレバノンで起きた廃棄物危機である。それは、レバノンにおける経済的・政治的な党派間闘争の論理と複雑に絡まり合った廃棄物処理システムの崩壊として始まった。人々がゴミをどこにでも捨てはじめ、ゴミは既に汚染されていた環境を悪化させはじめた。やがて路上の匂い、海や山の醜い景観、汚染された河川があらゆるものに浸透し、不便、不快感、病気を引き起こすようになった。「廃棄物処理」はもはや廃棄物との関係が手に負えなくなっただけには留まらず、社会全体の雰囲気を構成するものになった。それは人々の働き方や気分、子どもたちの遊び場、何をどこで食べるか、どのように、どこで運動するかなどに影響を与えた。今日、私たちが全世界で直面している「環境危機」を定義するのは、このような包括的な性質である。
上に例示した危機の包括的な特徴ゆえに、いかなる社会現象も環境危機と関連していると主張することは常に可能である。それどころか、そう主張することが分析的にも、倫理的にも不可欠となっている。この危機は地球を沈みゆく船にする。船が沈没していないかのように、船上の何かだけを扱って研究することは無益であり、蒙昧主義的ですらある。さらには、自分が研究していることが、どのような形で沈没を食い止める助けになるのかを示すこともまた不可欠である。本書の記述はこうした分析的、政治的、倫理的な要請を念頭に置いている。これにより私は、これまでに多くの活動家の間で形作られ、動物解放論者やエコフェミニズム論者が何年も前から繰り広げてきた、種差別とレイシズムに関する政治的主張を統合することを目指している——今日、エコロジストであることなしに反レイシストであることはできないし、その逆もまた然りである。
ただし、上述のようにエコロジーの危機がレイシズムにどのような影響を与えるのかを浮き彫りにすることは重要であるかもしれないが、本書の中心的な議論はこの因果関係に逆行する。本書の目的はレイシズムそのものがエコロジーの危機をどのように悪化させているのかを解明することである。本書の議論では、今日非常に蔓延しているレイシズムの具体的な形態、すなわち一般にイスラモフォビア(イスラーム恐怖症)と呼ばれる反ムスリム的なレイシズムを取り上げる。私がイスラモフォビアに注目することにしたのは、それが世界に蔓延り続けているレイシズムの最も重要な形態の一つ、すなわち奴隷制と植民地主義に根ざした西洋/白人のレイシズムだからである。誤解のないように言っておくと、レイシズムは白人のみがかかる病気ではないことは私も承知している。私は多くの場所で非白人によるレイシズムを目撃し、書き記してきた。にもかかわらず、グローバルな影響という観点からさまざまなレイシズムをランク付けするならば、非白人によるレイシズムは、本書で検証するそれよりも重要度が低いと言っても良いだろう。実証的な頻度、人々への影響、そして既存の国内・国際制度への構造的影響や浸透の度合いという観点から見ても、そう言える。
少なくとも今世紀に入ってから、反ムスリム的な実践や考え方が、現代特有のレイシズムの支配的形態のひとつとして顕在化している。今世紀は「イスラームという他者」のグローバリゼーションが世界中で発生した。そして、それはあらゆる形態の文化的グローバリゼーションと同様に、均質化と差別化の矛盾したプロセスを孕んでいた(Hannerz 1996)。つまり、抽象的な「イスラーム」と違いの無い複数の「ムスリム」がグローバルな脅威として同質に扱われる一方で、イスラームの脅威を具体的に表現するカテゴリーは国ごとに異なっていた。ムスリムという他者は、イギリスでは「アジア人」(そこではインド人やパキスタン人を意味する)、ドイツでは「トルコ人」、フランスでは「北アフリカ人」、オーストラリアでは「レバノン人」、そしてはアメリカではより漠然とした「アラブ人」であることから始まった。とはいえ、これらの国家単位でも、21世紀の最初の10年間に、パレスチナ人やアフガニスタン人、アフリカン・ムスリム、アラブ系や非アラブ系がほぼ全域に増えたことで、その様相は急速に複雑化していった。今日では、シリアやイラクでの紛争を逃れた難民の流入の結果、シリアやイラク国籍の者も「ムスリムのその他大勢」に加わっている。さらに、アル=カーイダ、そしてISISの台頭は、さまざまな民族的・国家的背景を持つ移民や欧米生まれの人々の間で、国境を越えたムスリム急進主義の世界的な拡散を加速させ、ムスリムというケーキに「他者性というアイシング」をトッピングした。
このグローバル化に伴う人種的実践は数多くあり、その数は増加の一途を辿っている。統計データや事例データは豊富にあり、それらはムスリムやムスリムらしき人に対する襲撃事件の発生状況を監視している世界中の国際機関や国家機関から入手することができる。路上や公共交通機関でムスリムの女性が怒鳴られたり、罵倒されたり、ヒジャーブを剥ぎ取られたりするケースは多く見られる。このような行為は、9.11のはるか以前、20世紀後半にはすでに広まっていたが、今日では西洋諸国全体で非常に多くなっているのだ。ムスリムの求職者が、ムスリムであると疑われた途端に、雇用を拒否されるという報告も増えている。同様に、ムスリムの労働者は職場でからかわれ、辱められ、差別されている。さらに一般的には、ムスリムは自分たちのタブーの尊重を拒否されることとも戦わなければならない。国際的によく知られた事例では、預言者ムハンマドの風刺漫画やハラール肉への反発がある。彼らは、シリア、イラク、アフガニスタンなどの紛争地帯であれイスラエルであれ、あるいは避難先へ向かう海上であれ、ムスリムの命が軽んじられ続ける事態に直面している。彼らはまた、ムスリムへのバッシングが常態化し、政治家たちの人気取りの手段とみなされるようになった西洋諸国の選挙運動文化にも直面している。ムスリムがテレビをつけたり新聞を読んだりするたびに、メディアが売りつける多様な偏見と折り合いをつけなければならない。同時に、自分自身や同胞のムスリムが有刺鉄線の向こうにいる光景を日常化しながら生きなければならない。刑務所であれ難民キャンプであれ、ヨーロッパのどこかの国境や、オーストラリア政府がオーストラリア内外に建設した留置所で待つときの光景である。このような光景や慣行は、至るところで見られる人種化や周縁化という現象の、より一般的で目立たない日常的で些細な形態のうえに生じる——それは、忌避、拒否、攻撃、憎悪に彩られた相互交流である。このようなイメージと実践の総体は多くの者にとって避け難い感覚を生み出している。今や「ムスリム」は『地に呪われたる者』だとする感覚すらある。
にもかかわらず、イスラモフォビアを「ちゃんとした」レイシズムと区別したがる分析家もいる。彼らがそうするのは、近代の初期に出現したレイシズムの歴史と論理に根ざした、より厳格で厳密な定義にもとづくからである。そのような書き手によると、人種に関する何らかの生物学的概念に準ずる思考様式を扱わない限り、人種やレイシズムについて語ることは有益ではないという。本書の目的から触れておくと、こうしたアプローチは、ピエール・ブルデューがスコラ的思考の一形態であると批判的に指摘するものの特徴を全て備えている(Bourdieu 2000: 49)。ここでいう「スコラ的」とは、レイシズムをその実践的・実用的文脈から切り離し、ある種の純粋な知識や、分類学のための類別を狙いとした学問的訓練として捉える思考様式のことである。
この知性偏重的傾向は、反レイシズム的分析と反レイシズム的政治の両方に制限をかけるような影響を及ぼしてきた。実際、史上のレイシズムと反レイシズムを比較してみると、レイシズムは学術的な反レイシズムよりもはるかに柔軟なあり方を示してきたといえる。レイシズムは変容し、さまざまな人々を、ときには多くを同時に、標的にしてきた——黒人やアジア人、アラブ人、ユダヤ人、ロマ、そしてムスリムなど。隔離、条件付き統合、そして最も劇的な場合は抹殺、といった技術の一部としてレイシズムは展開されてきた。その対象は、遺伝的外見、生物学的なもの、文化的なもの、あるいはそれらの組み合わせなど、その時代の支配的な分類様式にうまく適応しながら、効率的に構築されてきた。それに比べて、学術的な反レイシズムは概念として硬直的であり、レイシストが使う流動的な分類様式に常に追いつけないでいる。
レイシストたちはレイシズムをある形態から別の形態へと嬉々としてすげ替えるが、論理的矛盾や一貫性のなさ、議論の食い違いについて気にすることはほぼない。対して、反レイシズムの学者たちは、まさにそうしたことを気にしてレイシストを裁こうと膨大な時間を費やしている。彼らは、現実の解釈の仕方について、講義室で難癖をつけてくる学生や学者仲間であるかのようにレイシストを批判する。レイシストにとって最も重要なことである、レイシズムの命に関わるほどの行為遂行性に対しては、十分な注意が払われていない。あたかも、レイシストの最大の罪は、彼らが悪い思想家であることであるかのようだ——彼らは「本質主義者」であるか、「古典的生物学的レイシズム」から逸脱しているか、または現実について誤った経験的発言をしている。反レイシズムの学者たちは、その誤りを証明する大量の統計データを強調することで、誤りを正そうと長時間働いている。
例えば、本書に関わるケースでは、イスラモフォビアの分類化は、アラブ人、ムスリム、「イスラーム」の間で、つまり人種表現、民族的ステレオタイプ、宗教的一般化の間で、曖昧に絶えず揺れ動いている。つまり、人種で分ける人たちから見れば、アラブ人とムスリムがどこから始まりどこで終わるのか、どこで分離し、どこで混合するのか、さらには、西洋のレイシストにとっての「第三世界のように見える人間」を線引きするための境界線さえ分からないのである。レイシストも警察も、潜在的な「ムスリムのテロリスト」を警戒して、南米人、アフリカ人、シーク教徒、ヒンドゥー教徒、ギリシャ人、南イタリア人、その他大勢を殺したり逮捕したりしてきた。差別経験に宿る想像的本質について重要なことを知るためにも、レイシスト的な思考を曖昧なままにしておくことは極めて重要である。実は、この曖昧さは、現実的な観点からは重要ではない。レイシストは曖昧であることによって非常に効率的であり続けてきた。曖昧さ、実証的な「一面性」、矛盾、明白さの遮断、そして時には完全に超現実主義的な現実の把握さえも、レイシズム的実践を最大効率で行う可能性の条件そのものであると言えるだろう。レイシストが実証的に誤った分類を用いていることに注目していると、こうしたことは全て見逃されてしまう。
このことは、レイシズムと種差別主義の関係を研究する際に特に重要となる。動物は(そして時には植物も)、自然を家畜化する過程で分類され想像されるように、被支配者や劣等者を描写するメタファーの源として長い間用をなしてきた。これらのメタファーを分析すると、すぐに学問的な「実証的反レイシズム」の貧しさに直面する。黒人をサル、ユダヤ人をヘビ、ムスリムをゴキブリや狼として捉えるように、レイシストが時間や場所に応じて絶えず変化・変動する分類的メタファーで考えている隠喩空間を目の当たりにしたとき、「ちょっと待って。ユダヤ人はヘビじゃない」とか「ムスリムは狼じゃない」と「実証的」に証明しようとするために1秒でも費やす意味があるのだろうか。正直言って、言わずもがな、誰もそんなことはしない。しかし、それが明確な比喩であろうとなかろうと、このような動物的メタファーは全ての人種的分類化の本質を明らかにする、という主張はなされるべきだ。動物的メタファーに直面したとき、正しい主張かどうか問い詰めるのではなく、より重要な問いを立てることを求められている。例えば「ユダヤ人の他者やムスリムの他者をイヌ、ヘビ、ハイエナ、狼のように想像することは、レイシスト自身について、彼らの権力観について、彼らの他者に対する実践の性質について、何を物語っているのか」という問いだ。私の考えとしては、これは「シャリーアがこの国を征服しようとしている」というようなメタファーとも異なる疑似経験的な発言に直面したときこそ立てるべき問いでもある。その主張が実証的に意味をなさないことを説明するために時間を費やすべきではない。
実際、レイシズム的な動物への当てはめからレイシズムについて多くのことを学ぶことが出来る。というのも、レイシズムのより一般的な学術的定義よりも、他者に対する日常実践の志向性について学ぶことができる。なぜなら、メタファーが実践的な志向性を体現しているからだ。メタファーは「何をすべきか」を完全に指示する「マニュアル」を伝える。例えば、レイシズムを劣等感や劣等視と結びつける古典的な例を見てみよう。この連想は大方明白で正確であり、重要な帰結をもたらすが、それ自体が必ずしもレイシストを特定の行動に向かわせるわけではない。「劣等」はさまざまな意味を持ちうる。時には、誰かを劣等と明らかに分類することの背後には、その分類者がその人を恐れ、少なくとも何らかの形でその人を優勢と思っている、という事実が隠されている。それほど両義的ではないが、人は誰か・何かを「劣等」だと分類しても、その対象をとても愛らしく魅力的に思うことがある。実際、乳児は大人から「劣っている」と見做されることがある。また、家父長制思想の多くは、女性を「劣っている」とみなす一方で、女性を美や愛、ケアの対象物として描いている。劣等感についての考え方にどのようなイメージが付与されているかがわからなければ、その実際の意味を正確に理解することは難しい。しかし、奴隷が「雄牛」と呼ばれたり、女性使用人が「子羊」と呼ばれたりするときに、このような言葉の背後にある実際の人種的イメージをより良く知る手がかりがある。わたしたちは彼らの「雄牛化」や「子羊化」から、彼らと何をすることが望ましく、可能で、好ましいかを学べる。同様に、わたしたちはレイシストが「ユダヤ人」を「ヘビ」や「ウイルス」と結びつけるときに彼らが何をしたいのかを知る。その結果取るべき行動は、彼女が「劣っている」と断定されるときよりも、はるかに明確である。動物的メタファーは、単なる「レイシストによる観察的分類」ではなく、意思表示でもあるのだ。
したがって本書は、レイシストがどれだけ知的に正確であるかというより、レイシストがどれだけ思惑通りに物事を進めているのか、ということに関心がある。私の議論に関する限り、共通かつ継承可能な決定的特徴を共有すると考えられる人々のアイデンティティ・グループに対して問題視し、排除、疎外、差別し、不安にさせ、搾取し、違法扱いし、怯えさせ、排除される幻想を抱かせることを目的とする実践の束を「レイシズム」と呼ぶに足りる。これは、人種的思考が同時に人種的実践になることがないことを念頭に置くのであれば、ハンナ・アレントが「人種思考」と呼ぶものの延長とみなすことができる(Arendt 1944; see also Razack 2008)。レイシズムを実践的現実として捉えることで、物事の見方に関する問題が前景化する。レイシズムには二つの実践的経験が含まれる——加害者の経験と、それに従属する者の経験である。レイシズムに関する多くの分析は、この二つを十分に区別していない。ニーチェ(1997)が警告した「いかなる方向も持ち合わせない眼が生み出す“純粋な知識”」を想像する哲学者たちからすれば、分析の対象は、遠近法を持たない「レイシズム」なるものとして想像される。これとは対照的に、本書の議論は強力な遠近法的である。ただし、そうすることによって、イスラモフォビアを表明したりイスラモフォビア的な行動を取ったりする主体が「イスラモフォビア的であるか、そうでないか」のどちらかではないことが前提となる。イスラモフォビアは、そうした主体の存在が持つ側面の一つである。それはそれぞれ異なる形、程度、強さで、その人の思考や実践を彩っているのである。イスラモフォビアに関する実証的社会学は、それらの違いと、違いに影響を与える変数を検証することを目的とするものといえる。だが、それは私が本書で目指しているものではない。むしろ、私は、一般的な存在様式としてのイスラモフォビアとイスラモフォビア的文化に、より強い関心を抱いている。この世界をイスラモフォビア的に経験するとはどういうことだろうか。イスラモフォビアは、自分の環境や周囲に対して、どのような帰属様式を前提とするのだろうか。それによって、どのような主体が呼び起こされるのか。それは、どのような他者性の分類を、そしてどのような種類の実践を生み出すのか。さらに、おそらく最も重要な問いが、人はどのようにして自分の人生の実現可能性をイスラモフォビア的に演出するのか。つまり、イスラモフォビア的に行動することで、自分たちの生きがいを守っていると考えるようになるのはなぜなのか。本書の重要な論点は、これらの問いに答えることで、レイシズムが環境に対する脅威を引き起こすやり方のなかでも最も重要な一つに、私たちは向き合うことになる、ということである。
レイシズムが環境危機に影響を与えうる方法は数多くある。環境レイシズムという下位分野全体は、生態学的危機の有害な影響の生産と分配における人種的な公平性と正義に関する問いに徹する(Bullard 1993)。こうした研究はしばしば、他の社会過程と同様に、レイシズムが環境現象に影響を与えながらも環境現象から独立した、外部にあるものと考えてしまう。つまり、レイシズムはある空間で繰り広げられ、環境危機は別の空間で展開し、両者は偶然に出会うものと考えられている。これは、人間と自然、および人間と人間の関係という一般的な分析上の区別に従っている。したがって、狩猟、採鉱、小麦栽培の実践における変化は生態学的領域に直接関わるとされる一方で、性差別や税制のような多様な実践はそうみなされないのである。レイシズムは、後者の実践の一種と考えられている。本書は、レイシズムを前者に位置付ける議論に集中している。イスラモフォビアによって顕在化した人種的危機とエコロジーの危機はたまたま互いに影響を及ぼし合うだけでない——それらは事実上単一かつ同一の危機である。人種的支配と生態学的支配の双方によって再生産されている、この世界の支配的な存在様式に宿る危機なのだ。したがって、レイシズムが環境にとって脅威であるのは、単にそれが外部から環境危機に影響を与えるからではなく、内部から環境危機を激化させるからでもある。これは矛盾した主張である。より弱く、より強い因果関係の論証を同時にしているからだ。この主張は、レイシズム的実践が環境に及ぼす直接的な因果的影響について論証しないという点で、説得力に欠ける。しかし、より根本的な因果関係を浮き彫りにしているという点で、より強力である。レイシズムは環境にとっての脅威である。なぜなら、レイシズムは環境危機の発生の背後にある基本的な社会構造の支配を強化し、再生産するからである。そして環境危機は、その発生自体の背景にある構造も成している。
本書は、こうした基本的な構造とは何か、レイシズムがそれを正当化して強固にする方法とはいかなるものか、考究していくかたちで構成されている。本書はまずエコロジーの危機とイスラモフォビアに見られる危機の間にある多くの類似点を指摘する。次いで、これらの類似性の根源がどこにあるのかを精査する。そこでは、相互に連関する3つの領域が探究される。その根源は、第一に、レイシズムと環境支配に共通する他者化、支配、統治性のかたちで特定される。第二に植民地主義に伴う資本主義による人と資源の搾取のダイナミズムから、第三に存在様式としての「一般化された飼いならし」の構造から特定される。本書は類似するこれらの領域それぞれを扱う。レイシズムと種差別の最も基本的な生成構造を見出すことができるのは、第1章で検討する統治性、支配、他者化の様式でも、第2章で検討する植民地主義・資本主義的搾取でもない。それは、第3章で論じる「一般化された飼いならし」からこそ見出すことができる。レイシズムが再生産するのは、この一般化された飼いならしである。これを通じて、今日の世界を苦しめている有害な環境との関わり方も再生産される。最終章では、一般化された飼いならしによって支配されることのない、人間と自然の他者との関係様式のオルタナティブについて考えていく。
引用文献
Arendt, Hannah. 1944. “Race-Thinking Before Racism,” The Review of Politics, 6, 1: 36-73.
Bourdieu, Pierre. 2000. Pascalian Meditations. Polity Press.
Bullard, Robert D., ed. 1993. Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots. South End Press.
Hage, Ghassan. 2000. White Nations: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society. Routledge.
〔= 2003, 保苅実・塩原良和訳『ホワイト・ネイション——ネオ・ナショナリズム批判』平凡社〕
Hage, Ghassan. 2015. Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination. Melbourne University Press.
〔= 2022, 塩原良和・川端浩平監訳『オルター・ポリティクス——批判的人類学とラディカルな想像力』〕
Hannerz, Ulf. 1996. Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge.
Nietzsche, Friedrich. 1997. On the Genealogy of Morality. Cambridge University Press.
Razack, Sherene. 2008. Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics. University of Toronto Press.
(翻訳:中鉢夏輝)
※翻訳・内容理解に際して、中村峻太郎さんの貴重なご助言をいただきました。記して感謝申し上げます。
出典:Hage, Ghassan. 2017. Is Racism an Environmental Threat? Cambridge: Polity Press: 1-16.
Reprinted in translation with permission of the Author.
サムネイル画像:レバノン、ベイルート、2017年(翻訳者撮影)