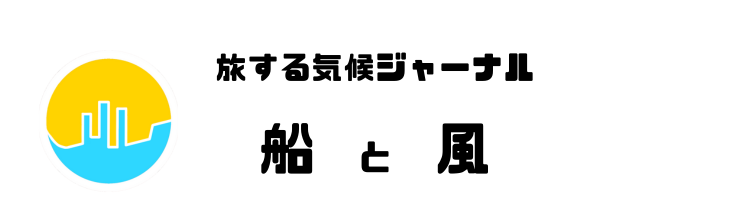タンクと、そのいくつかの壁:パレスチナの抵抗について
アンドレアス・マルム
2017年5月1日
注記〔2025年7月23日〕:この論考の翻訳は、改稿・改題のうえ、青土社から刊行されるアンドレアス・マルム『パレスチナを破壊することは、地球を破壊することである』(箱田徹 訳)に収録される運びとなりました。この記事もこのまま残しておきますが、改稿の過程で行った誤訳の修正や新たな注釈の追加等は、こちらの記事には反映しません。ですので、今後本テクストを引用・参照される際は、上記書籍のバージョンを定訳として扱っていただけますと幸いです。(訳者しるす)
〈ナクバ〉[大いなる災厄]
すべてが失われてしまったあとで、どのように闘いつづけるというのか? パレスチナ人に訊いてみるといい。パレスチナ人とは、瓦礫に膝まで埋まりながら歩みを進める者のことだ。パレスチナの政治とは、いつであれ、すでにアポカリプス以後のもの――世界の終わりのあとを生き延びること、そして最良の場合には、あらゆるものが失われたなかから何がしかを救い出すことをめぐって、なされるものなのだ。

パレスチナの作家たちは、世界の終わりをどのように描いているのだろうか? 『船(The Ship)』という小説で、1948年にパレスチナを去りイラクへ向かった作家ジャブラー・イブラーヒーム・ジャブラー(Jabra Ibrahim Jabra) は、「いくつもの川や滝」が流れる土地を振り返って見遣り、同胞たちが「炎立つ砂漠や悲鳴をあげる産油都市」へと放逐されていくことを嘆いている。彼の詩「亡命の砂漠で(In the deserts of exile)」において、同じ軌道が辿りなおされる。
われらがパレスチナ、われらが緑の地 (…)
三月は丘陵を飾り立て (…)
四月は平原に咲き乱れる(…)
かれらは周囲の丘の花を踏みつぶし、
私たちの頭上で家々を破壊し、
傷ついた生存者たちを追い散らし、
私たちのまえには砂漠が開かれた(…)
われらが土地は一粒のエメラルド、
だが亡命の砂漠にあって、
来る春も来る春も、
私たちの顔には砂塵だけがするどく吹きつける。
伝説的な作家でありPFLP[パレスチナ解放人民戦線]のスポークスパーソンであったガッサーン・カナファーニー(Ghassan Kanafani)もまた『太陽の男たち(The Men in the Sun)』のなかで、前日の雨で湿った地面――かすめすぎる幻覚のように、ほんの最初の頁にだけ現れる――から、四方に広がる不毛の砂漠へ、という航路を描いている。人間の身体が耐えられなくなる温度にまで、永久に上昇しつづけるかにみえる太陽の熱の下へと。三人の男たちは、砂漠を通ってクウェートの産油都市へ渡ろうとする。おそらくパレスチナをめぐるフィクション作品のなかで最も有名なシーンだが、かれらは密入国の仲介人が国境で足止めされているあいだ空の給水タンクのなかに隠れ、耐えられない暑さのために死んでしまう。仲介人はかれらの死体を発見し、叫び声をあげる。その叫びは、幾世代にもわたるパレスチナの抵抗文化のなかで、こだまのように響きつづけている。「なぜお前たちはタンクの壁を叩かなかったんだ? なぜ思い切りタンクの壁を叩かなかったんだ?」
この権威ある二人のパレスチナ人作家であれ、あるいはアラビア語で書く他の誰であれ、グローバルなベストセラー作家としてのスーザン・アブールハワー(Susan Abulhawa)の地位に肉薄する者はない。パレスチナ人の経験を英語圏の文学マーケットのまさしく主流に持ち込み、そのうえ何十もの他の言語に翻訳されるというのは、彼女の二つの小説作品『ジェニーンの朝(Mornings in Jenin)』と『空と水のあいだの青色(The Blue Between Sky and Water)』だけがなしえた特異な達成だ。どちらの作品も、パレスチナの生活世界についてのプレリュード、そうした世界の終わり、それ以後の登場人物たちの艱難辛苦、という同じ三部構成にしたがって書かれている。プレリュードは、『朝』ではオリーブの収穫を、『青色』では養蜂を中心に描かれる。どちらもはるかな昔から村で行われてきたものであり、その村では川が――「神様が詰めあわせた魚や植物で溢れそうになりながら」――農民たちの噂話や祈る声を運び流し、かれらの生活の鼓動にあわせて蛇行していた。それからハガナ[1920年に創設されたユダヤ人の正規の軍事組織。イスラエル建国とともにイスラエル国防軍(IDF)へと再編された]が「機械兵器や戦闘機とともに」やって来て、村は炎のなかに投げ込まれた。「煙雲が低いところを旋回して世界を黒く塗りこめ、暗い屍衣のように死者たちにまといつき、生者たちの肺に侵入する。かれらは喘ぎ、痙攣しながら避難場所を探す」。
しかしながら、パレスチナ人の経験の特有さは、終わりの瞬間が果てしなく繰り返すという点にある。
終末は、1948年に終わりを迎えたわけではない。アブールハワーは『ジェニーンの朝』のなかでその年を「歴史のなかの一つの契機、すなわち無限に広がる靄」と書いている。「未だ来ぬものに祝福を!(Blessed be that which has not come!)」という詩のなかで、マフムード・ダルウィーシュ(Mahmoud Darwish)はその年を「終わりを持たない年」と呼ぶ。難民たちの帰還が妨げられているだけではなく、住民たちの頭上で家々を破壊するという当初の行為が、何度も何度も繰り返されている。1950年のマジダルから、2016年のアラーキーブにいたるまで。新鮮な瓦礫が、いつでもパレスチナ人たちのうえに注ぎかけられる。『ファーカハーニー広場を見下ろすバルコニー(A Balcony over the Fakihani)』のなかで、リヤーナ・バドル(Liyana Badr)はこうした永遠の繰り返しのうちの一つ、1982年のベイルートの出来事を描写しているが、彼女の言葉はほかのどんな繰り返しに対しても当てはまるだろう。
積み重なったコンクリート片、たくさんの石、散り散りになった服の切れ端、粉々のガラス、小さな綿くず、金属の破片、破壊された家屋や、頭がおかしいほど傾いだ家屋を、私は見た。 (…) 白い塵によってその地区は窒息し、煙の灰色のなかから、空洞になった煉瓦の外殻や、倒壊した家屋の瓦礫がぼんやりと見える。(…) そこではあらゆるものが互いに入り混じっていた。車は逆さにひっくり返り、紙は宙を舞っていた。火。煙。世界の終わり。

『ファーカハーニー広場』の結末近くで、バドルは登場人物の一人をパレスチナの国境付近へと向かわせている。そこで彼は、山のふもとの緑の広がりのなかに、自分の故郷の村の姿をほんの一瞬、見分けることができる。そのとき、パレスチナ人の政治は世界の終わりの後を生き延びることだ、と述べるのは誤りだ。そうした終わりはむしろ、1948年に作られた軸線に沿って、更新され、再構築され、再強化されている。いくつもの川や湿った地面から、砂漠へ、暑熱へ、炎と煙へ、倒壊した家の瓦礫へと。渡河はいまだに完了していない。パレスチナ人たちはもう一方の側へ渡ることが決してできないかに見える。タンクの内側で、かれらは生き延びようとしているのだ。
パレスチナの命運についてのこれらの描写が作家たちの想像力の産物であるとすれば、私たちがいま手にしているのは、より手ごたえのある証拠を提供してくれる壮大な写真のコレクションだ。『パレスチナ人たち:1839年から今日までのある土地とそこに住む人々の写真集(The Palestinians: Photographs of a Land and its People from 1839 to the Present Day)』においてイルヤース・サンバル[エリアス・サンバー](Elias Sanbar)は、破局以前の生活についての記録を収集している。その大半はヨーロッパ人カメラマンのレンズによって歪められており、聖書の舞台の地、荒れ果てた廃墟、霊的な源泉、ないし誰も住んでいない土地といったパレスチナに関する先入観――そうしたイデオロギー素はすべて、サンバルの鋭いコメントによって厳しく批判されている――に一致するように作られているにもかかわらず、そこからはパレスチナの生活のリアリティという輝きがつねに透けて見えてくる。1948年以前、そうしたリアリティを写真の枠外に押し除けておくことはできなかったのだ。
私たちは、タバリーヤ川の漁師たちが網の手入れをするのを目の当たりにする。バイト・ラフム(ベツレヘム)の女たちが水を汲んだ甕を頭に載せている。船に満載された果実がヤーファーの港を離れ、労働者が厚手の手袋でオレンジを摘んではいくつものバスケットを一杯にし、一番高いところにあるオリーブに届くように農夫が梯子の位置を変え、巨大な梱を頭に載せた女たちが収穫から帰って来る。若い母親が赤子を抱え、ベールの端を噛んで誘いかけるように微笑む。上等な身なりの女が四つの枕に凭れて〈水煙草〉を吹かす。アル=クドス(エルサレム)旧市街の城壁では農民たちが小麦を刈り入れ、銅職人が容器のふたを金槌で叩き、石切り工たちは鶴嘴と手斧を覗かせ、荷物を背負ったぼろい衣服の男の一歩先を商人が主人然として歩いていく。露店商が道行く人々に差し出す、トマトや馬鈴薯やパンや敷物。ピクニックに来た群衆がアル=アウジャー川の土手沿いに散らばっている。水で溢れそうなヨルダン川でボートを漕ぐ人々。タバリーヤ(ティベリア)は中央モスクを囲む家々の集まりで、どの方向を見ても、緑と青の山々や湖に囲まれている。スィルワーンの街区はアル=クドスを囲む丘の一つをやわらかく抱き留め、その他の丘々は地平線に向かって広がっていく。 ナースィラ(ナザレ)の写真の半数では、前景に花々が咲き乱れている。ハイファーはターコイズ色の海岸にゆったりと安らっている。ハラムーン山の頂上ではターバンを巻いたシャイフが雪のなかで跪拝し、どこか別の場所の修道院のまえでは踊り手たちが〈ダブケ〉を披露する。
そんななか、サンバルが名付けるところの「溺死」の瞬間が割り込んでくる。「1948年、一つの国が消滅し、溺死した。数週間のあいだに、亡命状態になった。人々は徒歩で、トラックに載せられて、船で、あるいはその他の間に合わせの移動手段で故郷を離れ、不在という影がかれらを呑み込んだ」。
残存している最も古いパレスチナ難民キャンプの写真には、泥のなかを歩いている一群の女たちが写っている。彼女らの背後には、黒の森とナハル・アル=バーリドの灰色のテントが控えている。2007年夏のうだるように暑いある一週間、私は彼女らの曾孫世代の人々とともに難民キャンプ――そのころには紛れもない都市に変わっていた――の周囲に立ち、ナハル・アル=バーリドがレバノン国軍の戦車によって煙くすぶる瓦礫の山へと変えられてゆくのを眺めていた。

パレスチナと残りの世界とのあいだには、どのような関係があるのだろうか? 『グローバルなパレスチナ(Global Palestine)』のなかでジョン・コリンズ(John Collins)が主張しているのは、パレスチナという特定の国を、例外として、いつまでも解消できない異常として、あるいは近代が後に残した植民地主義の遺物として見るかわりに、ヴァルター・ベンヤミンが言う意味での〈モナド〉として捉えるべきだということだ。世界中で作動しているさまざまな強制力が、この国のなかで結晶化している。そうしたいくつもの力が、極端な凶暴さをともなってパレスチナの地で集合する。そしてそれは、他の人々もまた直面することになる未来への手がかりを内包する実験室、ないし「予言的な索引」として機能する。「私たちはみな、パレスチナ人になりつつあるのだろうか?」とコリンズは問う。グローバルな趨勢の一覧表――分離壁の急増、ドローン戦争の勃興、軍事的抑圧を目的とするテクノロジーの全般的な加速――は、この質問に肯定形で答えるよう、彼に促す。彼はまた、自然環境の破壊、ないし「環境に対する戦争」にも言及している。だが、パレスチナというモナドにおけるこの特定の鏡面にもっとも深い視線を投げかけてきたのは、ナオミ・クライン(Naomi Klein)だ。最近のエドワード・サイード記念講演「奴らは溺れさせておけ:温暖化する世界における他者化の暴力(Let Them Drown: The Violence of Othering in a Warming World)」[中野真紀子・関房江訳『地球が燃えている』大月書店、2020年に収録]のなかでクラインは、強制移住と望郷というパレスチナ人の経験が、温暖化する世界における普遍的な経験になりつつあるのではないかと示唆している。
根底から変貌してしまった故郷の地――もはや存在すらしないかもしれない故郷――を熱望するという状態は、急速に、そして悲劇的な仕方でグローバル化しつつあるように思われる。[……]もし私たちが根本的な変化を要求しないならば、私たちは、世界中で人々がもはや存在しない故郷を探し求めるような未来へと向かうことになる。
何百万もの人々が、パレスチナで作られた軸線に沿って移動しなければならなくなるだろう。砂漠が現れ、暑熱が、炎が、煙が、瓦礫が、そして溺死がやってくるだろう。まずはじめに大勢の漁師たち、労働者たち、小農たち、露店商たち、そして家のなかで働く女性たちのもとに。そして温暖化が止むことなく進行したならば、ほとんどすべての人々のもとに。かれらはボートの甲板によじ登るが、そのボートは海岸線のあいだをぐるぐると行ったり来たりすることしかできない。なぜなら、上陸することができる確固とした陸地はもはや存在しないからだ――小説『船』のなかで描かれているように。
パレスチナと気候変動との関係は、しかしながら、単なるひとつのアレゴリーやアナロジーという以上のものだ。化石燃料は、そもそもの初発から、パレスチナの破局と切っても切り離せないものだったのだ。

1839年、イギリス帝国とエジプト総督ムハンマド・アリー(Muhammed Ali)――当時、今日のシリア、レバノン、パレスチナを支配していた――とのあいだの緊張が頂点をむかえるなか、中東地域に戦争のドラムが鳴り響いた。自らを恃み、意志が強く野心的な総督は、綿を中心に国内の製造業の基盤を確立しようとしていたが、それは折りしも英国の綿産業が最初の過剰生産の危機に落ち込んでいるタイミングだった。英国は、ちょうどオスマン帝国とすばらしく有利な自由貿易協定を結んだばかりであり、そこに他の理由も重なって、アリーの領地を元のオスマン帝国領に返還させようとした。しかしながら1839年の夏、アリーの軍隊は今日の東トルコに侵入し、イスタンブールのとば口に立ったも同然の状態となった。ロンドンはそこで、もしエジプト人があと少しでも前進するならば、自分たちの軍事勢力の手綱が完全に解かれるだろうと告げ知らせた。「承知されたい」とアレクサンドリアの総領事は総督に警告を発した。「イングランドには汝を粉微塵に帰するだけの力があるのだ」。
「我々は一度に、急速に、そして手際よく襲撃を行わなければならない。そうすれば間違いなく軍事面での大成功を収め、エジプトおよびシリアにおけるマフメド・アリー(Mehmed Ali)の力の薄弱さを示すことができるだろう。」とイギリスの在イスタンブール大使であるポンソンビー卿(Lord Ponsonby)は説明した。「〈アラブ・ナショナリティ〉と愚かしくも呼ばれているぐらぐらする建造物もすべて、崩れ去って砕片に変わるだろう」。
戦闘の鍵となる兵器が、折りしも帝国の兵器庫に追加されたばかりだった――蒸気船である。それは石炭を動力としていた。エネルギー源がローカルな天候や地形から切り離されているため、波や風の状況にかかわりなく、司令官が望んだ場所に船の舵を取れるという戦略的な有利さが、イギリス帝国側にはあった。だが、1840年以前には、蒸気船が主だった戦争の現場で試されたことは一度もなかった。いまやロンドンはその本気を証明することを決心した――港湾の町を砲撃し、選ばれた場所に海兵隊を上陸させ、内陸の盟軍に武器を運び、アリーをレヴァント[東地中海沿岸地方]から一掃することを目的に、もっとも優れた戦闘艦が集められることになった。1840年9月初頭、英国はエジプトに対して宣戦し、海軍をレバノン湾へと差し向けた。その作戦の司令官であるチャールズ・ネイピア(Charles Napier)は、すぐさまロンドンに返報を送った。「蒸気は我々に大いなる優越性を与えてくれますし、私たちは奴ら[敵の隊]を追いやりつづけることでしょう」。
決定的な戦闘は、パレスチナの港町であるアッカー(Akka)で起こった。エジプト人たちは、かつての十字軍都市の城壁を修理し、塁壁に重砲を装備したうえでそこに何千人もの兵士を駐屯させており、レヴァントでそれまでのところ最も堅牢な要塞ができあがっていた。そこは同時に主要な兵站所でもあり、膨大な量の弾薬を備蓄していた。11月1日、凪のために同じくネイピア指揮下にある十七の帆船が出航できないなか、四隻の蒸気船からなる艦隊がアッカーに到着した。アラブ人たちが降伏の呼びかけを拒絶すると、第一陣が町への砲撃を開始し、防御を弱体化させていった。アラブ人たちも撃ち返したが、同時代の報告が強調つきで述べているように、「常時その位置を変える蒸気船からしてみれば、 それはまったく無害だった」。残りの英国の艦隊が到着したのは次の日の晩のことだった。11月3日には、アッカーの防壁のまえにすべての船が整列したが、蒸気船はその可動性を最大限に活用するべく、隊列の中央に位置取っていた。大規模な砲撃が2時に開始され、それは一度も止むことなく二時間半にわたって続けられた。
それから、耳を聾するような爆発音があたり一帯を切り裂いた。「恐ろしい破裂音が、襲撃の喧騒のはるか上方から聞こえてきた。それからすぐ、きわめておぞましい休止が続いた」という描写が、この出来事に関する多くの記述のひとつに見て取れる。「両陣営の砲撃は突如として中断され、その後の数分間というもの、この恐怖に満ちた沈黙を破るものといえば、ごろごろと遠雷のような音をくり返すやまびこや、ときおり崩落する壊れかけた建物の他には、なにもなかった」。アッカーの内側からの証人として、ロバート・バーフォード(Robert Burford)は次のように書いている。「炎と煙のかたまりが、火山の噴火のように突如として天に立ち昇り、その力によって巻き上げられたあらゆる種類の物質が、すぐさま雨と降り注いだ。 煙は巨大な黒いドームのようにしばらくのあいだ留まりつづけ、なにもかもを見えなくしていた」。海軍に従軍していた戦争記録者W・P・ハンター(W.P.Hunter)は、石や瓦礫が自らのボートの甲板に落ちてきた様子を詳しく描いているが、その際に画家・詩人のヘンリー・フュースリー(Henry Fuseli)の『大洪水の幻視(Vision of the Deluge)』 の一節――「厚みをました空が/黒い天井のようにかかった」――を引用することで、大地を揺るがすほどの爆発の規模を強調している。
蒸気船のひとつから放たれた砲弾が、アッカー最大の火薬庫を直撃していたのだ。指揮官たちの交信によれば、かれらは火薬庫の位置を意識し、それを標的にしていたらしい。この爆発の衝撃によって戦闘は終わりを迎えた。
「二つの連隊がまるごと殲滅された」と、あるロンドン向けの報告書には書かれている。「そして周囲6万平方ヤードのエリア内のあらゆる生命体が、その命を断たれた。人命の損失は、1200名から2000名まで、さまざまに推定されている」。英国の兵士たちが11月4日にアッカーに入ったとき、同時代の記述が詳細に記しているように、かれらは完全なる荒廃によって迎えられた。
弾薬庫の爆発によって黒焦げになり、大砲の砲撃によってきわめて恐ろしい仕方でばらばらにされた男たち、女たち、そして子供たちの死体が、そこらじゅうに転がっていた。家屋や要塞の瓦礫のなかに、なかば埋もれた状態で。女性たちは夫の亡骸を探し、子供たちは父親の亡骸を探していた。
妻への手紙のなかでネイピアは、居心地の悪さにとどまらずもしかすると痛烈な罪悪感でさえあるものを表明している。「私はエイカー(Acre)に上陸し自分たちが引き起こした惨事を目にしたが、そこで目撃した光景を私の記憶から消し去ることは二度とできないだろうし、いまでさえ、そのことを考えただけでほとんど身体が震え出すほどだ」。何百もの死者、および瀕死の人々が崩れた建物のなかに不揃いなまま横たわっており、「砂浜は半マイルに渡って、どちらを見ても死体がばらばらと並んでいた」。数日が過ぎると、遺体は「周囲の空気を臭気で汚染し、それは本当に身の毛がよだつほどだった」。英雄的な著書『シリアでの戦争(War in Syria)』での公式の説明においてさえ、ネイピアは次のように認めている。「ほとんど完全に粉々になったこの呪われた町のあらゆる場所で、無惨にも病み傷ついた哀れな人々を目にすることほど、ひとに強い衝撃を与えるものはない」。蒸気船のひとつに乗っていた海軍少尉候補生は、いくつもの手や腕やつま先が瓦礫から突き出ていた様子を書き記している。
イギリス帝国がその優越的な兵器を地球全体の戦争劇場へと配備していく新時代が画されるなかで、蒸気船はいかにも効率よくアッカーを叩き潰したことで称賛をうけた。蒸気船は「戦闘行為のあいだ継続的にその位置を移し、攻撃するうえでもっとも効果的な地点を見つけるやいなや、銃弾や砲弾を撃ち込んだ」とある報告では書かれ、こう続けられる。「四つの蒸気船のいずれからも、たった一人の死者や負傷者すら出なかったことは、特段の注目に値する」。しかし、男たちが無傷で戦闘をくぐり抜けたにしても、もうひとつの資源はほとんど使い果たされてしまっていた――燃料である。戦闘が終わったあと、一日分以上の補給を搭載していた蒸気船は一隻たりともなかった。町が粉々に爆破されるなかで、事実上すべての石炭が燃やされてしまっていたからだ。
アッカーの陥落は戦争の結末をさだめ、さらにその結果として、イギリスと中東との関係の行く末まで一撃のもとに決定した。エジプト軍はばらばらに撤退し、アレクサンドリアまで移動した蒸気船の艦隊がアッカーでの興行の再演をちらつかせたことで、ムハンマド・アリーはイスタンブールとロンドンのまえに降伏した。イギリスとオスマン帝国のあいだの自由貿易協定は、ほどなくして中東の全域に拡張され、エジプトの綿産業は崩壊した。
パレスチナの土地において戦争の後でなにが起こったのかといえば、ユダヤ人入植地の建設をイギリス帝国が協力的に行うようになった。ポンソンビー宛ての一連の手紙のなかで、外務官パルマーストン卿(Lord Palmerston)はアッカーの陥落のことで大使に祝辞をおくり、「そうしたユダヤ人たちのために、できることはなんでもする」機会を逃さないよう指導している。パルマーストンの主張によれば、オスマン帝国のスルタンには、
ユダヤ人たちが帰還してパレスチナで土地を購入するためのあらゆる激励、およびあらゆる便益を与えさせなければならない。もし不服申立ての経路として我々の領事および大使を活用することが可能になれば、すなわちいわば我々の保護のうちに実質的に収まったならば、かれらは相当な人数でもって帰ってきて、多くの富をもたらすことになるはずだ。
こうした考え方は、半世紀以上のちにシオニズムへと結晶化することになるだろう。

イギリス帝国がパレスチナを占領し、「ユダヤ人の民族郷土」というビジョンの実現に取りかかった頃、最先端の化石燃料はもはや石炭ではなかった。それは石油だった。
石油の湧出が約束された埋蔵地が、すでにペルシャ湾に隣接する国々において特定されており、はるばるイラクから西岸北部とジャリール(ガリラヤ)を通ってハイファーの精油所にまで原油を運ぶパイプラインが、委任統治領における中心的な産業プロジェクトだった。1936年4月(くしくもガッサーン・カナファーニーがアッカーの町に生を受けたのと同じ月だ)、パレスチナ人たちがイギリスによる占領とシオニストによる入植に対して大規模な蜂起に立ち上がったとき、作戦の多くはパイプラインをめぐって生起した。反乱者たちはほとんど毎晩のように、さまざまな場所でパイプラインを切断した。かれらはそれを爆弾で吹き飛ばし、火をつけて炎上させ、近距離からの銃弾で穴をあけた。埋められている地帯にそってパイプラインを掘り返し、破裂させた。かれらはそのようにして委任統治政府から主たる収入源およびエネルギー源を奪い取った。それに対して、委任統治政府はどのように反応したのだろうか?
ブルネル大学の軍事史研究者であるマシュー・ヒューズ(Matthew Hughes)は最近になって、イギリス帝国とシオニズムのアーカイブから、いくつかの暴露的な新事実を提示している。絶え間ないストライキ、ボイコット、ゲリラ戦闘、サボタージュからなる二年間のあとで、一般には反乱を鎮圧するため、個別にはパイプラインを防衛するために、委任統治政府は1938年、特殊夜間部隊(Special Night Squads)を立ち上げた。もっとも汚い仕事をさせる目的で、ユダヤ人入植地からも戦闘員を入隊させた。指揮を執ったのは、シオニズム事業の狂信的な支援者オード・ウィンゲート大尉(Orde Wingate)だった。ウィンゲートは新旧の反乱潰しの方法を導入したが、そこには「十分の一刑」も含まれていた。小銃の生産や諜報活動に失敗すると、その罰として男性の村人の八人に一人、ないし十人に一人を殺害するのだ。ジェニーンとハイファーのあいだの丘陵に延びるパイプラインに沿って、ウィンゲートはまた別の慣行も打ち立てた。器物損壊の攻撃が起こると、特殊夜間部隊は近隣の村からパレスチナ人のすべての男性を招集し、彼らに口を開けるよう命じて、パイプラインから漏れた石油が染み込んだ土や砂を、そこへ押し込むことになっていた。 嘔吐するまで押し込みつづけた。
やり口は多岐にわたっていた。ヒューズによって発見された証言のひとつによれば、
ウィンゲートはパイプラインのまえにアラブ人たちを整列させ、パイプラインに火が放たれたあとで地面の表面に形成された油層で顔を洗うように強要した。その油層は、小石や泥の混じった燃える石油からなっており、アラブ人たちが命令に従うことに躊躇するようなときにはいつでも、兵士たちがウィンゲートの指示が実行されるのを見届けることになった。
別の証言によれば、
ウィンゲートは「よし、このなんとかいう奴らに分からせてやろう」と言った。それで私たちは村の男たち全員を連れ出した。ああ、外では……石油が燃えてしまった場所では、黒く燃えた油の大きなプールができている。私たちは連れ出した男たちを全員、このプールのそばに立たせた。それから私たちは腕や脚をつかんで、やつらをみなそのなかに投げ込む。
そこにいるかれらの姿を見てみよう。サンバルの写真では生き生きとしていたパレスチナの村人たちが、一列に並ばされ、生き残れるかどうかも分からず、反乱者たちに同情的ではあれ直前のサボタージュについては何も知らないまま、イギリス人とシオニストの兵士たちによって体内に原油を注入される姿を。ウィンゲートは、こうした手口がパイプラインに対する「テロ」を終結させたのだと自慢していた。ヒューズの議論によれば、そうした手口は、その後すぐにハガナーの中核を形成することになる中隊の兵士たちに、受け継がれた。そのなかにはイガル・アロン(Yigal Allon)やモシェ・ダヤン(Moshe Dayan)といった著名な将軍たちも含まれる。ヒューズはそのことを、『大英帝国・連邦諸国史ジャーナル (Journal of Imperial and Commonwealth History)』の記事に書いている。「イギリス人たちは、アラブの反乱への対処において鋼鉄の刃物を使うことをユダヤ人に教えた」。反乱が1939年に鎮火されたあと、パレスチナ人たちの武装は解かれ、その運動は解体した。破局への道は整えられた。
そして私たちは、イスラエル国家がいかにアメリカの中東支配に貢献し、いかに同国の石油へのアクセスを容易にしてきたのかについては、まだ触れていない。パレスチナにおける化石燃料経済の歴史は、これから書かれなければならない。アッカーにおける蒸気の力との最初の出会いから、降雨量の減少、干ばつ、海面上昇、塩水の貫入、そして暴風雨にいたるまで。

パレスチナという眺望台に立てば、資本主義近代の真実の姿――人間以外のたいていの生命体にとっては周知のものだ――を、私たち人間もまた、見晴らすことができる。資本主義近代とは、クソいかれた〈ナクバ〉が次から次へと繰り返されることに他ならないのだ。

マフムード・ダルウィーシュの詩「川が渇きで死ぬ(A river dies of thirst)」を読み直してみよう。
ここには川があった
それはふたつの岸辺を持ち
天なる母が雲からの滴で養った
ゆっくりと動く小さな川
山の頂きから下りてきて
愛らしく生気に満ちた客人のように村々や野営地を訪ねては
夾竹桃や棗椰子の樹々を谷にもたらす(…)
あるとき川は英雄のように歌い
別のときには恋人のように歌った
それはふたつの岸辺を持つ川で
天なる母が雲からの滴で養っていた
だがかれらが母親を拐かすと
川は水を失ってゆき
ゆっくりと、渇いて死んだ。
この詩の軸となる単語、そしてそこにおいてパレスチナの破局が気候の破局に光を投げかけている単語は、言うまでもなく、「拐かす」という言葉だ。

〈アルド〉[土地]
だが土地はまだそこにある。人々もまだそこにいる。根絶されてしまったわけではない。「私たちはここにいる」とバドルの『ファーカハーニー広場を見下ろすバルコニー』のなかのある声が叫ぶ。「私たちはまだここにいる! 世界はまだ終わってしまったわけではない!」。パレスチナ人たちが終末を拒否する方法は、もっとも原始的なレベルで見れば、生き延びることだ。そうした試みで成功を収めることは、それ自体が敵の牙から小さな勝利を掠めとることにほかならない。このことはもちろん、パレスチナ人の〈ソムード〉[忍耐、不服従]として語られているものの第一原則であり、アブールハワーの『空と水のあいだの青色』のなかで見事に表現されている。
いまやそこにあるのは、抵抗の恐ろしい高貴さに対する母親たちの嘆き、そして満ち潮によってすぐさま洗い流されてしまうに違いない血が染み込んだ砂だけだった。「アッラーフ・アクバル! アッラーフ・アクバル!」と彼らは叫び、果てしない敗北という倦怠のなかへ落ち込んでいく。負傷者の世話をし、埋葬のために死者を清め、子供たちを慰め、歩いて家に帰り、ユダヤ人たちが地獄に落ちるよう呪いをかけ、夕食の支度をし、そして最後に、夜のなかに住みつく方法を見つけ出す。
アッカーであれアラーキーブであれ、いまだ故郷の内側にいるパレスチナ人たちにとって〈ソムード〉とは、単に生き延びることだけではなく、なんとしてでもその場から動かないこと、それによって敵がもっとも望んでいる勝利を否定することでもある。「穏やかな丘」を意味するナカブ(ネゲブ)砂漠にあるベドウィンの村アラーキーブでは、〈ソムード〉は感嘆すべき不条理さとでもいうべき新たな段階に達している。この稿を書いている時点で、住人たちは九十九回にわたって村を再建してきた。そして、ブルドーザーとイスラエル国家の武装兵士たちによるこの村の更地化が、まさに百回目を数えたのだ。アラーキーブはふたたび再建されるだろう。シオニストによる永続的な攻撃という条件のもとにあっては、ただ生存することが実質的に抵抗することであり、土地に住まいながらそうすることはもっとも頑強な対抗のかたちなのだ。
ここに私たちは残ろう、お前の胸には壁が立ち、
お前の喉のなかには
鋭利なガラスの細片と、仙人掌のトゲが刺さり、
お前の両目には
燃えさかる嵐 (…)
私たちのイチジクとオリーブの木陰を守り、
パン生地の酵母のようにそだつ思想を植え付けよう。 (…)
焼きつく地獄が私たちの心臓で燃え猛る、
という一節が、ジャリール(ガリラヤ)のコミュニスト詩人タウフィーク・ザッヤード(Tawfiq Zayyad)の有名な詩「不可能なこと(The impossible)」のなかにある。

私たちの希望の源泉はいまや、世界的な「気候ソムード」に他ならない、とクラインはサイード講演で提起している。パレスチナ人たちはもう何十年にもわたって、抵抗の方法を研ぎ澄ませてきた。だが、かれらから学び、それを急速に温暖化しつつある世界へと導入するということは、何を意味しているのだろう? そんなことはそもそも可能なのだろうか? それが明らかになるためには、いくつかの大いなる患難が必要になるだろう。

パレスチナの文学には、土地の美しさへの讃歌がすみずみにまで行き渡っている。短いがいまだ並ぶもののない研究書『石に声を与える:パレスチナ文学における場所とアイデンティティ(Giving Voice to Stones: Place and Identity in Palestinian Literature)』――まさにディープ・エコロジーのスローガンにもなりうる題名だ――のなかで、バーバラ・マッキーン・パーメンター(Barbara McKean Parmenter)は、作家たちが1948年以前には土地への愛着を言語化することに特段の関心を払っていなかったことを明らかにした。なぜならそれは実際的な生活に関わる事柄で、村で毎日のように実行されていたからであり、呼吸している空気は劇の題材にならないからだ。しかし破局のあとには、それこそがもっとも切迫した課題となった。それゆえにこそ、オリーブの樹々(土のなかに深く根を張り、まれな雨にもかかわらず生き延び、限られた区画でも育つことができ、何百年もの寿命に達する)や岩石(揺るぎなく、なにがあっても動じない)、そしてパレスチナの風景のその他の特色について、いたるところで強迫的に語られることになる。それらはいまや美と徳が具現化したものであり、人々と土地のあいだの破りがたい絆を証明するものとなったのだ。その一方で、初期のシオニストの書き手たちは、土着の農民たちの装わない土地との親交に対して、嫉妬の念を表明していた。それはまた反対に、後々まで持続するパレスチナ側の確信――あとからやって来る植民者たちは、自分たちほど親密に土地を知ることは決してないだろう――へと翻訳されることになる。
この点において、自然はそれ自体が自由のための基盤となる。「作家たちは」とパーメンターは述べる。「一般には自然に、そして個別にはパレスチナの土地に、自分たちの最後の、そして最強の同盟軍としての助力を求めている」。ライラ・アルーシュ(Layla Allush)の声を聞いてみよう。彼女は「親しみの道(The Path of Affection)」という詩のなかで、生まれ育ったアル=クドス(エルサレム)から新しくハイファーまで通った高速道路ぞいの旅路について、報告している。
最近の暦という咽喉から引き出された驚くような道路のかたわらで、
樹々は私に微笑みかけた、アラブらしい親しみで。
大地には私の父がうけた傷への詫び言が埋まっていた (…)
舌先[言語]の変化にもかかわらず何もかもがアラブらしい、
トラックや、自動車や、車のライトにもかかわらず、
これらすべての、緑と青の混じった標識にもかかわらず。
ポプラの樹々も、そして先祖たちの謹厳な果樹たちもすべて
誓って言うが、アラブらしい親しみで私に微笑みかけていた。
消し去られ整備されたすべてのものや、この「モダン」な音響にもかかわらず、
旅行者を平手打ちするあらゆるプロパガンダにもかかわらず、
光とテクノロジーの海にもかかわらず(…)
大地はアラブらしい親しみで歌いつづけていた、
パレスチナ人の特殊な経験がグローバル化してゆくなかで、同様の救済の希望を託すことができるような類似の層が、生物圏の深い場所や、気候の変化の奥底に存在しているのだろうか? アルーシュの詩を国境横断的なモードで書き直すことは、可能なのだろうか? 「トラックや自動車にもかかわらず…… 光とテクノロジーの海にもかかわらず」。あるいは、この破局は大地すらも沈黙させ、微笑む樹々を一本残らず隔絶してしまうところにまで行き着くのだろうか? 西岸を訪れた者ならだれでも、アルーシュの印象の真正さを確認することができる。植民者たちを収容する家屋は、空から落ちてきたかのように見える(プレハブの建物として、文字通りそうであることもしばしばだ)。アメリカの郊外用のテンプレートどおりに配置され、土地を蹂躙する要塞として建設され、丘陵に切り込みをいれるユダヤ人専用道路によって繋がれ、人工的な画一さをもった入植地は、その圧倒的な重量ゆえに、どういうわけかまったく非現実的に映る。
それに対してパレスチナ人の村々は、谷に咲いている花々がそうであるのと同じように、詳細な全体計画というものなしに生長したものだ。 それゆえ、〈セルビス〉[現地の乗合バス。黄色のミニバン]の窓から入植の様子を眺めるときにはいつも、かれらもいつかは去るだろう、表皮は取り除かれるだろう、と想像せずにはいられない。入植者による土地の鷲掴みはその後の植民地化の引き金になるが――ここは俺たちの土地だと証明してやろう! キルヤト・アルバにまた新しく百世帯!――、それはそれ自体が異質かつ短命なプロジェクトなのだという感覚を強める結果にしかならない。表向きは前進しているように見えても、究極的にはみずからを打ち負かしているのだ。
占領のあらゆる部分から、はかなさの感覚がにじみ出ている。1967年の占領地[西岸、東エルサレム]に足を踏み入れれば、「こんなふうに物事が進みつづけるはずがない」(ベンヤミンの言葉)という感覚なしには、一日たりとも、一分たりとも時間を過ごすことはできない。にもかかわらず、終わりを視界のうちに捉えることはできそうもない。検問所が人々の生を永遠に破壊しつづけることは不可能だが、そうした破壊はたしかに明日も続くだろう。そしてその次の日も。こうしたありえなさ、一時性と不可避性とのむすびつき、杜撰さと絶対的な慣性とのむすびつきこそが、シオニズム事業のもとでの生をかくも拷問的なものにしているのだ。化石燃料経済に関しても、私たちはそれが終焉を迎えることを確かなこととして知っている。物理的な自然によってすでに定められているからだ。だがさしあたり、新たな石炭火力発電所が、石油掘削装置が、パイプラインが、空港が、高速道路が、郊外のショッピングモールが、私たちの緑の惑星のうえに建てられつづけている。物事がこんなふうに進みつづけることは不可能だ。そしてそのように進み続けている。一人の人間に自分自身を爆破しようと思わせる経験、〈ソムード〉の文化に刺激を与える経験とは、このようなものなのだ。

私が初めてのパレスチナ旅行で1996年から1997年にかけてバイト・ラフム(ベツレヘム)を訪れたとき、 そこにはまだ、目を休ませることのできる緑の丘がひとつ残っていた。リフターの遺跡からヤフーダー砂漠まで、みたところ途切れなく広がる都市圏の粉塵、灰色、白色に挟み込まれるようにして。ジャバル・アブー・グナイムの丘は、北側に威容ある頂をもっていた。それは南の谷へとゆるやかに下ってゆき、谷は何千本もの樹々で覆われていた。その森は、遠目にはそこだけ閉ざされた秘密めいた場所に見えた。周辺の村から来た羊飼いたちは、羊を放牧し、オリーブの樹々を育てるためにその丘を使っていた。誰も覚えていないほど、はるかな昔から。ジャバル・アブー・グナイムの頂には、六世紀のビザンツ修道院の遺跡があった。芝地にモザイク石が散らばっていて、その模様は失われてはふたたび再生されてきた。
私が1999年に戻って来たとき、ブルドーザーが森のなかにつづら折りの道を切り開いてしまっていた。ジャバル・アブー・グナイムは、「壁の山」ないし「柵」を意味するハル・ホマへと作り変えられている最中だったのだ。それは 25000人のユダヤ人のための植民地で――もちろん他の人々がそこで暮らすことは許されていなかった――、よくある単色の様式(砂白色)でデザインされ、分譲マンションが要塞も兼ねていた。春のある日、私はバイト・ラフムの別の側に位置する植民地テコア(Tekoa)を訪れた。ブルース・ブリルという名前のアメリカ人入植者が案内してくれた。彼は眼が青く、すらりとしてカリスマ性があり、自信に満ち溢れていた。彼は土地を解放するためにそこにいた。「ユダヤ・サマリア地区」[イスラエルが行政権をもつヨルダン川西岸地区(エリアC)のイスラエル側の呼称]のただの一平方インチたりとも、これまでアラブ人から押収されたことはなかったと言うのだ。タクーア(Teqoa)と呼ばれるもともとの村に住んでいた人々がブリルとその仲間たちに危害を加えようとしたため、軍隊が住民たちに向けてコンクリートの要塞を築いたところだった。ブリルのズボンのしたには、ピストルの輪郭がはっきりと見て取れた。
その日の後刻、私がジャバル・アブー・グナイムに面したバイト・ラフムのアパートメントに戻ると、太陽が谷のうえにかかっていた。私は棚田と果樹園のなかを歩いて下りていって、つづら折りの道に着いた。道をわたり、森に入った。丘の頂で、私はモザイク石を探し、見つけた一掴みの石を急いでポケットに押し込んだ。一週間後には、その場所はコンクリート舗装で覆われることになっていたからだ。私はその小さな石たち(縁はギザギザで、表面は色あせている)を、両親の家の戸棚に飾っている。ハル・ホマの壁がバイト・ラフムを攻撃的ににらみつけている今この瞬間も、その石たちは宙吊りになったままだ。

「生態学の教育を受けることの罰のひとつは、傷にみちた世界のなかで一人きりで生きるということだ」とアルド・レオポルド(Aldo Leopold)が日誌に書き込んだことはよく知られている。「学んでいない人々にとって、土地へのダメージの大半はきわめて目につきづらいものなのだ」。パレスチナでは、生態学の学位を持っていなくてもそうした傷を目にすることができる。そして、自分だけがそのなかに生きているわけでもない。土地のなかの傷はまた、つねに人々のなかの傷でもある。この二重性を誰よりも雄弁に捉えたのが、『パレスチナ人は歩く:消えゆく風景についてのノート(Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape)』を、そして同じくらいに感動的だがそれほど評価されていない『時の亀裂:オスマン帝国に住んでいた伯父との旅(A Rift in Time: Travels with my Ottoman Uncle)』を書いたラジャー・シャハーダ(Raja Shehadeh)だ。 どちらの本も、いたるところ刺し傷にみちた土地のガイドブックになっている。一つ目の著書で、彼は状況をこんなふうに描き出している。
私たちのパレスチナの世界が収縮するにつれて、イスラエルの世界が拡大し、より多くの入植地が建設される。涸れ川や岩壁が永久に破壊され、丘は平らに均される。変貌させられた土地のかつての姿は、多くのパレスチナ人にとって、二度と見ることができないだろう。たったの三十年間のあいだに、[西岸の]5900平方メートルにすぎない領域に、50万ちかくのユダヤ人たちが入植した。それほど多くの人口の生活を維持するために必要なインフラの機構――何世紀も手つかずのままだった丘陵に都市をまるごと建設するために、莫大な量のコンクリートが注ぎ込まれた――によって、どれほどの損害が土地にもたらされたのかは、正確に測ることすら難しい(……)。今日の入植者たちが後世の人々に残すものは、愛しているとみずから主張していたはずの土地を破壊した醜い構造物のほかに、何があるのだろうか?
しかしながら、ひとにそうした傷を見えなくするための効果的な条件が存在する――シオニストであることだ。『パレスチナ人が歩く』の鍵となる対話において、彼は細流が底を流れる緑の谷を下っていく途中、ラーマッラーの周囲の丘で、ある入植者と行き会う。その入植者――言うまでもなく、銃で武装している――は、この風光明媚な谷を守ることができるのは自分やその仲間なのだと主張する。自分たちはここを自然保護区として宣言したのだ、と。そこでシャハーダは度を失う。
ここが本当の意味での自然公園だったころ、この辺りがどんなふうだったか説明させてくれ。あなたたちがやって来て、なにもかも滅茶苦茶にしてしまうまえ。新築のビルなんてひとつも見えなかった、車の音なんてまったく聞こえなかった。目にするものといえば、段丘を駆け上がっていく鹿だけ。野生のウサギや、狐や、ジャッカルや、絨毯のように敷かれた花々だけ。そのときこそ、ここは公園だった。何百年にもわたって、多かれ少なかれ同じ状態に保たれて。
それに対して、入植者はこう言い返す。
「何百年も手つかずでいられるものなんて何もない。進歩は避けられないんだよ」。(…)
「お前たちが俺たちの丘を掘り返したって、何にもならなかった」。
「道路を造ることは進歩であって、破壊じゃない」。
私たちが住む資本主義の中心地にあっても、こうした入植者的メンタリティの持ち主に出会うことは、なんとありふれたことだろう。かれらは自分たちが進歩と呼ぶものの避けがたさを、道路の必要性を、その土地にあるものすべてが当然ながら自分たちのものであることを、信じ込んでいる。自分たちは資格を持った人々、所有者なのだと。
傷ついた生物圏に対して心痛をおぼえない人間はだれであれ、そのなかで植民地主義者とおなじ行動をとる。もちろん、そうした無頓着さや自己陶酔は、経済的な富裕さと密接な関係にある。資本主義の世界経済が生んだ犠牲区域において、人々は傷をみずからの身体のうちに持ちはこぶ。もっとも高級なショッピングモールにも深い刺し傷が刻まれていることに気づくためには、政治的エコロジーの教育が必要であり、おそらくその作業はまったく一人で行わなければならない。生物圏に刻まれた傷に近づこうとすることによってのみ、ひとはパレスチナ人的な感性――あなたたちがやって来て、何もかも滅茶苦茶にしてしまうまえ。今日の入植者たちは、後世の人たちに何を残すのだろう?――をきちんと育むことができるのだ。

パレスチナ人とおなじポジションを取るということは、究極的には、自然をみずからの最後で最大の同盟者として選ぶということだ。それは、レオポルドすら霞ませてしまうような切迫性をもった土地倫理[生態系にまで倫理の対象を拡大することを説くレオポルドの用語]だ。緑の糸、それが1948年以後の最初の勃興期からアブールハワーやシャハーダの世代に至るまで、パレスチナ文学のなかを縦断している。「この土地はふたたび立ち上がるだろう」――人々ではなく、〈アル=アルド〉[土地]が――というリフレインが、『空と水のあいだの青色』のなかで歌われている。『パレスチナ人は歩く』のなかで、シャハーダは「土地のパースペクティブ」を採用し、それがシオニズムによる植民地のような人工の構築物の丈を縮減させることを発見している。そうした構築物はもはや、
ほとんど何の意味もない。道路は丘に切り傷をつけるが、時とともに傷は癒え、吸収されて、体内に取り込まれる。家々を建てるために岩石が集められるが、それらは瓦解して土地に戻る。かつての姿が、いかに大きく強大なものであったとしても。記念碑的な十字軍の城が、荒れ果てた状態で土地に点在している。この地域に広がっていた他の帝国が残した遺跡と同じように。帝国や征服者はやって来ては去っていくが、土地は残る。
『時の亀裂』のなかで、特別夜間部隊が男たちに石油を食べさせた村々には気がつかないまま、ジャリールのターブール山に登るとき、シャハーダは、この山がもっとも強大な占領勢力よりもしっかりとした根を持っており、かれらよりも長く生き延びるだろうという感覚をおぼえる。レオポルドはそのことを、「山になったように考える」と呼んだ。そうした思考が――政治未満のエコロジーとは異なり――つねに権力の問題と結びついているパレスチナにおいて、それもまた〈ソムード〉の名において行われる。私たちが温暖化しつつある世界で生き延びようと思うならば、おそらくこれこそが真に必要なものなのだ。

〈ムカーワマ〉[抵抗]
だが、生き残り、その場を動かないことは、〈ソムード〉の第一の原則に過ぎない。第二の原則は、抵抗することだ。[普通、〈ソムード〉(原義は我慢・忍耐)という不服従の抵抗と〈ムカーワマ〉(原義は闘争、対抗)という反撃の抵抗とは、占領に対する二つの対をなす抵抗方法として位置づけられている。]
パレスチナは過剰に研究されている場所だと悪い意味でよく言われるが、まさしくパレスチナ側の信条に関連する研究文献において、ぽっかりと空いた空隙が存在する。それなくしては「パレスチナ紛争」などとっくに終わってしまっていただろうもの――武装解放闘争だ。 今日にいたるまで、1936~39年の大反乱を記録した年代記は、英語では一冊たりとも出版されていない。それが二十世紀で最大の反植民地主義蜂起のひとつ、史上最長のゼネラル・ストライキのひとつ、そしてその後のあらゆるパレスチナ解放闘争の原型へと発展したにもかかわらず。同じ年にスペインで起こった戦争についての、数えきれないほどの著作と比べてみればいい。いくらかなりとも包括的な形で第二次インティファーダを物語り分析している著書も、一冊もない。この千年紀でもっとも叙事的な大衆蜂起へと発展し、決定的な契機、転換点、実験、攻撃、大惨事が豊富に存在しているにもかかわらず。パレスチナ左派についての通史も、PFLPについてのモノグラフすら書かれていない。PFLPは、さまざまな弱点はあるけれども、ガザの戦場で、占領軍の監獄で、西岸の路上で今日まで重要な役割を果たしており、同時期の大抵のマルクス派の解放運動とは違って(例えば、学術・文化産業の対象となりおおせているブラック・パンサー党と比較してみればいい)現実の政治的な力として歩みを進めてきたという事実があるにもかかわらず。
あふれんばかりの著作という報酬を受けてきたのは、抵抗のひとつの側面に過ぎない――非暴力闘争という側面だ。あたかも、パレスチナの政治のなかで、それだけが持続的な注目に値する唯一の形態であるかのように。

第一次インティファーダ初期の生気に満ちた日々からこのかた、パレスチナの抵抗運動が、勝利は近いという幻想を抱いていたことはない。オプティミズムは、かれらの物の見方ではない。自分たちの面前に積み上げられた力がとてつもなく大きいこと、そして――現在のパワーバランスのもとでは――土地を解放する望みはほとんど存在していないことを完全に理解したうえで、抵抗運動は続けられている。では、抵抗することの利点は何なのだろうか? 「対立の残り火を燃やしつづけること」というハマースの言葉がある。それがいかに遠くにあれ、未来のいつかの時点で、より広範な歴史的プロセスによって敵との力関係が逆転するときまで――あるいは、「勝利のための必要条件が実体として現れるまで、問題を生かし」つづけること。『パレスチナ研究ジャーナル(Journal of Palestine Studies)』で公開されたインタビューにおいて、抵抗運動において第二の重要な武装勢力であるイスラーム聖戦の指導者ラマダーン・シャラフ(Ramadan Shallah)は、同様の戦術方針を詳細に説明している。目的は、「新たなパラメーター」が現れるまでイスラエルに軍事的圧力を加え続けることなのだと。 それがいつになるのかは、誰にも分からない。(これら二つのグループがイスラーム主義を掲げていることに胸のざわめきを覚える人は、次のことを特によく考えてほしい。つまり、かれら――とりわけハマース――が、ダーイシュ[イスラーム国]がガザで鎌首をもたげるのを、いかに目覚ましく防いでいるのかということを。)
まったく大真面目な話、短期的・中期的には楽観的どころか悲観的なものであるにしろ、抵抗運動は長い時間軸を見据えて塹壕を掘り進めている。残り火が燃やされつづけてこそ、圧力が維持されてこそ、パレスチナ人たちは突進の可能性を保持することができるのだ。もしその瞬間が訪れるならば、そのときに。これこそ、武装闘争もふくめて多様な形態で展開している今日のパレスチナ抵抗運動の全体的な精神的態度なのである。
武装闘争に首をつっこんだ数少ない研究のひとつ――厳密に人類学的な方法で特定の側面のみを探究しているとはいえ、第二次インティファーダの無視に対する申し分のない例外――が、ナースィル・アブーファルハ(Nasser Abufarha)による『人間爆弾の作り方:パレスチナの抵抗についての民族誌(The Making of a Human Bomb: An Ethnography of Palestinian Resistance)』だ。 ジェニーンにおける武装地下勢力へのインタビューを重ねたなかから、アブーファルハは次のように報告している。
パレスチナ人たちは、力の規模において不利であることは完全に意識しているが、かれらのあいだには、自分たちが最後には打ち勝つのだという驚くべき信念が存在している。ハサン(Hasan)もまたこうした信条を分かち持っている――「アル・マブニー・アラー・ハター・ファフワ・ハター(アラビア語の諺で、間違った土台のうえに建てられたものは、間違っている)。私たちはそれを未来の世代まで言い伝えるだろう」。
こうした精神的態度は、パレスチナの特定の派閥の私有財産ではない。むしろそれは、組織によるどのような装飾がまとわりついたとしても、抵抗運動というものそのものの真髄――無限なるものへの関与――なのだ。パレスチナの作家たちは、民族運動が誕生した当初からそのことを明確に言い表していた。「私がどこへ行こうとも、どのような空想にとらわれようとも、私は永久に、私の土地に向かって走りつづける。有刺鉄線によって千キロメートルもむこうに切り離されてしまった、私の土地へ。私は手榴弾を手に、そこへ走っていく」。小説『船』におけるメインのパレスチナ人キャラクターであるワーディー(Wadi)はそう語る。彼のさしあたりの第一目標は、アル=ハリール(ヘブロン)の郊外に小さな土地をもつことだ。堂々と誇りにみちて、さまざまな形の〈ソムード〉が互いに手をとりあって進んでいく。
人間性が狂気におちいってしまったら、そのたびに私はもう百本の樹を植えよう。(……)二三の銃や手榴弾は家のなかに隠しておいて、その代わりに樹を植え、絵を描き、生の美しさに身を捧げる子供たちを十人でも産もう――かれらもまた悲劇の一部になるだろうけれども。そこから、決定的な瞬間を近づけるための仕事を私はしよう。

気候変動の破局的な局面について書かれた近年のエッセイのなかでもっともよく読まれたもののひとつ『人新世のなかで死ぬことを学ぶ:ある文明の終わりについての省察 (Learning to Die in the Anthropocene: Reflections on the End of a Civilization)』においてロイ・スクラントンは、「私たちはもうダメだ。問うことができるのは、それがどれだけ早くやって来て、どれだけひどいものになるかだけだ」と主張している。それゆえに、私たちは死ぬことを学ばなければならない。個人としてではなく、集合体として。ひとつの文明として。私たちは闘ったり抵抗したりする必要はなく、そのかわりに物事の終わりについて観想し、それとともに生きなければならない(残されたわずかな時間のあいだ)。スクラントンは、気候変動に対するデモやその他の形での集合的な行為を、エネルギーの浪費として嘲笑している。ある箇所で彼は、これまで通りのビジネスという既得権を退けるためには暴力的な反乱が必要になるだろうと示唆している――「非暴力が力を持たない人々の美徳と見なされている真の理由は、力を持った人々が、みずからの生命や財産が脅かされるのを目にしたくないからだ」――が、そうした考えは宙づりにされたままであり、全体としての要点はタイトルにある通りだ。それを何と呼ぶにせよ、まったくもって非パレスチナ的なものであることだけはたしかだ。想像してみてほしい、例えば1946年にパレスチナ人たちが「私たちはもうダメだ。私たちはひとつの民族として死ぬことを学ばなければならない」と語る姿を。かれらは本当に歴史から消え去ってしまっていただろう。

全面的なペシミズムが、正反対のものへと転換する地点が存在する。「私がオプティミストなのは、私たちの目の前に、果たさなければならないマンモス級の仕事が存在しているからだ」とワーディーは言う。「仕事とは何かって? あらゆることだ。パレスチナ。未来。自由」。クリスチャンの実存主義者であるガブリエル・マルセルにならって、テリー・イーグルトンはこのことを「基盤的な希望」として理論化している。それは、敗北の莫大さと荒廃とを知ったうえで、それでも降伏することを拒み、いくらかの特定されざる未来が開けている可能性に賭ける、という希望の形式だ。絶望からのわずかな距離、それが、特定の願望や具体的な財産が綺麗さっぱり流されてしまった後に残るすべてだ。それこそ、イーグルトンが言うように「全面的な廃墟を生き延びるもの」なのだ。それゆえに、パレスチナの作家たちは以下のような文章を好んで書く。「瓦礫のなかを引っ掻き回して、私は光と新しい詩を探す」(ダルウィーシュ)。「〈ノー〉と言える権利に、私はまさしく自分の爪で、自分の歯で、しがみつこう。たとえそれで血が流れようとも」(ジャブラー)。「物事はつねにこんなふうであるわけではない。そう私は思っていた。世界にはいくらかの新鮮な空気がまだ残されているのだと」(バドル)。「おそらくいつの日か/川が叫ぶだろう/『起き上がり、ふたたび呼吸せよ』と」(ザッヤード)。「どういうわけか分からないが、私たちはこれらの丘の未来について希望を持ち続けている。地質学的な時間という長い視野にしがみついている友人さえいる」(シャハーダ)。それを基盤的な希望と呼ぶこともできるし、〈山になったように考える〉こととも、それどころかパレスチナの抵抗の地質学的なエートスと呼んでもいい。疑いないこと、それどころか自明ともいえることだが、私たちが温暖化する世界というタンクの内側で生き延び、生きてそこから出る方法がもしあるとするならば、それは――死ぬことではなく――闘うことを学ぶことによってであり、そうした種類の気候の〈ソムード〉を養い育てることによってだ。

パレスチナでは、真の災厄が達成されるのはこんな日だ。もはやガザと1948年の占領地との国境のしたに掘られるトンネルから、くぐもった音が聞こえてこない日。国境を越えてロケットを飛ばす訓練が行われなくなる日。石が入植者の車に飛び込まなくなる日。植民地のフェンスが破られなくなる日。火がついたタイヤが分離壁の見張り塔に転がっていかなくなる日。ひと月以上のハンガーストライキのあとで救命ルームに運ばれる囚人がいなくなる日。金曜日の祈りのあとの果樹園への行進が途絶える日。抗議者たちがみずからの身体をオリーブの樹々に結びつけなくなる日。〈男子〉と〈女子〉のあいだで、クーフィーエで包んだスリングショットが手渡されなくなる日――そんな日は、幸いなことにどうやらまだずっと遠くにある。
偽善的な道徳主義、勝者にしか手に入らない倫理的な自己満足に浸りながら、「我々は武装闘争を糾弾しなければならない」と要求してくる人々には、こう答えるべきだ。あなたはパレスチナ人に何を求めるのですか? かれらが地に倒れて沈黙のうちに死ぬことを望むのですか? 武装闘争とは、大目に見てあげる対象ではない――問題になっているのは、注意してほしいが、パレスチナだけではないからだ。そこには自分自身もまた挟み込まれている。武装闘争とは、他に呼吸する空気がまったくなくなったときの最後の酸素チューブなのだ。

西岸地区の北部、ナーブルスとトゥールカルムとジェニーンの三つの町に囲まれて、丘の上の入植地をいちども目にすることなく日々を送ることができる三角地帯が存在する。ここでは、オリーブの林が、ミントやタイムの茂みが、段丘が、集落が、細流が、波打つ土地を自分のものにしている。シオニズムの植民地主義も、この地にまで侵入してくることは決してできなかった。「孤立した」と形容されていた四つの入植地も、うまく保護することができなくなったという理由で2005年に退避させられた。まさしくここが、1936~39年の大反乱においてもっとも強力な根拠地となった場所だった。英国はこの地に「恐怖の三角地帯」、「テロルの三角地帯」といった洗礼名を与えた。というのも、どれほど力をかけて試みても、反乱者を鎮圧することも、これらの丘陵における事実上の自治をやめさせることも、できなかったからだ。そのなかには、PFLPのマイサルーン基地があり、のんびりとして豊潤な小農たちの村があった。その村ではいまやほとんど耄碌してしまったある老人に出会うこともできた。彼は1968年にイスラエルの警備隊に待伏せ攻撃を行ったあと、三十年以上を監獄のなかで過ごしていた。西岸において、私はここよりも〈パレスチナ〉を想像することが容易な場所、呼吸することが容易な場所を見つけ出すことはできなかった。

アラブ人でない人間からしても、ムハンマド・ダイフ(Mohammed Deif)のような人物には敬意を覚えないわけにはいかない。イッズッディーン・アル=カッサーム旅団(Izz ad-Din al-Qassam Brigades)――言うまでもなく、1936年の反乱のシンボルにちなんで名づけられた――の司令官である彼は、少なくとも六回以上のイスラエルのよる暗殺の試みを生き延びてきた。2002年、ガザ市の上空を旋回するアパッチ・ヘリコプターが、彼の乗っていた車を砲撃し、運転手を殺害した――だが彼自身は燃える車の残骸から生きて脱出した。2014年の戦争のあいだ、イスラエル国家は彼の妻、娘、そして赤子の息子を殺すことには成功したが、ダイフ自身は瓦礫のなかから救い出された。『五十一日間戦争:ガザの廃墟と抵抗(The 51 Day War: Ruin and Resistance in Gaza)』のなかでマックス・ブルーメンタール(Max Blumenthal)が他のひとにも口伝えせずにいられなくなるような称賛の調子で述べているように、ダイフは極度の秘密主義をみずからに課していた。決して公の場に姿を見せず、母親の葬式にすら出席しなかったし、ほとんどの時間を地下トンネルのネットワークのなかで過ごしていた。そのなかから彼は、民間人に対する自爆攻撃という方針を転換し、戦闘能力を育成することを画策した。それは――およそ考えうるかぎりもっとも困難な兵站の条件下にあって――中東でもっとも強力な軍隊に一撃を加えうるほどに有効なものとなった。だからこそ直近のガザ戦争の統計では、パレスチナ側の死傷者のおよそ70~80パーセントが民間人だったのに対して、イスラエル側の死傷者のちょうど93パーセントが兵士という結果になったのだ。あらゆる作戦のなかで大胆不敵さという点でもっとも衝撃的だったナハル・オズ軍事基地への襲撃――九人の戦闘員がトンネルのなかから現れ、要塞に突入して五人の兵士を殺害し、無傷でガザに退却した――のあと、ダイフは五年ぶりとなる声明を発し、パレスチナ側の〈テロとの戦争〉の諸原則を述べた。「犯罪的な敵は、民間人を攻撃して血を流させ、虐殺に関与し、住民たちの頭のてっぺんに家の屋根を崩落させているが、それに対して私たちは、民間人を攻撃することよりも、軍隊や検問所の兵士たちに立ち向かうことを優先させてきた」。
スーザン・アブールハワーは、『空と水のあいだの青色』を、この戦争についてのエピローグで締めくくっている。彼女はこう書く。「私は、これらのパレスチナの戦闘員たちに敬意を表したい。かれらはどうあがいても死が確約された領域に、自由という大義のただそれだけのために、みずから進んで足を踏み入れたのだ。かれらの勇気は、伝説となるに値する」。この最後の三文は、ベストセラー作家が書くにしてはいくらか大胆なものだが、それによってアブールハワーは、シオニズムのナラティブにいかなる歩み寄りも見せることなく何百万人もの西側の読者の心を動かしてきた。 そして、ダイフがその肩に背負っているのは、ガザの土だけにとどまらない。この世界における抵抗の力のイメージとして、ぴったりではないだろうか?――周縁的な区域や地下に押しやられ、生者たちの世界へのアクセスを否定され、不可視なままで、戦車やヘリコプターに蹂躙されるというイメージは。そして、それでも完全には根絶やしにすることができないということは。

こうしたことはいずれも、パレスチナ人がある種の抵抗ロボットであると示唆するものではない(あるいは、さらに言えば環境の天使だと)。かれらが抱えてきた喪失の巨大さを思えば、かれらが地面に倒れもせず、気を失うことも、羅針盤を失くすこともなく、つまらないことで言い争うことも、自らの個人的な利益を追求することもなかったとしたら、実際のところかれらは超自然的な存在だと言うべきだ。抵抗のバランスシートというものがあるとすれば、そこには我慢強さと崩壊との混淆が認められるはずだ。ディアスポラの難民キャンプにおいて、イスラエルのレバノン侵攻[1982年]は抵抗運動を根本的に打ち負かし、パレスチナ民族運動の元来の根拠地を等式のなかから消し去った。今日、こうしたキャンプは極度に抑圧的な場所となりうる。そこで第四・第五世代の若者たちの目の前にある主要な二つの選択肢は、地中海の「死のボート」か、なんらかのジハード主義セクトの狂気かであり、それらのいずれも、かれらを一インチたりとも故郷の地へ近づけることはない。
パレスチナ解放機構(PLO)は死後硬直の状態にある。民族和解は依然として、リップサービスの対象品でしかない。ファタハの指導部は、交渉という幻影を手放すことを拒否し、みずからの物質的な安楽をいかなる解放の戦略よりも特権的に優先しつづけ、パレスチナの歴史に類例をみないほどの恥辱にしがみついている。占領軍と手を結んだセキュリティ企業と化しているのだ。このこと、そしてパレスチナの人々が孤立した個々の断片へと分派してしまっていることは、シオニズム国家が1982年以来に成し遂げたもっとも大きな達成だと言ってよい。 国際的な状況も、極度に陰惨なものだ。測り知れない量の集団的エネルギーが費やされ使い果たされた二回のインティファーダのあとで、何十年にもわたって骨身を惜しまずに建設された政治的なインフラのうちで残っていたのは、ごくごくわずかなものだけだった。それゆえに、目下のところ西岸でくすぶっている疑似的なインティファーダは、なんとも方向の定まらないものとなっている。ガザは絶望しきった砦として屹立している。
その一方で、抵抗がより大きな軍事的パンチ力を獲得しそうな傾向を指摘することもできるだろう。直近の戦闘では、近接戦におけるかつてないほどの熟練が証明され、他方でロケット弾は――象徴にしかすぎないとしても――はじめて1948年の占領地のあらゆるコーナーを射程に収めた。BDS[ボイコット、資本引き揚げ、経済制裁の運動]はもう一つのまたたいている光だ。だがもっとも重要なのは、イスラエル国家はいまだに抵抗それ自体を一掃することにも、みずから出す条件で紛争を締めくくることにも成功していないということだ。ここにこそパレスチナの人々のもっとも大きな達成がある――たとえそれが緩慢で、かすかなものでしかないにしても、残り火は実際に燃やされつづけているのだ(もっとも、ガザで次の大火が起こるのは時間の問題であり、それはこれまでよりもさらに破壊的である可能性が高く、その結果は――抵抗運動が生き残るのかどうかも――見通しがたい)。ラマダーン・シャラフは、危機的局面における基盤的な希望についてこんな格言を残している。「もし強い者が勝利を収めていないなら、かれらは負けたということだ。もし弱い者が打ち負かされていないなら、かれらは勝ったということだ」。

土地それ自体に関しても、オスロ合意以後の年月が、パレスチナ人と土地との関係を毒する役割を果たしてきた。刊行予定の論文のなかでヌーラ・アル=ハリーリー(Noura al-Khalili)は、在来の集団的土地所有形態である〈ムシャー〉の制度が、シオニストへの土地の移譲を円滑にすることを目的としたイギリスの試み、すなわち共有地をばらばらにし私有化するという試みを防ぐうえで、どれほどの成功を収めたのかを実証している。しかしながら、このところ残存している〈ムシャー〉の土地は、こうしたコモンズを囲い込み、利潤のための建物を建てるパレスチナ人の土建業者によってつかみ取られるがままになっている。かれらはそれを〈ソムード〉の行為として正当化している――もし自分たちが空いている土地をつかみ取ってしまわなければ、入植者たち、あるいは壁がそこを食い尽くしてしまうだろうし、そこはパレスチナの人々の手から失われてしまうだろう。それゆえに、そのうえには可能なかぎり迅速にコンクリートが注がれなければならないのだ。
ラーマッラーの周囲で高騰する不動産ブームのなかで、赤いタイルの屋根がいぶかしくも入植地の屋根に似て見えるというのは、いかにも幻惑的な現象だ。シャハーダは、「野生の美しい丘陵」が成長する都市によって「侵略」されており、そうした拡張は敵の拡張を反映している、それどころか敵と張り合っていると不平をもらしている。もっとも気の遠くなる例は、ラワービー計画だ。私企業の資本だけから融資を受ける最初の計画的なパレスチナの都市として売り出され、建築家・資本家のバシャール・アル=マスリー(Bashar al-Masri)の管理下に置かれたラワービーでは、ラーマッラーとナーブルスのあいだの二三の丘のうえに高層ビルが広がっており、第一フェーズにおいて25000人の住民――主としてパレスチナ人だが、イスラエルのユダヤ人にも世帯を購入する招待があった――を収容することが予定されていた。それはまさしく大規模な入植地のような外観だ。計画を実現するために、アル=マスリーはトニー・ブレアの申し出をまんまと利用し、付け加えられた産業区域の業務の外部委託をGoogleやMicrosoftに依頼し、イスラエルのハイ・テック会議に政府の代表とならんで参加し、入植地の代表的な建築家の助力の恩恵をこうむり、アリエル・シャロンのかつての助言者だったドヴ・ワイスグラスからシモン・ペレスにいたるまで、あらゆる人物と連携を行ってきた。
これが、パレスチナの風景と遺産にかかわるひとつの方法だ。また別の方法のひとつは、伝統的な種の品種のライブラリーを立ち上げるというものだ。2016年の夏、農学者ヴィヴィアン・サンスール(Vivien Sansour)のリーダーシップのもと、パレスチナ〈遺産の種〉ライブラリーが西岸地域の中心部に出現した。彼女は可能なかぎり多くの種をあつめ、それらを絶滅から救うことと同時に、その地域のパレスチナ人の誰もが種を借り、植物を育て、新しく種を返せるようになることを目指している。 『オブザーバー』紙で、彼女はみずからの救出の仕事の背後にあるビジョンを説明している。
私はながいこと、パレスチナを離れていました。離れているあいだに思い出されたのは、匂いであり、味でした。帰って来てみると、自分が思い出していたものが脅かされ、消滅しつつあることに気がつきました。脅威の原因は、いくつかあります。特定の品種や栽培方法を後押しするアグリビジネス企業、そして気候変動。人々が食用植物――〈アクーブ〉アザミなど――を探して手に入れる場所もまた、イスラエル入植地の拡大といった問題のために脅かされていました。そして同時に、何かもっと深いものもまた脅かされているのだと、私は気づきました――文化的アイデンティティという感覚への繋がりです。女たちが畑でうたっていた唄。私たちが使うフレーズ、それどころか一つ一つの言葉まで。ですから、そこではローカルな生物多様性を保全することのみならず、伝統的な方法の農業というパレスチナ文化の重要性もまた問題になっているのです。
ひとつの例を挙げれば、
たとえば、西岸の北部で生育していた〈ジャドゥーイー〉として知られる巨大なスイカがあります。1948年以前は、それは周辺の地域へ輸出されていました。シリアのような土地では、よく知られたスイカだったのです。このスイカはほとんど消滅してしまいました。これまででもっとも興奮した発見のひとつは、このスイカの種のいくつかを私たちが見つけたことです。もう七年目になるので、それが生育可能かどうか試してみないといけませんね。
ダリア・ハトゥーカー(Dalia Hatuqa)が『アル=ジャズィーラ』紙に語ったところによれば、ワークショップのなかで若い参加者たちは年長者からの証言を集めるように求められてきた。「際立っていたある物語は、クウェートに亡命していた、いまは年老いた女性の話です。彼女は国を去るまえにオレンジの樹の種を持っていくことを忘れずにいて、移動先でそれを植えました」。そしていま、それらの種をパレスチナの故郷に持ち帰ることができる。西岸とガザに支部を立ち上げることを望んでいるそのライブラリーは、ネオリベラリズム、占領、気候変動という三つの害悪に反対して立ち上げられた。最後の気候変動に関しては、次のこともまた、別の恩恵と言えるかもしれない。つまり、使われてはいないけれども潜在的には救出可能である最古の種の品種のなかには、ときおり暴風雨を浴びるだけの乾燥した不毛な丘陵にも適応したものがある――つまり、いまやますますありふれたものになりつつある種類の気候に。
〈ムカーワマ〉[抵抗]はこのとき、パレスチナ人の生来の性質なのではない。ほかのいかなる人間にとってもそうでないのと同じように。それが別のタイプの破局と闘ううえでインスピレーションの源になるのは、それがただ積極的に選び取られるという、それだけの理由によるものだ。

〈アウダ〉[帰還]
左派が持っているノスタルジアとの関係は、こじれたものだ。昨今の加速主義の流行は、ノスタルジアへの侮蔑という伝統をよみがえらせたかに見える。オリジナルの『加速派政治宣言(#Accelerate Manifesto)』のなかでウィリアムズとスルニチェクは、「抽象性、複雑性、グローバル性、そしてテクノロジーからなる近代のなかで安らぐ」ことを学ぶよう、私たちに懇願する。そして行動の動機付けとして過去を眼差すことをやめ、未来からの眩しい光に(ふたたび)向きあうことを学ぶように。そうしたことは、いま取り上げている問題にとって、何を意味しているのだろうか?
アラステア・ボネット(Alastair Bonnett)は、前に進むことについて別の考え方を有している。過小評価されている著書『過去に取り残されて:ラディカリズムとノスタルジアの政治(Left in the Past: Radicalism and the Politics of Nostalgia)』のなかで彼は、「メエルシュトレエムの大渦のなかでくつろいだ」気分になろうとする左派の近代主義的なプログラムの末路は、数多くのサバルタン階級の人々のただなかで耳を閉ざしてしまうことだと強く主張する。なぜなら「混沌や方向喪失の状態を楽しく味わうのは、十中八九、直接それらを経験してきた人々ではない」からだ。現在そうした状態にある人びとは、ノスタルジア(「変化を目の前にして喪失の感覚を覚え、過去を憧憬すること」として定義される)にたずさわる可能性の方が高い。かれらには、特定の物事に関しては昔の時点のほうが良かった――あるいは、特定の物事が現在失われつつある――し、それらは復元し防衛する必要があるのだと信じるだけの理由がある。ボネットはそうした信念なしには考えられない二つの闘争を名指している。反植民地主義の闘争と、環境をめぐる闘争だ。

カランディア難民キャンプ、2001年4月。第二次インティファーダの波が大きく寄せては返している。サリーム(Salim)はみずからの活動について話しはじめるまえに、私にあるものを見せようとする。彼は緊張し、気を張りつめ、警戒している。一時間もしないうちに、近隣の子供たちがアラームを鳴らし、サリームは裏のドアから飛び出していくだろう。だがいま彼はゆっくりとソファをはなれ、隣の部屋に入り、ビデオを持って戻ってくる。彼はテレビをつける。ぶれの多い手持ちカメラは、緑のなかのあるシーンを写していた。そのフィルムは何年か前のもので、そのころはまだ完全封鎖が行われていなかった。サリームの一家はミニバンで森のなかを走り、ここがそうだと思われた林間の空き地へと入ってきていた。1920年代には生まれていたという年齢の祖母が、茂みのなかの道を先導していく。彼女は伝統的な刺繡をあしらった上着を着ていて、白い頭飾りが風にはためいている。彼女が帰ってくるのは今回がはじめてだが、この場所を立ち去ったことは一度もないかのように見える。彼女はあらゆるものをたちどころに見つけ、指をさして大声をだす。ここが井戸! ここで私は生まれたんだ! お母さんはここで野菜を育てていたよ! あそこ、あの家に、私らは新婚夫婦として住み始めたんだ! 子供たちは彼女のあとをついていき、かれらの好奇心をカメラがおさめる。かれらは想像力を働かせなければいけない。というのも、目に見えるのは、草に覆われた基部と、植物のあいだから突き出している石だけだからだ。しかし見間違えるはずもない。ここがその場所、薙ぎ払われた村があった場所なのだ。
サリームは涙の波を押し戻そうとする。彼はそのフィルムを何百回となく見ているに違いなかったが、反応は身体的にあらわれる。彼は震えだす。それをどうにかしようとあらゆる力を奮い起こしても、涙は彼を打ち負かす。そのあいだにも、兵士たちはキャンプのコンクリート・コンテナに挟まれた路地を、奥へ奥へと進んでくる。

パレスチナの人々にとって、ノスタルジアはなによりの前提だ。それを克服するよう、かれらに訓示を垂れる人々もいる。昔の村々のことは忘れて、先に進むようにと。「忘れる能力とは」とボネットはヘルバート・マルクーゼを引用して言う、「服従を維持するための心的機能だ」。勝ち誇る主人(この場合には、シオニズムの入植者植民地主義者)の声が聞こえてくる――過去のなかにはまり込むのはよせ。これに対して、パレスチナ人は戦闘的ノスタルジアで応じる。
パレスチナの人々にとって、1948年以前のほうが幸せであったことを否定するためには、シオニストにならなければならない。化石燃料経済の蓄積的な効果が二十世紀後半に牙をむく以前のほうが気候という点ではこの惑星はより良い状態にあったことを否定するためには、気候変動否認主義者にならなければならない。クラインの未来予測の帰結は、(パレスチナ型の)ノスタルジアが普遍化されるだろうというものだったが、そこには十分な理由がある。実際のところ、いくらかの非常に価値ある物事に関して、川が干上がるまえ、土地が海の底に沈むまえ、穀倉地帯が乾燥地帯に変わるまえ、私たちの北極の家に雪が降らなくなるまえのほうが、客観的にみて、良かった。ますます多くのビデオが、衝動にかられて観られるようになるだろう。何度も、何度も。ノスタルジア過剰という理由でパレスチナ文学をせせら笑ってきた批評家たちの判断は、早計なものだった。「パレスチナ人たちはみな、生まれながらの詩人だ」とジャブラーは小説『船』のなかで書いている、「なぜならかれらは二つの根本的な物事を経験しているから。自然の美しさと、それから悲劇を」。それは塩の柱[旧約聖書の『創世記』の逸話では、ロトはソドムから逃げる際に神の命令に反して後ろを振り向いたことで、妻を塩の柱にされてしまう]というよりも、予言的な目録なのだ。
さらに、もし私たちが、パレスチナや気候変動について、その他の点では健康的な進歩という軌道からのマイナーな逸脱に過ぎないと考えるのをやめ、むしろ後期資本主義こそが社会と自然の双方における根本的に破壊的な作用力なのだという視点をもつならば、喪失こそがこの時代における主たる状態であることを私たちは受け入れなければならない。そして、あまたの闘争が始まるベースラインには、瓦礫が一面に散らばっているだろうということを。私たちは「避けがたい落下穴に頭から突っ込んでいっている。これが進歩であり、むしろ病気の進展に似ている」とワーディーは言う。だから、手榴弾を手に取り、樹々を植えよう。

ナースィラの〈ウード〉を手に、怒りと哀悼の満ちた音色でル・トリオ・ジュブラーン(Le Trio Joubran)は戦闘的ノスタルジアのための驚くべきサウンドトラックを奏でる。もう一人、アノーニ(Anohni)もいる。おそらくこの千年紀に現れたこれまでのところもっともソウルフルな白人の声であり、間違いなく、政治的カルチャーのなかのもっとも力強いアクトのひとつだ。
なぜ私を地球から切り離したのか?
おまえたちは何マイルもの高さの線を引いてきた
鋼のなかや原子核のなかに(…)
腐った死体は金色の糸
瀝青のような髪とねばつく肉
プラスチックで切断された海の生命(…)
コンクリートでできた鋭いナイフ
それから、彼女の声はもっとも強烈な悲しみと憤怒の音調へとのぼり詰める。
お前の未来なんて欲しくはない
私が故郷に帰ることはけっしてない
お前の未来なんて欲しくはない
お前が生まれるまえに、私は生まれているだろう

パレスチナの民族運動は、帰還の権利を要求している。国連総会決議194号でそれが認められているように。気候運動は、CO2濃度の目標値として350ppmを呼び掛けてきた――現在はおよそ404ppmであり、毎年2度ずつ上昇している[2017年当時。翻訳時の前年2023年で約422ppm]――が、それは安定的な気候のための限界値として科学的に合意された数値に基づいている。(近年では気候活動家たちのあいだで、自分の生まれた年のppmを身体にタトゥーで入れるという流行が生まれている。 「やつらにも決してできないこと/闘争のタトゥーをお前の腕から取り去ること/そしてお前が生まれた日付を消し去ること」と、パレスチナの詩人マイ・サーイグ(Mayy Sayigh)は書いている。) どちらの運動も、いくつかの物事に関しては、過去の姿に戻ることが必要になるだろう。 パレスチナ人はまさしく1948年以前にそうであったように自らの国のなかで暮らす必要があるし、CO2濃度は1980年代後半の水準以下にまで戻る必要がある。
それらがドン・キホーテ的な要求であることは分かり切っている。そうした理由でこれらの要求を鞭打つ人々は、技術的にも、記述的も、正しい。だがドン・キホーテ的とは何を意味しているのだろう? その単語は言うまでもなく、セルバンテスの『ドン・キホーテ』の逸話――騎士が三十も四十もある水車小屋を獰猛な巨人たちだと思い込み、槍で攻撃しようとしはじめる――に由来している。騎士の従者は、それが巨人ではなく碾き臼を回す機械仕掛けであることをおだやかに伝える。こうしたイメージにおいて、資本主義以前の所有関係と、本質的に化石燃料以前のものであるエネルギー源とが、典型的に結びつけられている。
今日では、騎士も従者も存在しないし、槍をもって旅してまわる者は誰もいない。石が私たちの時代の遍在する武器であり、特徴的なエネルギー源は石炭だ(世界ではいまなお風力の十倍以上の電気を生産している)。石炭火力発電所に、石を投げつけろというのだろうか? そうすることは、特段に錯乱的でも不名誉なことでもない。
私たちが抱えこまなければいけないドン・キホーテ的な大義の数は、深大な不正がいかに幾何級数的なしかたで増殖してきたのかを反映している。それは、今世紀のうちに人間の文明が崩壊する可能性があるということが、厳密かつ最新の科学を手放すことなく主張されるほどの地点にまで達している。今日だれかがある大義をドン・キホーテ的だと酷評したときには、それはそこにこそ集結する必要があるというサインなのだ。

川から海まで――CO2の排出はまず根絶され、それからネガティブに転じなければならない。森林の拡大であれ、岩石の風化であれ、マングローブ林の生長であれ、地中への炭素隔離であれ、その他のプロセス――そしてそれらの組み合わせ――であれ、人間とその最良のテクノロジーによって改良された方法で、地球という同盟軍を味方につけなければならない。〈アウダ〉[帰還]のほかに、前に進む方法はない。パレスチナに関しては、不正という土台に立ったものが権力の座にありつづけるかぎり、火の手は燃え上がりつづけるだろう――そして圧迫は日ごとに強固なものになっている。気候変動に関しては、ゼロからネガティブ排出へという以上に現実的な提案をできる者はだれもいない――そしてCO2の濃度は毎月毎月急上昇しつづけている。破局が滝のように段々と落下していく世界において、生存への道は、あらゆることを求める拒絶主義[マキシマリストは最大限綱領派(テロ行為も含めた直接的な革命を唱えるロシア社会革命党の一派)、リジェクショニストは拒否派(イスラエルとの交渉・和平をいっさい拒否するアラブの指導者・組織・国家)を普通指す]で敷かれている。要求を実現するためには何世紀もかかるかもしれないが、私たちが諦めてしまったら、死ぬことを学ぶことのほかに、そこには何も残らないだろう。

2015年の8月、ハマースの指導部がイスラエル国家との「長期的な休戦」を準備しているという報道が流れた。運動のヒエラルキーの最高位にいるハーリド・マシュアル(Khaled Meshaal)は、和解決着を試みるためにトニー・ブレアに複数回面会した。その時点でPFLPはプレスリリースを出し、政治局のメンバーであるラバーフ・ムハンナー(Rabah Muhanna)は武器を置くことに対して警告を発した。
二十年にわたるオスロ合意の苦い経験とその破滅的な結果から教訓を引き出す必要があることを、彼は話題にした。はじめのうちオスロ合意には広範な支持が集まっていたにもかかわらず、そこから私たちの人民が恩恵を得ることはまったくなかったのだと。「戦線はいつも〈タンクの壁を思い切り叩く〉」と、パレスチナの作家でPFLPの指導者ガッサーン・カナファーニーの小説『太陽の男たち』を仄めかしつつ、ムハンナーは語った。「私たちの人民に、そしてパレスチナの大義と解放に益をもたらさない合意には、私たちはいかなるものであれ反対するし、私たちの武器は常にシオニストの敵に向けられている」。
この主張は、簒奪の行為ではなく連帯の行為として、そして闘争を共有する行為として理解してほしいのだが、タンクの壁を思い切り叩かなければならないのはパレスチナの人々だけではない。熱は恐ろしいほどで、刻一刻と悪化しており、私たちの両手に火ぶくれを起こさせるだろう。それでも、私たちは思い切り叩こう。

アンドレアス・マルムは、スウェーデンのルンド大学でヒューマン・エコロジーを教えている。彼の著作は、『環境史(Environmental History)』、『史的唯物論(Historical Materialism)』、『対蹠地(Antipode)』、『組織と環境(Organization and Environment)』といったジャーナルに掲載されている。多数の著書をあらわし、近著に『パイプライン爆破法』[日本語訳は箱田徹訳、月曜社、2021年]がある。スウェーデン語でも、政治経済学、中東、そして気候変動に関して6冊ほどの著作がある。
(翻訳:中村峻太郎)
※翻訳に際して、中鉢夏輝さんともうお一人、パレスチナに関わって来られた方から貴重な助言を頂きました。記して感謝します。もっとも、タイトなスケジュールでのお願いでもあり、本文中の事実誤認・誤訳等の責任がすべて訳者に帰せられることは言うまでもありません。
出典:Andreas Malm, The Walls of the Tank: On Palestinian Resistance, Salvage 2017, pp. 21-55.
©Salvage, Reprinted in translation with permission of the Author.
画像:Disturbance. Attack on an Arab buss (i.e., bus) July 4, 1938. An Arab National blood-stained buss LOC matpc.18573.jpg (Wikimedia Commons)
公開日:2024年1月22日
最終更新日:2025年7月23日