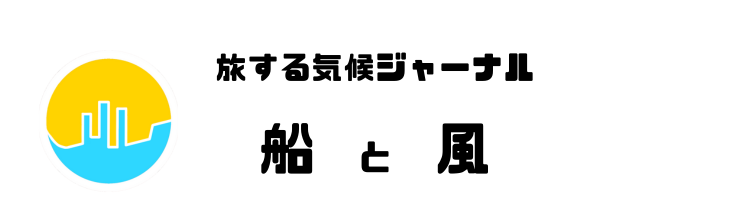脱植民地エコロジーとクルディスタンにおける「低強度戦争」
原文URL:https://merip.org/2024/07/decolonial-ecologies-and-low-intensity-war-in-kurdistan/
はじめに

ディヤルバクルの世界文化遺産であるヘブセル庭園のあいだを流れるチグリス川。Mehmet Masum Suer/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
2024年の冬、アメド(Amed)(北部クルディスタン)という名でも知られている、トルコのクルド地域にあるディヤルバクル(Diyarbakır) に帰還したとき、私が目にしたのは包囲攻撃後の都市の姿であり、歴史あるキリスト教地区スール(Sur)を野外ショッピングモールへと作り変える工程は、すでに部分的に完了していた。
私が2004年以来訪問を重ねていた地域は、二〇年が経った今となっては地図の外に掃き出され、新築コンクリートのアパートメント邸宅と修復を待つマンション群とをつなぐ、閑散とした観光公園にとって代わられようとするばかりだった。
こうした開発プロジェクトは、2015年から2016年にトルコ国家とクルディスタン労働者党(PKK)とのあいだで生じた都市部戦争の結果のひとつだ。2015年7月にトルコとPKKのあいだの和平プロセスは終わりを迎え、それから間もなく、シリアとの国境のトルコ側に位置する国境都市であるスルチュ(Suruç)でISISによる自殺攻撃があり、コバニ(Kobanê)再建のためにロジャヴァ(Rojava)へ向かっていた社会主義青年組織連合(Federation of Socialist Youth Associations)のメンバー33人が殺害された(その攻撃は、2013-2015年のISISに関連する攻撃の大波の一部だった)。だいたい同じ頃、親クルドの人民民主主義党(Halkların Demokratik Partisi, HDP)の首長たちやクルド人運動の設立者たちが、トルコ領内クルディスタンのいくつかの都市における民主的な自治を宣言した。クルドの若者たちは愛郷革命青年運動(Yurtsever Devrimci Genclik Hareket, YDG-H)を形成した。その運動は新しく宣言された自治空間の防衛に責任をもつものであり、トルコ国家に対する戦争での前線のアクターとなった。
軍事作戦は2016年に終了したが、包囲封鎖は2017年に入るまで継続した。スール地区はこの時期を生き延びたが、それによって人口上・空間上の地殻変動的な傷痕が残された――地区の住民の半数が移動を強いられ、東部地区にある六つの近隣地域は、反テロリズム令によって永久的に立ち退かされた。こうした法令は、管理単位に基づく地域のさらなるセキュリティ化と新たなコンクリート・ブロック住宅の開発につながった。
しかし2015年から2016年の包囲攻撃以前であってさえ、2009年にクルド自治体が始めたスールでの都市の再開発プロジェクトは、クルド人の貧しい都市在住者を立ち退かせ、かれらの家屋や農園を没収していた。そしてさらに過去に遡れば1990年代には、クルドの田舎地域を巻き込んだトルコ国家とPKKのあいだの戦争のあいだ、クルド人の住民たちはその田舎の故郷から強制的に追い立てられ、ほとんどが農民であったクルドの民間人たちは、近隣の州首都やスールのような区域――1990年代以降人口が倍加してきたような区域――へと押しやられた。
反乱潰しとしての環境への暴力というパターンは、アルメニア人ジェノサイドの瓦礫へと遡る、トルコ支配の長い多層的な歴史のなかにぴったりと収まるものだ。脱植民地エコロジーによるアプローチは、低強度戦争と、土地を改造・破壊しようとするより大きな歴史的努力とのあいだの繋がりを暴き出す。エコサイドと植民地暴力のあいだの繋がりがますます意識されるようになるなかで、クルド人の活動家たちは、先祖伝来の土地への要求と、大規模な政治的暴力に対抗するエコロジーのイニシアティブをめぐる、現代的な闘争にたずさわっている。クルドの先祖伝来の[土地への]要求は、非・ムスリム、非・トルコ人のコミュニティのそれとも交差している。とりわけ、かつてはそうした土地で農業を営んでいたアルメニア人たちと。
クルド人の自治と土地
脱植民地エコロジーのアプローチは、ダム、採掘、都市改造、軍事作戦といった介入を通して、トルコ国家がいかにクルド人の地理を不安定化させ、封じ込めてきたかを明らかにする。こうした諸技術は、人工環境および生態系の生命の双方を、主権国家としてのトルコの所有物および商品化可能な資源として枠づけるものであり、クルド地域の封じ込めのためのレールを敷くものだ。このアプローチはさらに、植民地化されたクルドの領域におけるエコロジカルな瓦礫に注意を向け、人々と人間以上の存在(農地、庭、果樹園、在来の種子、樹木、薬用ハーブ、植物と動物たち)とのあいだの連携がいかに破壊され、傷つけられてきたかということを強調する。
大規模暴力がもたらす構造的効果、ならびに(グローバルな環境アクティヴィズムというより大きな文脈のなかでの)そうした暴力へのエコロジーに基づく反応を理解するうえで、シリアとトルコのクルド地域は(決定的に異なりつつ重なりあってもいる)いくつかの素材を提供してくれる。農業の近代化は、シリアにおいては歴史的に人種化された問題だった。水と土地の権利へのアクセス、そしてアラブ人による大規模な土地所有を伴う国営農場の確立は、アラブ化政策に役立てる目的で利用されていた。[1] アサド政権が倒れ、 ISISによる封じ込めを受けたのち、ロジャヴァのクルド地区における農業政策には、自給的な農業を支援することによる現地での食料供給の確保が含まれるようになった。
トルコでもまた、農業の近代化は人種化された、そして官僚的な事柄だった。目標はトルコ化であり、それを中心的に計画したトルコ人の技術官僚たちは、クルドの連合や地主たちとも地域的な同盟を結ぼうとした。[2] こうしたプロセスには、主要作物に目標を定めた包括的な年次計画を制定すること、作物ごとのエーカー数を確立すること、そして種子や肥料、その他の生産要素の使い方も含む、作物の育成を可能にするための指導を提供することが含まれていた。
クルドのいくつかのローカルな環境コレクティヴは、こうした撚り合わされてはいるが別個のものである人種化のプロセスを生き延び、それを転覆させようと試みてきた。[3] シリア北東部でのクルドの自治連合システムにおける食料協同組合や農業イニシアティブ、ならびに環境活動家たちの半自治的なネットワークが、環境政治をめぐる議論に介入してきた。かれらは、戦争、気候変動、災害(2023年の地震のような)による絡まり合った環境破壊への解決策として、脱植民地エコロジーのモデルを押し出した。
新たな集合的参加形態のなかには、クルディスタンにおけるエコロジー協議体(Ecological Councils) やメソポタミア・エコロジー運動(Tevgera Ekolojiyêya Mezopotamyayê)——ローカルなエコロジー組織のネットワークとして2011年に設立された——などがあり、それらは現代のクルド人の政治的実践を反映している。かれらの環境保護への関与は、PKKのアブドゥッラー・オジャラン(Abdullah Öcalan)が2005年初頭に宣言した民主的連合主義の原則に基づいたものだ。その宣言は、トルコのクルド地域の政治的組織が、国家による掌握よりも自治に基づいた脱植民地的な自己統治のプログラムを目指すようになる転換点を画した。
エコロジー協議体のような水平的かつ集合的な参加の形態を用いて、環境活動家たちは、より大規模なクルド人の運動が環境保護により積極的に関与するための組織化を行ってきた。こうしたエコロジー協議体は、あらたな高度セキュリティの警察署の展開を通じた地域の軍事化や、シェールガスの水圧破砕[による採掘]に反対し、文化遺産や自然遺産を保護することを求めるキャンペーンを行ってきた。
クルド人の運動は自治に力点を置くものだが、そこでは、食料主権、先祖伝来の土地への権利、そして脱植民地化の遺産といった事柄に対するトレーニング・教育セミナーを通じて、土地との親密な結びつきが保たれている。例えば、〈農業・種・食料委員会〉のアメド支部は、食料主権やクルディスタンに自生する在来種の収集のためにキャンペーンを行っている。
ロジャヴァにおけるクルド人の自治的連邦システムにおける食料主権を基盤として、いくつもの農業イニシアティブや食料協同組合――ゆっくりと姿を見せ、異論もあり依然として発展途上ではあるとはいえ――が、国境によって分断されているにもかかわらず、トルコのクルディスタンにおける半自治的な環境アクティヴィズムやイニシアティブのネットワークと共存しながら仕事をしてきた。
エコロジカルな再生
包囲攻撃の前、アメドはひとつのエコロジカルな再生を目撃していた。それを具現化していたのは、都市部の都市農園と果樹園だった。[4] 環境活動家が説明しているように、その存在自体が、トルコ国家、産業化された商品作物ビジネス、そして協働するクルド人の地主や請負業社のあいだに存在する人種化された暴力的な同盟関係を避けて通り、それを押し戻すことを意図したものだ。それらはまた、小農たち――かれらのほとんどは、二度目ないし三度目の強制移住を経験してきていた――から食料主権のコントロールを奪い去る産業化された単一栽培政策に対しても挑戦を投げかけるものだった。
新たな連携関係を形作っていたのは、エコロジー協議体、小農、環境活動家、自治体職員、都市居住者、そして時には、2011年のシリア内戦や2014年にシャンジールで行われたヤズディ・ジェノサイドから逃れてきた難民たちだった。ヤズディの人々は、イラク・トルコ国境のクルドの村によって受け入れられたあと(かれらの越境を手配したのは密入国業者だった)、クルドのゲリラ・グループの助けを借りてアメドまで辿り着いていた。かれらはその後アメドのようなクルドの都市に散らばった(難民の数は着実に5000人に到達した)。バルカン半島ルートでブルガリアを経由してドイツに向かう中継地点と見做されていたキャンプの滞在中、ヤズディの家族たちは環境活動家たちと協働し、難民の家族によって世話されていた都市農園から構成される、一つの都市森林を作り上げた。
こうした果樹園での生産物は、都市部の市場へと集配され、自治体による特設市場で販売されるか、消費者に直接販売されることになっていた。なかには、クルドの地主の用地を自治体が貸し出す場合もあった。自治体の職員が苗木や在来の種を提供し、農民たちをローカルな市場にじかに結び付けた。こうしたアプローチによってローカルな市場における男性の行商人や露天商が不要になり、女性たちが、みずからの生産品からより多くの価値を手にすることができるようになった。スールのヘブセル庭園(Hevsel Gardens )では、アシェフティス(asheftis :農園で薬草を集めて市場で売る女性)として働いている女性たちもいる。
包囲攻撃の期間中、HDPによって運営されていた親クルドの自治体は、国選の行政官の手に引き渡された。社会的・文化的な連合体やコミュニティは、承認制によって許可されたり閉鎖されたりした。アーミドの政治的・社会的・文化的な労働者たちは、逮捕されるか(そのなかには自治体市長と副市長たちも含まれていた)、辞職を強制されるかした。
2016年、トルコ国家に任命された自治体の管財人が到着した直後、用地での耕作が禁止された。立ち退かされた農民たちが持ち帰ることを許されずに残った作物は、放置されて腐るがままになった。それ以来、以前の共同体の仕事や農耕のあらゆる痕跡が消し去られてきた。ヤズディの家庭と協働して2014年に都市果樹園を設計し栽培していた環境活動家たちは、国家による散発的な軍事攻撃のスパイラルのなかで脱植民地エコロジーの原則を実行に移すことの困難さを強調している。そこでは、よく口にのぼる言い回しにあるように、「戦争こそが風土」になっているからだ。
破局の層、脱植民地化の要求
2024年現在、運動設立にたずさわっていた私の友人のほぼ全員が、スールの陥落とその町の近隣を守って亡くなった若い世代の人々の死に直面して、自己批判をする以外に選択肢はないと言明した。彼らの自己批判は政治的説明責任への絶え間ない要求へと変わり、ときにそれは罪のかぶりあいにまでなった。
彼らの中には、襲撃のあいだに加えられた損壊を記録することを目指し、様々な国際的な組織のために一覧表を作るものもいた。筆者は2019年に、彼らから、そしてヘブセルの古くからの庭園で農業用地を管理しているクルド人の請負業者へのインタビューから、庭園を開発するために建築の許可を得たいという請負業者の望みは、ユネスコの世界遺産プログラムによって部分的に棄却されていることを知った。ユネスコは包囲攻撃より先にその町に来ていた。学者やユネスコの専門家と連絡を取って、旧市街中心部と庭園を世界遺産リストに登録したのは、クルドの文化遺産の専門家と地方自治体レベルの政治家だった。しかし、アメドの地にデータ収集者として、ユネスコの管理者として在留していたプロジェクトマネージャーやフィールドワーカーたち-彼らは反乱潰しに対抗するクルド人の運動による環境キャンペーンに精通していた-によると、組織はトルコ政府と同盟を結んだクルド人の地主、開発者、請負業者が、スールや城壁に隣接した庭園から収奪することを止めるように国家に圧力をかけることに失敗していた。

2024年ダバンオール地区における破壊されたマンション。著者提供。
敗北の跡を見るのを拒んで、私の友人は旧市街にもはや行かなかった。彼らは2000年代の初めに、そこでソーシャルワーカーや地方自治体レベルの政治家として働いていた。しかし、これらの元運動設立者たちは、今では主に選挙期間中しかその町での政治生活に参加していないにもかかわらず、革命勢力として自分たちを位置づけ続けている。包囲攻撃のあいだとその後にも続く対テロリズム令によって投獄された何千人もの人や、トルコから逃げることができる人々を除いて、多くの元運動メンバーはその町に新しく形成された20~30階建ての高層ビル群がある中流階級の地区に入ることを諦めて受け入れた。
これらの空間では出入りの管理された区画、カフェ、レストランなどで活気のある社会生活が営まれていた。山の中にあるPKKのトレーニングキャンプを含むクルドの土地の地名にちなんで、いくつかの事業が名づけられた。都市は数年の絶頂期のあと、現在は開発の行き詰まりを経験しているが、建設は続いており、黒海地域からのトルコ人の請負業者と様々な経歴をもつクルド人のビジネスマンとを出会わせる市場関係を生みだしている。このような新しいエリートビジネス階級の一部は、自身をパルチザンと位置付けている。彼らは革命の栄光ある立役者としてPKKの指令者や戦闘員を記憶しており、彼らの名前を会話に潜り込ませる。
最近その町を訪れた際、スールのザンチェペクにある歴史あるキリスト教徒居住地は歩くのが困難だった。攻撃によって完全に破壊された歴史ある地域は、コンクリート造りの邸宅と修復作業との間で圧迫されている。1990年代の戦争と、そして今回の包囲攻撃によって、逃げるよう強いられる前、住民は困難に直面しつつ活気のあるストリートカルチャーをここで作り出してきた。しかし今、その地域は巨大なショッピングモールに変容しつつある。アルメニアの使徒教会、カルデアのカトリック、シリアの正教会など、今では神聖視されなくなった様々な宗派の古い教会は、観光客を引き寄せている。デザイナーズブティックやお土産物屋が周りには立ち並ぶ。低強度戦争は破壊だけを指すのではない。破壊の上に収奪し、ストリートの政治精神を停止させ抑止し、クルド人の都市貧困層の社会的回復を妨害する。
ザンチェペクで、城壁からグランドモスクに向かって歩き、コンクリート造りの邸宅や復元を待っている古いマンションの残骸を通り過ぎた。この辺りの古いマンションの中に、一つの建物がまだ立っていた。入り口の扉に新しくつけられた銘板によると、それはハスルルモスクといい、その最初の持ち主はアルメニア人だったようだ。復元会社のインターン生の若いムスリムの女性が話しかけてきて、私たちは一緒に歩いた。カルデアの教会を通り過ぎた。そこは教会兼ディジュレ大学のアートセンターとして機能する空間として改修される予定で押収されている。それはほかの復元される建物のモデル例になると考えられている。彼女はザンチェペクだったところに次から次へと付け加えられる新しいコンクリート造りの邸宅を見せてくれた。彼女からすると、邸宅は町の精神を破壊する。邸宅は町の過去の歴史的現実を反映していない。彼女はトルコ政府の勝利の印として地域全体の瓦礫の上になされる復元作業のイメージを伝えるのではなく、クルドを中心とした歴史とひもづけてその地域を伝えてくれた。良心的な復元と魂を破壊する再建との間の彼女による区別は、包囲攻撃のあいだに現在の体制が権力を確立してから育まれた、新しい世代の政治的な立場を垣間見せた。文化的にはクルド、政治的にはイスラム、社会的にはクルドのまちの遺産に与しており気を払っているという立場である。
私は城壁に向かって散歩を続けた。その日は晴れた冬の日で、古い城壁に沿って並ぶ、よく手入れされた庭に置かれたベンチに腰かけている女性たちを見た。その都市から追い出されるのが2回目で、破壊された家や生活を懐かしく思うスールの以前の住人たちが、日中をここで過ごし、昔住んでいた地域の空気を吸いに来るのだと、一人の女性が話してくれた。彼女は、彼女のように前回の包囲攻撃によって強制的に追い出された人々を住まわせる、トルコ集合住宅局によって建てられた新しい建物に対して、よく思っていない。
私が話したもう一人の女性は、メリクアフメット出身で、ダバンオールに親せきがいる。これらは隣接する地域である。前者の地域ははまだ活気があった。通りには子どもがあふれ、女性たちは路地でおしゃべりし、コーヒーハウスからは笑い声がはじけている。後者は包囲攻撃の期間に、そして破壊した当の国家による土地の合法的な没収によって、部分的に破壊されていた。スールの他の5つの地域と同様に、そこは低強度の計画のえじきとなっていた。
長いおしゃべりのあと、私たちはお互いに共通の知り合いがいることに気が付いた。木をこづきながら彼女は「彼らはいつメリクアフメットを破壊すると思いますか?」と聞いた。私が答える前に、彼女は「最初に爆撃がやってくるでしょう」と付け加えた。彼女は昔住んでいた地域を指し示した。そこはアルメニア人ポグロム、もしくはアルメニア人ジェノサイドの時に破壊されたマンションの廃墟の上に成り立っており、その後のクルドの人々に対する包囲攻撃の期間を目撃してきた。復元の作業は、これらのマンションや、玄武岩や根ごと引き抜かれた木々でいっぱいの庭で続けられている。「国家は破壊し、若者は防衛して死に、そして私たちは毎回戻ってきます」と彼女は言った。
長い歴史のレンズをとおしてみると、1915年のアルメニア人ジェノサイドにつながる1895年のアルメニア人ポグロムから始まる、没収された財産を取り戻すという情熱は、トルコがクルドの地方と都市に対する低強度戦争を始め、土地を改変し始めるはるか前にさかのぼる。まとめると、層の上に層が重なっている復元は、この前線となっている地理において、脱植民地化を訴えるただ一つの要求のみがあるのではないということを示している。■
翻訳:坪田七海、中村峻太郎
※翻訳にあたり、トルコ語の表記等に関して、京都大学人間環境学研究科修士課程(人類学)の田辺清鼓さんに貴重なアドバイスをいただきました。記して感謝いたします。
出典:Umut Yıldırım “Decolonial Ecologies and ‘Low-intensity War’ in Kurdistan,” Middle East Report 311 (Summer 2024).
© Middle East Research and Information Project, reprinted with permission of editorials.
[1] Miriam Ababsa, “The end of a world: drought and agrarian transformation in Northeast Syria (2007–2010),” in Syria: from Reform to Revolt, Volume 1, eds. Raymond Hinnebusch Tina Zintl (Syracuse University Press, 2015), pp. 199–222.
[2] Begum Adalet, “Agricultural infrastructures: Land, race, and statecraft in Turkey,” Environment and Planning D: Society and Space 40/6 (2022), pp. 975–993.
[3] Stephen E. Hunt and John P. Clark (eds), Ecological solidarity: thought, practice, challenges, and opportunities (Lexington Books, 2021).
[4] Umut Yıldırım, “Resistant breathing: ruined and decolonial ecologies in the Middle East,” Current Anthropology 65/1 (2024), pp. 123–149.