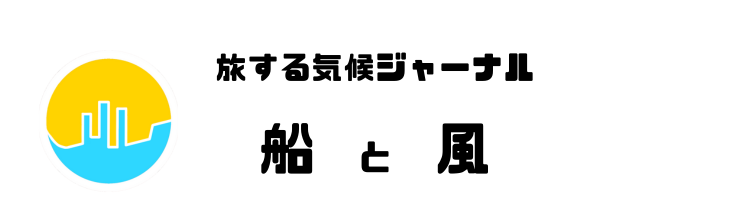[以下はティモシー・ミッチェル著『カーボン・デモクラシー:石油時代における政治権力 Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil』の序章(pp. 1-11)の試訳です。底本は2013年刊のペーパーバック版を使用しました。著者の了解のもとに公開いたします。
原書のサイトはこちら→ https://www.versobooks.com/en-gb/products/2222-carbon-democracy
ティモシー・ミッチェルのアカデミック・ウェブサイトはこちら→ https://blogs.cuit.columbia.edu/tm2421/ ]
ーーーーーーーーーー
化石燃料は、現代の民主主義の可能性とともに、その限界もまた生み出している。そうした諸々の限界を理解するために、何がある種の民主的な政治――私がカーボン・デモクラシーと呼んでいるもの――の出現を可能にしたのか探ることからこの本を始めよう。だが過去に目を向けるまえに、私が念頭に置いているいくつかの現代的な限界の例について説明させてほしい。
2003年、アメリカによるイラク侵攻が行われるなかで、そうした限界のひとつが広く議論されていた。中東地域の際立った特徴とは民主主義の欠如である、ということが頻繁に語られていたのだ。この地域について書く少なからぬ論者にとって、そうした欠如は石油と関係がある。輸出収入の大部分を石油資源に依存している諸国家は、より民主的でない傾向にあるというのだ。2011年にアラブ世界全体に広がった蜂起の波は、大規模な石油収入があることと、より民主的で平等な生への主張を展開することの難しさとのあいだの相関関係を立証しているように思われた。全体として見れば、その国が産出する石油が少なければ少ないほど、そしてその生産量の減少が急速であればあるほど、民主主義のための闘争を展開する用意ができていた。蜂起が始まったチュニジアとエジプト、そしてそれが急速に広まったイエメン、バハレーン、シリアは、中東地域でもっとも石油の産出が少ない国々の一部であり、いずれの国においても石油生産は減少中だった。中東における八つの大きな産油国のなかでは、もっとも産出量の少ない(そして近年生産が落ち込んでいた)リビアにおいてにのみ、同様の政治闘争が勢いを獲得した。対立が崩壊し暴力と国外勢力の干渉の手に落ちたのも、リビアの場合がもっとも早かったとはいえ。[1]
しばしば「石油の呪い」と呼ばれるこの問題について書いている人々の大半は、石油の性質について、そしてそれがどのように生産され、分配され、使用されているのかについて、ほとんど語る言葉を持っていない。かれらが議論しているのは、石油ではなく石油マネー――石油が政府歳入や私的な富へと変換されることで生ずる収入――についてなのだ。石油の持つ反=民主的な特性についてかれらが理由をしめす際には、こうした余剰歳入に焦点が当てられる。すなわち、そこから得られる資金を用いて公的給付や補助金による物価低減を行うことで、諸政府は反対派を抑圧し、政治的支持を買いつけ、より平等な繁栄の共有への圧力から解放されるというわけだ。こうした説明は、石油がいかに採掘され、精製され、輸送され、消費されるかということとは何の関係もないし、凝集的なエネルギー源としての石油の力とも、この燃料を富と権力という形態へと転換させる諸装置とも、何の関係もない。かれらは石油の呪いを、その収入に依存せざるを得ない諸政府を苦しめるものとしてのみ扱っていて、より広い世界がエネルギーを獲得し、その物質的・技術的生活を駆動させるプロセスそのものもまた苦しめられているのだとは考えない。[2]
石油生産の装置の無視は、その下にいかなる民主主義の概念が横たわっているのかを反映している。まさしくそうした概念を共有していたのが、アメリカが2003年にイラク侵攻を行った九カ月後にイラク南部に派遣され、地方議会の議員たちと「能力形成」について議論したあるアメリカ人の民主主義の専門家だ。アメリカの先人たちが設計してきた行政構造をまとめたパワーポイントのスライドを映写しはじめながら、「民主主義の新しい段階へようこそ」と彼は語った。「前にもお会いしたことがありますよね。あなた方とは、カンボジアでお目にかかりました。ロシアでお目にかかりました。ナイジェリアでお目にかかりました」。聞くところによれば、二人の議員たちが話の途中で出て行ったそうだ。[3] 民主主義の専門家にとって、民主的な政治というものはどの場所でも基本的に同じものなのだ。民主主義は一連の手続き及び政治的形態から成り立っていて、上手くやればどんな民主化のための機関でもそれを再生産することができる。あるヴァリエーションから別のヴァリエーションへと。あたかも民主主義が生じるのは、それ自身のカーボン・コピーによってでしかないかのように。民主主義というのはひとつのモデル、ひとつのオリジナルな考え方に基づいていて、ある場所から別の場所へとコピーを取ることが可能なのだ。そのコピーが――多くの産油国でそう見えているように――失敗するとすれば、それはそのモデルの一部が失われているか、機能不全に陥っているからなのだ。
ある理念とは、別の場所でもどういうわけか同一であるようなもののことだ。それはある文脈から別の文脈へと反復することができ、ローカルな歴史・状況・物質的編成から切り離され、抽象的なものに、ひとつの概念になる。民主主義の専門家というのは、民主主義をある抽象物へと、場所から場所へ容易に動いていくものへと作り変えなければならない。それを自分のスーツケースに入れて、あるいはパワーポイントのプレゼン資料として持ち運べるように。ロシアからカンボジアへ、ナイジェリアからイラクへ、人々に民主主義の仕組みを教えるために。
自分もそれとともに動き回るために、民主主義を世界中を動き回る理念に変えてしまった人間は、その理念がどのように作動するのか、どうすれば人々が民主的になるのかといった事柄に対して、もはや特定の方法の説明しか行うことがない。民主主義がある理念なのだとすれば、ある国々が民主的になるためにはその理念を人々の頭のなかに吹き込むしかない。民主主義の問題は、新しい市民のモデル――民主主義の理念にその精神を捧げている人間――をいかにして製造するのか、という問いに姿を変えてしまう。
このところアメリカ合衆国内で行われている中東についての議論のなかで中心的なテーマとなってきたのは、いかに新しいタイプの市民を製造するかという問題だった。イラク戦争について、経済改革について、パレスチナの未来について、政治的イスラームについて、民主化の障壁について、反米主義の拡大について、そして2011年の蜂起について議論がなされるなかで、いかに新しい種類の政治的行為主体を生み出すのかという問いに関心が向けられるのを繰り返し目にすることになった。政治当局に制限を課す能力を適切に備えた権力の主体を、いかに作り出すことができるのか? 権威主義を権威化することを拒絶する市民社会を、どのように形成するのか? 腐敗や縁故主義よりも合理的な自己利益に基づいて行動する行為者に基盤をおいた経済を作るためには、どのような教育、啓蒙活動、訓練ないし経験が必要なのか? 猜疑や抑圧のかわりに、相互の信頼と敵への敬意を土台とする政治形態は、何によって生じるのか? つまるところ、こうした議論が尋ねているのは、どうすれば人々が自分自身を認識することを学び、新しい形態の権力の主体として反応することができるのかということだ。逆に言えば、どのような形態の権力であれば、リベラルないし民主的な政治主体を人工的に作り出すことができるのだろうか?
こうした問いが提示され解答される仕方に対しては、とりわけ民主化に関する議論において数多くの批判がなされてきたが、それはしばしば、いわゆる「より大きな力」の働きを無視しているという理由からだった。中東における民主主義の問題を論じたアメリカの著作はどれをとっても、資本主義によるグローバル化について、そして西側の経済危機を解決するために[中東の]人々を従順な労働者および意欲的な消費者へと作り変える作業について、ほとんど語る言葉を持っていない。帝国の権力――そこから見れば民主化のスキームさえ、弱まりつつある覇権を支えるより広範な努力のマイナーかつ外交的な一部分でしかない――についても、占領軍や軍事政権が用いている暴力と抑圧の諸手段についても、事情は同じだ。だが同時にそうした批判は、こうした[民主主義の布教に関する]議論の興味深い点を見逃してもいる。すなわち、新たな政治的主体の製造し、人々を新たなの被-統治の方法へと従属させるという点に関して、民主主義とは技術工学的なプロジェクトであるという考えのことだ。
中東の民主化に関する調査の一つの例として、アラブ・バロメーターのプロジェクトを取上げてみよう。このプロジェクトは、民主主義の確立につながるであろう個人的な態度および志向の存在を計測するために、五つのアラブ諸国で意見調査を実施した。そうした志向のうちには「政治的な寛容、多様性の尊重、市民としての政治参加、諸個人間の信頼」[4] などが含まれる。プロジェクトの資金源は主にアメリカ合衆国国務省の中東協力関係イニシアティブ(MEPI)であり、プロジェクトがその政治文化を計測・記録しようとしているそれぞれの国出身の研究者たちも運営ボードには含まれていた。アラブ・バロメーターは、グローバル・バロメーターという名前でアフリカやラテンアメリカ、その他の地域でも同様の調査を行うより広範なイニシアティブの一部だ。そのアラブ・バージョンが公開した意見調査の結果は、同地区についての他の多数の調査と同じように、アラブ世界における政治的態度をめぐって合衆国内の公的なサークル内部で行き渡っている多くの想定を問い直すよう要求している。
公的な言説のいくつもの限界を私たちに示してくれる点でいかに有益なものであれ、このプロジェクトもまた民主化と市民社会の問いに関する大半の調査を毒している弱みを抱えていることは、一目見ただけで理解できる。それは「民主化なき民主主義」[5] とでも呼びうるものを探し求めているように見えるのだ。このプロジェクトの前提は、「民主化の成功に必要なのは、民主主義を尊重し、民主的な政治文化の原理を手にしている市民社会の存在である」[6] ということだ。だが私の知っているかぎり、市民的な文化――信頼、寛容、相互尊重といった心的態度やその他のリベラルな美徳――の存在が民主主義の出現を助けることをしめす信頼にたる証拠は存在しない。実際のところ、それと正反対のことを示唆する歴史的な証拠には事欠かない。寛容で教育のあるリベラルな政治階級が、西側の民主主義への闘争の担い手でありながら、同時に民主化の敵対者であり、財産を持たない者たち、宗教的・人種的マイノリティ、女性たち、および植民地主体に有効な政治的権を拡張することを阻止するべく闘った例を、歴史のなかに繰り返し見出すことができる。多くの場合、支配的な政治階級が有していた市民的な美徳とは、民主化に反対するための基盤を提供するものに他ならなかった。みずからの市民性と合理性こそが、いまだ自身のために語ることのできない人々の利益の代弁者として振舞う権限を自分たちに与えているのだ、とかれらはしばしば主張した。いちど民主的な権利を獲得してしまえば、それを行使することで、すくなくとも拡張された政治階級のメンバーのあいだでは、美徳ある市民的態度の発展がうながされるだろう――その美徳の布教と実践という方法を経ることで、人々は民主的権威へと服従するようになるのだ[とかれらは考えた]。それと反対に民主化とは、しばしばこうした態度に対する闘争であった。それが要求してきた一連の政治参加および実践は、より妥協のないものだったのだ。[7] この書籍が関心を寄せるのは、こうしたより非妥協的な政治参加についてであり、有効な非妥協性を有する主体を作り上げるうえで、炭素エネルギーがどのように役立ったかということだ。
私がこの本を書きはじめたのは、民主主義と石油の関係についてより良く理解したいと考えたからだ。はじめのうちは、誰もがそうであるように、私も石油と民主主義を別々の二つのものと考え、一方が他方に対して都合が悪いように見えるのはなぜなのか理解を深めようとしていた。だが中東で石油産業がいかに築かれたかを追跡することで、すなわち人々が石油を探査し、パイプラインとターミナルを建設し、石油を熱エネルギーや輸送手段に転化させ、こうしたプロセスから得られる収入を利潤へと変換し、こうしたお金の流れを還流させ支配しようとした方法を辿るなかで、炭素エネルギーと現代の民主主義が相互に結びつき入り組みあっているということがいよいよ明白になってきた。この本は民主主義と石油についての研究というよりも、石油としての民主主義――そのメカニズムがさまざまなレベルで炭素エネルギーの生産と使用のプロセスを含みこんでいるような政治形態としての民主主義――についての本になった。
石油と民主主義をめぐる研究がその関心をオイルマネー――石油からの収入とその腐敗させる力――のみに限定し、石油が生産され分配されるプロセスから考え始めることがないならば、そうした研究はエネルギーのネットワークが最初に築かれたときの仕方をそうとは気が付かぬままに模倣することになる。1914年、ロイヤル・ダッチ/シェル社がベネズエラで石油の生産を開始したとき、同国の独裁者であるゴメス将軍は、同社に対して精製施設を沖合部、すなわちオランダ領であるキュラソー島に建設するよう要求した。彼は石油から得られるお金は欲したが、精製施設が引き起こすであろう労働力の大規模な集中とそれに付随する労働上の要求は欲さなかったのだ。[8] その十年後、いまではBP社として知られる企業がイラクで石油産業を建設しはじめたとき、同社は近隣諸国を通過して地中海――そこから大半の石油がヨーロッパの精製施設へ輸送されることになる――まで石油を運ぶパイプラインを作ることを計画した。それによって極めて広大な距離にわたって石油生産の細いラインが伸びることになる。民族主義政府がのちにBP社に対してイラク国内で近代的な精製施設を建設するよう要請したとき、同社はこれに激しく反対した。言い換えれば、石油が産油国に影響を与えるのが概してそれがお金の流れに転化された後のことに見えるとすれば、そうした見せかけは、パイプラインの建設、精製施設の位置取り、油田使用料の交渉、ないしその他の配置編成といった事柄を反映したものなのであり、そうした事柄はそもそもの始まりから、組織化された労働力による要求を回避する努力であるという点で、カーボン・デモクラシーの問題に関わるものだったのだ。石油が膨大かつ説明のない政府歳入に転化するということは、民主主義と石油をめぐる問題のひとつの原因なのではなく、むしろ特定の方法でエネルギーの流れから諸々の政治関係を人工的に作り出すことの結果なのだ。
石油の呪いについての説明する際、石油そのものの生産と流通を追跡することに失敗することで、それを通して石油が流れ、エネルギーや利潤や政治権力へと転換されるネットワークのなかのただ一つの結び目だけが、病弊の在り処として診断されてしまう――すなわち、個々の産油諸国における意思決定機関だけが。こうした診断に伴って、産油国にあって非産油国にない症候が、個別のものとして分離されることになる。だが、もし民主主義がカーボン・コピーではない代わりに、カーボン・ベースド[炭素エネルギーの使用に基盤を置いたもの]だったとしたらどうだろう? 炭素燃料の歴史と、独特の仕方で結びついたものだったとしたら? 私たちは炭素そのもの、すなわち石油を追いかけることで、産油国を苦しめている問題とその他のカーボン・デモクラシーの諸限界とを結びつけることができるのだろうか?
工業化された先進諸国もまた、石油国家であることに変わりはない。石油から引き出されたエネルギーなしには、そうした国々の現在の政治的・経済的な生活形態は存在していなかっただろう。その市民たちが発展させてきた食事、旅行、居住、そして物品やサービスの消費の方法は、石油やその他の化石燃料に由来するエネルギーを膨大に必要とする。こうした生活方法は持続不可能であり、かれらは現在、それを終わらせるであろう双子の危機に直面している。
第一に、新たな石油の発見が現在の供給量[の蓄え]の消耗ペースに追いつくことは不可能だ。化石燃料の埋蔵量の算定が複数の対立的な計算方法を含んだ政治=技術的なプロセスであるにせよ、どうやら私たちは供給量が減少していく時代に入りつつあるらしい。[9] 地球全体の化石燃料の貯蔵が使いつくされるということはないだろう。石炭と石油が今よりもさらに希少になり、それらを採掘する困難が増大することで、採掘に必要なコストとエネルギー消費量[の増加]が化石燃料時代に終わりをもたらすだろうからだ。[10] その結果何が起こるのか、私たちには分からない。「他の生物種から人類に遺贈された資本」とかつてジャン=ポール・サルトルが言い表した地球内部のストックは、著しく短い期間のあいだに消費されることだろう。[11] かつては採掘がもっとも容易であったが今や供給量を増加させるのがもっとも難しい化石燃料である石油の場合、近代的な石油産業が始まった1860年代と2010年のあいだの150年間で消費されたトータルの量のうち、半分以上が1980年以降の30年間で燃焼された。[12] 人類史というパースペクティヴから見れば、化石燃料の時代はいまや束の間の幕間劇に見える。
二つ目の危機は、アメリカ合衆国大統領の科学諮問委員会がほぼ半世紀前の1965年に警告したように、これらのエネルギー源を利用することで人類が「知らず知らずのうちに広大な規模の地球物理学の実験を行って」きたということだ。過去5億年以上にわたって地球内部に蓄積されてきた化石燃料をほんの数世代のあいだに燃焼することによって、人類は二酸化炭素を大気中に注入しており、その結果として2000年までに大気中のCO2濃度は25パーセント上昇することが予想されると言われていた。「この数字は、計測可能で、場合によっては著しい程度の気候上の変化を引き起こすのに十分かもしれない」と1965年のレポートは警告し、これらの変化が「人間存在という観点から見て有害」なものになりうると付け加えている。[13] この実験は予想よりも急速に進行した。大気中の二酸化炭素の水準はいまや産業革命期の開始以来40パーセント増加しており、こうした増加のうちの半分が1970年代の後半以降に生じている。その結果起こっている地球上の気候の変動は、単に人間存在という観点から見て有害なだけではなく、惑星的なスケールで破局的なものになろうとしている。[14] 石油が民主主義に課しているより大きな制限とは、化石燃料時代を支配するべく生じた政治的な機構が――それ自体が部分的にこうしたエネルギー形態の産物だが――それ自体を終わらせてしまう出来事[気候変動]に取り組むことを不可能にしてしまうかもしれないということだ。[15]
炭素[の物質そのもの]を追跡することは、民主主義の専門家たちの観念論的なスキームを唯物論的な説明に取り換えることを意味するわけではないし、政治的な結果の原因をそれらを規定するエネルギー形態に遡って求める――あたかも炭素の力が油田ないし採炭場から国家の支配者の手へとそのままの形で移送されるかのように――ことを意味するわけでもない。地中からそれを掘り出す人々の労働にはじまり、炭素はさまざまな変容をこうむらなければならない。そうした変容には、繋がりの確立や連携の構築――そうした繋がりや連携は、物質と観念、経済と政治、自然と社会、人間と非人間、ないし暴力と表象といったいかなる分割にも配慮を示さない――も含まれている。そうした繋がりが、ある形態の力を別の形態へと翻訳することを可能にする。化石燃料の使用と民主的な要求の形成とのあいだの相互の繋がりを理解するためには、それらの繋がりがどのように形成され、それによってどのような脆弱性や機会が生まれ、そこで[化石燃料の]制御がとりわけ効果的なものになるような狭い通過ポイントがいかにして生み出されたのかを追跡する必要がある。[16] 政治的な可能性は、さまざまな仕方のエネルギーの流れと集中によって開かれもすれば狭められもしたし、エネルギーの分配と管理に関連する人々、金融、専門技術、そして暴力の寄せ集めによって高められもすれば制限されもしたのだ。
化石燃料由来のエネルギーと同様に、民主主義の政治もまた最近の現象だ。これら二つの種類の力=権力はその始まりから互いに織り合わされたものだった。この本ではそれらがいかにひとつに寄せ集められたかを辿るが、第一章では、19世紀後半から20世紀初頭のヨーロッパとアメリカにおける石炭と大衆政治の興隆から始めよう。石炭の興隆――地中深くの炭層にアクセスするために蒸気力の利用することで可能になった――によって大規模な製造業および近代都市の発展の道が開けたのだと、そして鉱山、工場、近代的な都市生活のなかから民主主義のために闘う勢力が出現したのだと、長いこと理解されてきた。だがこうした勢力は通常、一面的にも「社会運動」として考えられてきた。仕事場や労働組合、そして政治クラブに集まることで人々は政治的な意識を鍛え上げ、より平等主義的で民主的な集合的生活のために闘ったのだと言われる。こうした説明が一面的なのは、そうした政治的な行為体を結集させた装置の存在を忘れ去り、少数による支配形態が当時晒されていた技術的な脆弱性を無視しているためだ。第一章で示されるように、石炭由来の膨大な新エネルギーによって形成された社会=技術的な世界は、ある特定の点において脆弱なものだったのであり、炭素エネルギーの集中的な蓄積こそが効果的な民主的要求を結集するための手段を提供した。
エネルギーの流れと民主主義の出現の関係についてのこの新たな理解を心に留めつつ、第二章では中東における石油産業のはじまりを点検する。標準的な歴史が伝えているのは、遠く離れた困難な立地で石油を発見する英雄的なパイオニアの物語であり、第一次世界大戦の前夜にこの戦略上重要な獲物を確保するべく行動した先見的な政治家の物語だ。石炭と民主主義の歴史から、エネルギーの政治にはエネルギーの供給を確保する権力と同時にその流れを遮断する権力の獲得が伴うことを学んだ私は、また別の説明を提案する。私が明らかにするのは、いかに石油企業が中東における石油産業の出現を遅らせるために協働したかということであり、いかに政治家たちが海外での石油の確保を自国で民主的勢力を弱体化させるための手段と考えていたかということだ。そもそもの初発から、中東における石油の歴史は民主的政治の形成と解体の一部を成しているのだ。
民主主義に敵対する闘争が第一次世界大戦を引き起こす一因となり、そこから国際連盟と中東の石油地域を支配するための新たな機構――国際連盟の委任統治というシステム――が生まれた。こうした出来事は通常、民主的な自己決定を擁護するウッドロウ・ウィルソン大統領の「十四か条」の理想主義と、中東の石油地域、とりわけイラクを支配下に置いていたヨーロッパ列強国の自己利益とのあいだの争いとして記述されている。第三章が提示するのは別の歴史だ。そこでは、ヨーロッパ左派が帝国主義および原料資源のより民主的な制御を求めて闘った戦時中の争いが、「非統治者の合意」を生み出すための非民主的な機構へと翻訳されることになる。帝国的統治へのこうした「合意」を生み出すためのもっとも重要な場所は、イラクだった。第四章では、イラクにおける政治的勢力およびその他の中東地域がいかにこれに反応したのか、そしてイラクに埋蔵する石油の制御[機構]がいかに鍛え上げられたのかを検証する。結果として生じたイラクや他の中東地域での石油産業の構築は、民主的な政治要求を組織化する新たな可能性を開いた。それと同時に、新たなエネルギーの流れの分配と規模は、こうした要求を前に進めることをますます困難にするものでもあった。
「民主主義」という用語は、二つの種類の意味を持ちうる。共通の世界をより公正で平等主義的にするための効果的な要求の形成方法を指す場合もあれば、共通の世界を分割し、より大きな平等と公正への要求を制限する手段として人々の合意を用いる人口統治の方式を指す場合もある。そうした制限は、特定のエリアを人々の決定に委ねられるべき公的な関心事として認知する一方で、その他の領域を代替的な支配方法によって管理されるべきものとして確立することを通じて作られる。例えば政府の施策は、私有財産の規則によって治められる私的領域、自然の法則によって治められる自然界、経済の原理によって治められる市場という境界を確定することができる。民主主義のための闘争は、物事の切り分け[分配]をめぐる争いとなり、そこでは他の人々によって「私的である」(雇用者によって支払われる賃金の水準など)、「自然の事柄である」(天然資源の枯渇や大気中のガスの組成など)ないし「市場の法則に支配されている」(金融投機など)と主張される問題を、公的な関心事として確立することが目指される。20世紀の半ば、こうした「切り分けの論理」は、ある広大な統治の新領域を名指し、その規則を通じてオルタナティブな政治要求に制限をかけるようになった。すなわち、「経済」として知られるようになった領域だ。[17]
第五章では、20世紀中盤に新たな政治の対象物として経済が形成された過程を追跡する(大抵の説明は経済の出現を一世紀か二世紀前に位置づけているが、それは誤りだ)。そこではまた、急速にその量を増加させる低コストの炭素エネルギー(すなわち石油)の生産が、この[経済という]新たな政治的計算および民主主義的支配の方法にいかに寄与したのかが検証される。石炭時代の統治に特徴的な物質的計算の形態とは対照的に、潤沢な石油によって可能になったこの新たな計算方式は、限界のない経済成長という新奇な原理にもとづいて集合的な生活を管理する方法を切り開いた。経済成長の統御は、カーボン・デモクラシーを統治するための新たな種類の理性および規制方式を提供するものだった。
経済の形成が、物質的生活を国民国家のレベルで秩序付ける方法を提供したのに対して、戦間期の民主主義の危機の原因を作ったと多くの人が考えている力をそれによって統御することは不可能だった。すなわち、投機という運動によってヨーロッパの金融・政治システムの崩壊を引き起こした私的な多国籍資本の流れのことだ。ここでもまた、第二次大戦後、多国籍資本を制御する新たな方法の創出を引き受けることよって、その解決策を提供したのは石油だった。国民経済の形成につづいて第五章で追跡するのは国際的な金融メカニズムの構築であり、それは私的な多国籍銀行の脅威――20世紀の後半になって新たな規模で再出現することになる民主主義政治への脅威――を抑制するという意図を持っていた。新たな制御の機構は部分的に石油の流れの支配によって作動しており、中東が世界の石油の主たる供給源になりつつあったため、この地域をふたたび帝国主義的制御のもとで組織化することが、統治方式としての民主主義を西側において可能にするうえで重要なものとなった。アメリカ主導の「国際的信託統治」という形のもとに中東の石油を置こうとする戦後の試みは石油企業によって妨害され、「冷戦」というよりシンプルな枠組みで置き換えられることになった。特定のエリアを民主的要求の前進に不適切な領域と名指す切り分けの論理は、まさしくそうしたエリアとして中東を取り込んだのだ。
カーボン・デモクラシーについての私の説明は、石炭への依存に起因する脆弱性と効果的な平等主義的要求を行うこととのあいだの比較的シンプルな関係を追跡することから始まった。しかしながらこの本をこの部分まで書き進めることで、そこには複数の次元が付け加わり、石炭から増大する石油利用への転換、エネルギーの生産・分配のネットワークの飛躍的な拡大、潤沢な化石燃料により可能になった新たな集合的生活の形、そして石油生産にもとづいた物品流通と金融の急速な拡張といった事柄が反映されるようになった。
第六章では、ふたたびイラクおよびより広い中東地域に目を向け、1950年代および1960年代の国内の政治闘争が、いかに石油の支配をめぐる石油企業との闘争に変容したのかを検証する。OPEC[石油輸出国機構]の興隆の歴史と同様によく知られているのは、はじめは外国企業による石油生産に課される税率の制御を、つづいてそうした企業の所有権と操業の制御を、産油諸国が主張するにあたって、民族主義勢力の果たした役割だ。だがカーボン・デモクラシーという観点から見た場合、私たちはこの物語のいくつかの新しい側面を強調しなければならない。この章で追跡するのは、精製施設、パイプライン、海輸ルート、そしてそれらのサボタージュ[破壊工作]といったレベルでの石油をめぐる戦いである。そこで明らかにされるのは、イランをはじめとする産油諸国によるハイテク兵器の購入が、石油歳入を循環させるための独特な仕方で誂えられたメカニズムを提供した可能性があるということであり、「安全保障」という新たなドクトリンが武器の販売とセットであったということだ。そしてこのことが、中東における石油の問題を、西側における民主的な政治要求の新たな統御方法へと結びつけている。こうした展開が1973年-74年の危機につながったということは、第七章で明らかにされる。紛らわしくも単に「石油危機」と呼ばれているこの時期の中軸的な出来事には、国際金融、国民経済、そしてエネルギーの流れを統治する方式の変容もまた含まれていたのであり、それは西側で弱まりつつあるカーボン・デモクラシーを中東の石油諸国との新たな関係のなかに置きなおすものでもあった。アメリカ合衆国の産油諸国との関係の変化は同時に、集合的生活を民主的に統治する方法として「経済」を統御することに反対していた右派の政治勢力に対して、代替的な支配技術としての「市場」の法則を再導入・拡張する口実を与えた。それ[市場]は、共通の世界の一部を民主的な論争の手の届かない場所に置くためのより効率的な手段を提供するものだった。
1979年のイランでのイスラーム革命から2011年春のアラブの蜂起にいたるその後の30年のあいだに、中東に関する石油と民主主義をめぐる支配的な議論のなかに二つのテーマが加わった。一つはイスラーム主義による政治運動の興隆であり、それは多くの論者にとって、より民主的な政治形態を構築するうえでの障壁であるように映った。もう一つは、石油諸国を巻き込んだ軍事的暴力のレベルの増大――とりわけ、2003年のアメリカのイラク侵攻で頂点を迎えることになる湾岸での一連の戦争――である。この時期に関してよく読まれている研究は、その力学を資本のグローバル化する力と部族的・宗教的アイデンティティをもった狭量な勢力とのあいだの抗争、ないし「ジハード対マックワールド(Jihad vs McWorld)」[ベンジャミン・バーバ―による著作の題]として記述していた。第八章で提示するのは、石油・いわゆるグローバル化・政治的イスラームの力という三者のあいだの関係をまた別の仕方で考える筋道であり、そこでは「マックジハード(McJihad)」という概念が使用される。
最終章では、カーボン・デモクラシーのいくつかの現代的な限界に立ち返る。枯渇した油田を新たな発見で置き換えることがますます困難になり、新たに発見された埋蔵の開発がますます高価でエネルギー集約的になることで、潤沢で低コストの炭素エネルギーの時代が終わりを迎えることについて。そして、現存する民主主義政府の形態では惑星の長期的な未来をまもるのに必要な予防策を取ることがどうやらできないなかで加速しつつある、気候崩壊の脅威について。私は、こうした問題にまとわりついている技術的な不確かさによって特定の形態の合理化――経済的計算――が民主的討論の空間を埋め尽くすことが許されていることを明らかにし、この本で追及してきたカーボン・デモクラシーの社会=技術的な理解によって、私たちが集合的な未来を形作る際のこうした障壁をよりよく克服する方法が提供されるのだと主張する。
[1] 2010年には、最初に挙げた五つの国の石油生産高は、66万8000バレル/日(エジプト)から4万4000バレル/日(バハレーン)までの幅があった。八つの大きな産油国(アルジェリア、イラン、イラク、クウェート、リビア、サウジアラビア、そしてアラブ首長国連邦、+カタール)の生産高は、1051万バレル/日(サウジアラビア)から179万バレル/日(リビア)までの幅があった。カタールは石油の生産では143万バレル/日のみだったが、国民一人あたりの産出量としては最大であり、くわえて中東で二番目に大きな天然ガスの産出国でもあった。オマーン(86万9000バレル/日、2011年の政治的抗議は穏やか)は二つのグループのあいだにぴったり収まっていた。石油生産が最小限かゼロである五つの国々のうち、四つは石油政治よりもパレスチナ紛争によってその政治的力学が相互に連結されており(イスラエル/パレスチナ、ヨルダン、レバノン)、残りの一国は好況のリン産業という別の鉱物輸出に頼っている(モロッコ)。原油やその他の液体についての数字は、 www.eia.gov. から得た。
[2] レンティア国家に関する議論において石油の物質性が無視されるこうした傾向の重要な例外として、Fernando Coronil, The Magical State: Nature, Money and Modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press, 1997 が挙げられるが、そこでこの問題は、富の編成を理解する際のより広範な自然の抹消と結びつけられている。前石油期の政治構造に依拠し、「石油複合体」とそれが形成する「統治可能な空間」を論じたMichael Wattの議論(‘Resource Curse?’: Governmentality, Oil and Power in the Niger Delta, Nigeria’, Geopolitics 9, 2004: 50-80)、およびサウジアラビアの石油生産を組織化した労働者政権とそのイメージ形成に関するRobert Vitalisの検証(America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, 2nd edn, London: Verso, 2009)も参照せよ。
[3] Rory Stewart, Occupational Hazards: My Time Governing in Iraq, London: Picador, 2006:
[4] Mark Tessler and Amaney Jamal. ‘Political Attitude Research in the Arab World: Emerging Opportunities’, PS: Political Science and Politics 39: 3, 2006: 433-7.
[5] Ghassan Salamé, ed., Democracy Without Democrats, London: I. B. Tauris, 1994.
[6] Tessler and Jamal, ‘Political Attitude Research’.
[7] 以下を参照せよ。Bruno Latour, Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004; Lisa Disch ‘Representation as “Spokespersonship”: Bruno Latour’s Political Theory’, Parallax 14: 3, 2008: 88-100.
[8] Coronil, Magical State: 107.
[9] 結論部[最終章]を見よ。
[10] Vaclav Smil, Energy in Nature and Society: General Energetics of Complex Systems, Cambridge, MA: MIT Press, 2008: 204. 供給量の採掘が難しくなるにつれて化石エネルギーの生産に必要なエネルギー源が増大すること――EROI(投資したエネルギーの見返りに得られるエネルギー)の減少として知られている問題――については、同書275-280頁を参照せよ。
[11] Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, vol. 1, Theory of Practical Ensembles, London: Verso, 1977: 154.
[12] 最近に至るまで、石炭の埋蔵量のほうが石油よりもはるかに長持ちし、何百年にもわたって豊富な供給をもたらすと考えられていた。近年の研究は、石炭埋蔵の推定が石油のそれにも増して信頼ならないことを示唆している。アメリカ合衆国――最大の埋蔵量を有する国家だ――における生産はすでにピークを迎えて減少しはじめており、グローバルな生産も早ければ2025年にピークを迎える可能性がある。Werner Zittel and Jörg Schindler, ‘Coal: Resources and Future Production’, EWG Paper no. 1/01, 10 July 2007, available at www.energywatchgroup.org.
[13] R. Revelle, W. Broecker, H. Craig, C. D. Keeling and J. Smagorinsky, ‘Atmospheric Carbon Dioxide’, in Restoring the Quality of Our Environment: Report of the Environmental Pollution Panel, Washington: White House, President’s Science Advisory Committee, November 1965: 126-7.
[14] Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report, 2007, available at www.ipcc.ch. ジェイムズ・ハンセンと彼の同僚が行った古気候学の研究が示唆しているのは、氷の融解におけるフィードバックの連鎖が、地上氷河の喪失の急速な加速を引き起こし、激変的な帰結を潜在的にともなうはるかに極端な気候変動を生み出すかもしれないということだ。こうした発見からすれば、IPCCの暗澹たる警告さえ馬鹿々々しいほど楽観的なものに映る。James Hansen, Makiko Sato, Pushker Kharecha, Gary Russell, David. W. Lea and Mark Siddall, ‘Climate Change and Trace Gases’, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 365, 2007: 1,925-54.
[15] Elmer Altvaterはこれらの双子の危機について明快な説明を提示するだけにはとどまらず、それらが資本主義の論理と化石エネルギーの物質的特性とが「一致」した時代の終わりを意味しているのだと示唆している(‘The Social and Natural Environment of Fossil Capitalism’, Socialist Register 43, 2007: 37-59)。私はこれからの数章で化石燃料の物質的特性についてまた別の説明を提示する――例えば、石油の輸送可能性は石炭のそれとは非常に違ったものだ――が、それは一連の不変の「論理」を持った歴史的プロセスとしての資本主義という考えとはなかなか適合しない。
[16] Gavin Bridgeは、産油国および資源の呪いへの排他的な焦点化から注意を逸らし、生産・精製・分配から現在の炭素回収・貯留やカーボン・クレジット取引への関与まで、石油の関わる企業の多様なネットワークに目を向けている。それらのいずれもが、別々の政府によって統治されているものでありうる。‘Global Production Networks and the Extractive Sector: Governing Resource-Based Development’, Journal of Economic Geography 8, 2008: 389-419. 翻訳の社会学、および「拘束的な通過ポイントobligatory passage points」については、Michel Callon, ‘Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay’, in John Law, ed., Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?, London: Routledge, 1986 を参照せよ。
[17] 公的な物事とそうでない物事を名指す切り分けの論理に対する戦いとして民主的闘争を議論しているものとして、Jacques Rancière, Hatred of Democracy, London: Verso, 2006 を参照せよ。
翻訳:中村峻太郎
©Verso 2013, Reprinted with permission by the Author.
使用画像:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq,_oil_fields,_drilling_tower_LOC_matpc.13163.tif