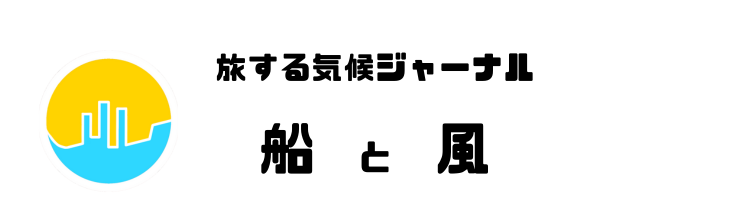パレスチナを枠づける:イスラエル、湾岸諸国、中東におけるアメリカ権力
アーダム・ハニーヤ
トランスナショナル研究所、2024年6月13日
原文リンク:https://www.tni.org/en/article/framing-palesti
過去七か月以上にわたって、イスラエルによるガザでのジェノサイド戦争は、前例のないグローバルな抗議と、パレスチナをめぐる意識化の波を生み出してきた。何百万もの人々が路上に繰り出し、連帯キャンプは世界中の大学に広がり、勇敢な活動家たちが港湾や軍需工場を封鎖し、イスラエルに対するボイコット・投資撤退・経済制裁(BDS)のグローバルなキャンペーンがかつてなく必要とされているという認識が深く根付いている。南アフリカによる国際司法裁判所(ICJ)でのイスラエルに対する訴訟が非常に大きな注目を集め、こうした民衆的運動の力強さを後押しした――その訴訟は、単にイスラエルによるジェノサイドの現実だけではなく、ガザ地区をはじめとするイスラエルの行為を可能にしている主導的な西側国家の頑迷さをも力強く強調するものだった。
しかし、パレスチナとの連帯がグローバルな高まりをみせているにもかかわらず、パレスチナが一般に議論され枠づけられる際には、いくつかの誤った考えがいまだに存在している。 あまりにしばしば、パレスチナの政治は単にイスラエル、西岸、ガザというレンズを通して眺められ、中東のより広い地域的なダイナミクスや、イスラエルのセトラー・コロニアリズム(入植型植民地主義)が作動するグローバルな文脈が無視されてしまう。それに関連して、パレスチナとの連帯はしばしば、イスラエルによる大規模な人権の蹂躙や進行中の国際法侵犯――パレスチナの人々が八十年近くにわたって経験してきた殺害、逮捕、財産収奪――に問題を切り詰めてしまう。こうした人権による枠づけの問題点は、パレスチナの人々の闘争を脱政治化してしまうことであり、なぜ西側の諸国家がかくも明確にイスラエルを支援しつづけているのかを説明できないことだ。そして西側による支援に関するこの決定的に重要な疑問が持ち上がると、多くの人が北アメリカとヨーロッパで活動する「親イスラエル・ロビー」をその要因として指摘する――これは誤りであると同時に政治的に危険な見方であり、西側国家とイスラエルの関係を根本的に見誤ってしまうものだ。
この論考での私の目標は、パレスチナを理解するためのオルタナティブなアプローチを提示することだ。そのアプローチとは、より広い地域によって、そして私たちの化石燃料中心の世界で中東が占める中心的な位置によって枠づけられたものだ。私の主要な議論は、アメリカと主導的なヨーロッパ諸国による惜しみない支援をこうした枠組みから離れて理解することは不可能だというものだ。入植型植民地であるイスラエルは、西側の帝国的な利害――とりわけアメリカ合衆国の――を中東において維持するうえで決定的に重要だった。イスラエルは、 アメリカによる中東地域支配のもう一つの主たる柱――石油の豊富な湾岸アラブ君主国、とりわけサウジアラビア――とともに、その役割を演じた。湾岸、イスラエル、アメリカとのあいだで急発展する関係は、とりわけアメリカのグローバルな権力が比較的弱まっている以上、現在の状況を理解するうえで欠かすことができないものだ。
戦後改革と中東
第二次世界大戦直後の数年間の世界秩序の変化を規定したのは、二つの主要なグローバルな転換だった。一つ目は、世界のエネルギー体制における革命だ。石油が世界のもっとも重要な化石燃料として登場し、主導的な産業化された経済のいたるところで石炭やその他のエネルギー源に取ってかわった。こうした化石燃料の移行はまずアメリカで生じ、そこでは1950年に石油の消費が石炭を追い越した。そして1960年代に西ヨーロッパと日本があとに続く。経済協力開発機構(OECD)に代表される富裕な諸国家の合計では、1950年にはトータルの化石燃料消費に占める石油の割合は28%に満たなかったが、1960年代の終わりまでに石油は過半数のシェアを占めるようになった。エネルギー密度が高く、化学的な柔軟性を持ち、輸送が容易であった石油は、急成長する戦後の資本主義の動力となり、一連の新たな技術、産業、インフラの基盤となった。これがのちに科学者たちが「大いなる加速」――二十世紀半ばに始まる大規模かつ継続的な化石燃料消費の拡大であり、それが今日の気候の非常事態に否定しがたく繋がっている――と言いあらわすものの端緒となった。
石油へのグローバルな移行は、第二の主要な戦後の改革と密接に結びついていた。すなわち、主導的な経済的・政治的権力としてのアメリカの立場の強化と。アメリカの経済的興隆は二十世紀の早い時期から始まっていたけれども、グローバルな資本主義のもっともダイナミックな作用力としてのアメリカがはっきりと姿を見せたのは第二次世界大戦時であり、それに敵対するのはソビエト連邦とその同盟国のみだった。アメリカ権力の増大は戦時中の西ヨーロッパの破壊を土台としており、いわゆる第三世界の大部分に対するヨーロッパの植民地支配の弱まりとも結びついていた。イギリスとフランスの勢いが弱まるなか、アメリカが戦後の政治と経済の土台骨を形成するうえで主導権を握り、そこにはアメリカ・ドルを中心とした新たなグローバルな金融システムも含まれていた。1950年代半ばまでに、アメリカは世界の生産高の60%のシェアを抱え、グローバルなGDPの四分の一を超えた。そして、世界の工業企業のトップ50社のうち42社がアメリカ企業だった。
これら二つのグローバルな移行――石油への移行とアメリカの権力の上昇――は、中東にとって深甚な意味を持っていた。一方では、中東はグローバルな石油への転換において決定的な役割を演じた。この地域は豊富な石油供給を有しており、その量は1950年代半ばまでに、確認されていた世界の埋蔵量の40%近くに達していた。中東の石油はまた、多くのヨーロッパ諸国の近くに位置しており、生産コストは、世界の他のどの場所での石油生産コストよりもはるかに低かった。見たところ無尽蔵の量をもつ低コストの中東の石油は、したがって石炭よりも安い価格でヨーロッパに供給することができ、そうすることでアメリカ国内の石油市場は、増大するヨーロッパの需要の影響から遮断されたままでいることが保障された。 ヨーロッパへの石油供給を、中東に再中心化することは、驚くほど急速なプロセスだった。1947年から1960年にかけて、中東に由来するヨーロッパの石油のシェアは倍増し、43%から85%に増大した。これによって新たな産業(石油化学のような)の出現が可能になっただけではなく、新たな形態の輸送や戦争遂行もまた可能になった。実際のところ、中東がなければ、西ヨーロッパでの石油への移行は決して生じていなかっただろう。
中東の石油埋蔵の大半は、湾岸地域――とりわけサウジアラビアと比較的小さな湾岸アラブ諸国、ならびにイランとイラク——に集中している。二十世紀の前半を通して、これらの国々はイギリスの支援を受けた専制的な君主によって支配されていた(名目上イギリスの植民地主義からは独立していたサウジアラビアは除く)。この地域での石油生産は一握りの西側の大石油企業によって管理されており、そうした企業はこうした国々の支配者にレントや油田使用料を支払うことで石油を採掘する権利を得ていた。こうした石油企業は垂直的に統合されており、そのことは、企業が単に原油の採掘だけではなく、精製、輸送、世界中での石油販売もまた管理することを意味していた。こうした企業の権力は絶大なものであり、石油を循環させるインフラ群を管理することで、潜在的な競争相手を排除することができた。石油産業における所有権の集中は、かつて別の産業でみられたものをはるかに凌駕していた。実際のところ、第二次世界大戦の終了時には、アメリカとソ連以外の世界の石油埋蔵の80%以上が、たった七つのアメリカおよびヨーロッパの大企業によって管理されていた――いわゆる「セブン・シスターズ」によって。[1]
イスラエルと反植民地蜂起
1950 年代と1960年代を通じて中東が世界の石油市場の中心地になったことで巨大な権力を手にしたにもかかわらず、こうした石油企業は大きな問題に直面していた。世界中のほかの場所で起こっていたように、一連の強力な民族主義、共産主義、その他の左翼による運動が、イギリスとフランスの植民地主義をバックにした支配者たちに異議を申し立て、注意深く構築されていた地域の秩序をいままさに転覆しようとしていたのだ。これをもっとも鋭く経験したのはエジプトであり、 イギリスの支援をうけた君主であるファールーク王[一世]は、人気のあった軍人ガマール・アブドゥル=ナーセル(Gamal Abdel Nasser)が主導した1952年の軍事クーデターによって追放された。ナーセルが権力についたことでイギリス軍は撤退を余儀なくされ、そのことが1956年のスーダンの独立成功につながった。エジプトが新たに獲得した主権は、イギリスとフランスが管理していたスエズ運河の1956年の国有化で頂点を迎える――この行為は中東全体の何百万という人々に歓迎され、イギリス、フランス、イスラエルによるエジプト侵攻を招いた(そしてそれは失敗した)。ナーセルがこうした歩みを行うなかで、中東のほかの場所――もっとも著しいのはアルジェリアだった――でも反植民地闘争が拡大し、1954年にフランスの占領に対して、独立を求めるゲリラ戦が開始された。
今日しばしば見過ごされていることだが、こうした長年にわたる植民地支配に対する脅威は、湾岸の産油諸国でも同じように感じ取られていた。サウジアラビアやより小規模な君主国でも、ナーセルへの支持が盛り上がり、さまざまな左翼運動が、[金銭上の]無節操、政治的腐敗、そして支配君主の西側寄りの立場に対して、抗議を行った。こうしたことの潜在的な帰結は、近隣のイランで可視化されていた。そこでは人気のある民族リーダーのモハンマド・モサッデク(Mohammed Mossadegh)が、1951年に権力の座に就いていたのだ。モサッデクの最初の行動のひとつは、イギリスが管理していた石油企業アングロ・イラニアン石油会社(今日のBPの先駆け)を買い取ることであり、それが中東ではじめての石油の国有化となった。この国有化は近隣のアラブ諸国で強い反響を呼び、一般的な反植民地のムードのなか、「アラブの人々にアラブの石油を」というスローガンが広く人口に膾炙した。
イランの石油国有化をうけて、アメリカとイギリスの情報局は1953年にモサッデクに対するクーデターを指揮し、イランの君主モハンマド・レザー・シャー・パフラヴィー(Mohammad Reza Shah Pahlavi)に忠実な親・西側の政府を政権につけた。このクーデターは、中東全体でのラディカルな運動や民族主義的な運動に向けられた継続的な反・革命の波の開始を告げる号砲となった。モサッデク政権の転覆は、地域の秩序が大きく転換したこともまた明瞭に示すものだった。イギリスもクーデターのなかで重要な役割を果たしたけれど、作戦の計画と実行の主導権を握ったのはアメリカだった。アメリカ政府が戦時期以外で外国の支配者を追い落としたのはこれが初めてであり、CIAのクーデターへの関与は、1954年のグアテマラのクーデターから1973年のチリのサルバドール・アジェンデ政権の転覆まで、のちのアメリカによる介入の重要な露払いとなった。
こうした文脈のなかで、イスラエルは中東地域でのアメリカの利害を守る主要な防波堤として立ち現れたのである。二十世紀の初期には、イギリスがシオニズムによるパレスチナの植民地化の第一の支援者であり、1948年のイスラエル建国以後、英国はシオニズムの国家建設プロジェクトの支援を継続した。しかし戦後にアメリカがイギリスとフランスの植民地支配にとってかわると、アメリカによるイスラエルの支援は、新たな地域の安全保障秩序のくさびとなった。鍵となる転換点は、イスラエルと主導的なアラブ諸国とのあいだの1967年の戦争であり、そこでイスラエル軍はエジプトとシリアの空軍を破壊し、西岸およびガザ地区、(エジプトの)シナイ半島、(シリアの)ゴラン高原を占領した。イスラエルの勝利によって、ナーセルのエジプトでもっとも鋭く結晶化したような、アラブ統一、民族独立、そして反植民地抵抗の運動は粉砕された。それは同時に、イギリスに代わってイスラエルの第一の保護者になるよう、アメリカを励ますものでもあった。その時期以降、アメリカは毎年、何十億ドル相当の軍事兵器や財政支援をイスラエルに提供するようになる。
セトラー・コロニアリズムの重要性
1967年の戦争は、イスラエルが強力な勢力であり、それは中東におけるアメリカの利害に対するあらゆる脅威に対して用いることができるということを証明した。しかしここには、しばしば注目されないままになっている決定的に重要な次元が存在している。アメリカ権力を支えるイスラエルの空間的位置は、パレスチナの住民に対する継続的な収奪に基づいた、入植型植民地であるという、内的な特性と直接的に結びついたものだった。入植型植民地は、人種的な抑圧、階級による搾取、そして収奪という構造を強化し、固定化するという継続的なはたらきを有している。結果として、そうした植民地は概して、高度に軍事化された暴力的な社会――外部からの支援に依存する傾向にある――であり、それ[軍事化と暴力]によって、敵対的な地域環境のなかでみずからの特権を維持することが可能になるのである。そうした社会では、住民のうちのかなりの割合が先住民の人々に対する抑圧から利益を得ており、人種化された、軍事主義的な意味合いのなかでみずからの特権を理解している。こうした理由で、入植型植民地は西洋の帝国的利害にとって、「通常の」従属国家よりもはるかに頼りになるパートナーとなるのである。[2] これこそが、イギリス植民地主義が二十世紀前半に政治運動としてのシオニズムを支持した理由であり――アメリカが1967年以後の時機にイスラエルを大事にした理由なのだ。
もちろん、これはアメリカがイスラエルを「コントロール」していることを意味するわけではないし、関係維持の仕方について、アメリカ政府とイスラエル政府のあいだに意見の相違がまったくないわけでもない。しかし、イスラエルが永続的な戦争状態、戦争、抑圧を維持する能力は、もしアメリカによる継続的な後方支援がなかったならば、著しい危険にさらされていただろう(物質的にも政治的にも)。反対に、イスラエルもまた忠実なパートナーとして、中東でのアメリカの利害に対する脅威への防波堤として機能している。イスラエルはこれまで、世界中のアメリカをバックにした抑圧的政権を支えるため、グローバルに行動してきた――アパルトヘイト期の南アフリカから、ラテンアメリカの軍事独裁政権まで。リチャード・ニクソン政権時[1969-1974年]のアメリカ国務長官であったアレクサンダー・ヘイグは、かつてぬけぬけとこう述べた。「イスラエルは、決して沈まない、世界で最大のアメリカの航空母艦であり、アメリカの兵士は一人も乗りこんでいないが、アメリカの国家安全保障にとってきわめて重要な位置についている」。[3]
イスラエル国家の内部的な性質とそれがアメリカ権力にしめる特異な位置とのつながりは、南アフリカのアパルトヘイトがアフリカ大陸全体をめぐる西側の利害関係にとって果たした役割と似たものがある。同じ入植型植民地としての南アフリカとイスラエルとのあいだには重要な違いがあるが――とりわけ、(イスラエル国内のパレスチナ人とは異なり)南アフリカの黒人人口は同国の労働者階級において多数派を占めていた――、どちらの国もそれぞれの近隣地域における西側の列強国の核となる組織化の中央として機能するようになった。南アフリカのアパルトヘイトへの西側の支援の歴史を詳しく調べると、今日のイスラエルのケースで用いられているのと同じ種類の正当化をいくつも目にすることになる(国際的な制裁を防止し、抗議運動を犯罪化する試みも同じ種類のものだ)。こうした平行関係は、特定の諸個人の役割にまで拡張される。このことのほとんど知られていない一例は、1989年に英国保守党の若い党員が行った南アメリカへの旅であり、その旅のなかで彼は南アフリカに対する国際的な制裁に異論を唱え、イギリスがそのアパルトヘイト政権を支持しつづけるべきだとする理由を並べ立てた。数十年後、その若いトーリー党員デヴィッド・キャメロン(David Cameron)は、いまやイギリスの外務大臣の地位を占めており――イスラエルによるガザでのジェノサイドを応援し鼓舞している世界の指導者たちの中心的な一員となっている。
中東がグローバルな石油経済の中心地であることによって、イスラエルが帝国権力[列強国]のなかに占める位置は、アパルトヘイト下の南アフリカがそうであったよりも決然としたものになっている。しかしどちらのケースも、国内における入植型植民地の階級的・人種的力学が、地域的ないしグローバルな諸要因がいかに交差しているのかを考えることの重要性を明白に示している。
イスラエルの中東への経済的統合
1970年代から1980年代にかけて、中東地域(とその他の地域)の大半で原油埋蔵の国有化が起こると、アメリカ権力にとっての中東の重要性ははるかに大きなものになった。国有化によって、中東の原油供給に対する長年にわたる西側の直接的管理は終わりを迎えた(アメリカとヨーロッパの企業は、引き続きグローバルな精製・輸送・石油販売の大半の部分を管理していたけれども)。こうした文脈のなか、中東でのアメリカの利害が何を中心にして展開したかといえば、(米ドル建てである)世界市場への安定的な石油供給を保障することであり、石油がアメリカ中心のグローバル体制を不安定化させるための「武器」として用いられるのを防止することだった。さらに、湾岸の産油国がいまや原油の輸出で何兆[ドル]もの稼ぎをあげるなかで、こうしたいわゆる石油ドル(petrodollars)がグローバルな金融システムのなかを循環するようになることにも、アメリカは深い関心を抱くようになった――アメリカのドルの支配に直接的な影響をもたらす事柄だからだ。
こうした利害を追求するなかで、アメリカの戦略は、鍵となる地域の同盟国として、サウジアラビアをリーダーとした湾岸君主国の生き残りにフルに焦点を当てるようになった。これは、1953年のクーデター以来アメリカの湾岸での利害のもうひとつの頼みの綱であったイランで、1979年にパフラヴィー朝が倒れて以降、とりわけ重要なものとなった。アメリカの湾岸君主国への支援は、さまざまな方法で表明された――大量の軍事兵器の販売によって湾岸は世界で最大の武器市場へと変貌し、経済的イニシアティブによって湾岸の石油ドルの富はアメリカの金融市場へと流し込まれ、永続的なアメリカ軍の駐留によって君主による支配の最終的な保障が形成しつづけられた。アメリカ・湾岸関係の中枢的な瞬間が、イラン・イラク戦争とともに訪れたが、その戦争は1980年から1988年まで継続し、二十世紀のもっとも破壊的な紛争のひとつに数えられている(最大で50万の人々が非業の死を遂げた)。この戦争のあいだ、アメリカは双方に武器、資金、機密情報を提供し、そのことを、これら二つの近接する大国から力を搾り取り、湾岸君主国の安全を引き続き確保するためのひとつの方法と考えていた。
このようにして、中東におけるアメリカの戦略は二つの核となる柱に依拠するようになった。ひとつはイスラエルであり、もうひとつは湾岸君主国だ。これら二つの柱は、今日でも中東地域におけるアメリカ権力の核心でありつづけている――しかしながら、両者のあいだの関係には決定的な転換が生じてきた。1990年代初頭、アメリカ政府は――ヨルダンやエジプトのようなその他の重要なアラブ諸国とともに――これら二つの戦略上の極を結び合わせ、アメリカの経済・政治権力と結びついた単一の領域へと統合しようとした(その試みは現在まで続いている)。これを実現するためには、イスラエルはより広い中東のなかへと統合される必要があった――アラブ諸国との関係(経済的、政治的、外交的な)を正常化することによって。なによりも重要なのは、これが何十年も存在していたアラブ諸国によるイスラエルへの公式のボイコットが除去されることを意味していた点だ。
イスラエルの側から見れば、正常化は単に自国とアラブ諸国との貿易(およびアラブ諸国への投資)を可能にするものではなかった。1980年代半ばの大きな景気後退ののち、イスラエル経済は建設や農業といった部門からシフトし、ハイテク、金融、そして武器輸出などにはるかに重い力点を置くようになった。しかし主導的な国際企業のなかには、イスラエル企業との取引(ないしイスラエル国内での営業)に躊躇するものも少なくなかった。アラブの諸政府によって二次的ボイコットが課されていたからだ。[4] こうしたボイコットをやめさせることは、西側の大企業をイスラエルへと引き込むためにも、またイスラエル企業がアメリカその他の外国市場にアクセスするためにも、欠かすことができないものだった。言い換えれば、経済的な正常化で問題になっていたのは、イスラエルが中東の市場にアクセスできるようになることだけではなく、同時にイスラエルの資本主義がグローバル経済のなかに場所を占めることの保証でもあったのである。
この目的のために、アメリカ(およびヨーロッパの同盟国)は1990年代以降さまざまなメカニズムを導入し、イスラエルのより広い中東地域への経済的統合を推し進めようとした。そのひとつは、経済改革を深化させることだった――外国への投資と貿易の流れが中東地域全体に急拡大する端緒が開かれたのだ。その一環として、アメリカは一連の経済イニシアティブを提案し、イスラエルとアラブの市場をたがいに(そしてその後はアメリカ経済に)結びつけようとした。鍵となるスキームのひとつは、いわゆる資格産業区域(Qualifying Industrial Zones:QIZs)――1990年代後半にヨルダンとエジプトに設立された低賃金の製造業区域――である。資格産業区域(QIZs)のなかで生産された製品(ほとんどが繊維類と衣類)は、イスラエルに由来する生産要素が一定の割合で製造に用いられている場合、関税なしでアメリカに輸出することができた。イスラエル、ヨルダン、エジプトの資本を共同所有という構造で糾合する――二つのアラブ国家と隣国イスラエルとのあいだの経済関係を正常化する――うえで、QIZsは初動において決定的な役割を果たした。2007年時点でのアメリカ政府による報告では、ヨルダンのアメリカへの輸出のうちの70%以上がQIZsに由来しており、エジプトに関しては、2008年のアメリカへの輸出のうちの30%がQIZsで生産されたものだった。[5]
資格産業区域(QIZ)のプログラムとならんで、アメリカはまた2003年に中東自由貿易エリア(Middle East Free Trade Area:MEFTA)を提案した。MEFTAは2013年までに中東地域全体に張り巡らされた自由貿易ゾーンの確立を目指したものだった。アメリカの戦略は、累進的な六段階プロセスを用いて「友好的」な国々とのあいだで個別に交渉を行い、最終的にそのプロセスをアメリカと当該国とのあいだの完全な自由貿易協定(FTA)に持ち込むというものだった。こうしたFTAは、各国がアメリカと自国とのあいだの二国間FTAを別の国との二国間FTAに連結できるように設計されており、したがって中東全体で亜地域レベルの協定を立ち上げるものだった。こうした亜地域協定は、地域全体をカバーするまで、時間をかけて結び合わせることができた。重要なのは、これら複数の自由貿易協定(FTA)が、イスラエルの中東市場への統合を促す目的で使用されるようになったことだ。それぞれの協定には、協定国がイスラエルとの関係を正常化することを義務化し、貿易関係のあらゆるボイコットを禁止する条項が含まれていたからだ。アメリカは2013年にMEFTAを確立するという目標には失敗したが、この政策は中東地域でのアメリカの経済的影響力を拡大させ、さらにその土台として、イスラエルと主要なアラブ諸国とのあいだの関係を正常化させることにも成功した。今日アメリカは世界中の国々とのあいだで14の自由貿易協定(FTA)を有しているが、目を引くことに、そのうちの五つは中東の国々とのあいだで結ばれたものなのだ(イスラエル、バハレーン、モロッコ、ヨルダン、オマーン)。
オスロ合意
しかしながら、経済的な正常化が成功するかどうかは、政治的な状況が変化し、それによってイスラエルのより広い中東地域への経済的統合に対してパレスチナの人々の「青信号」が出されるかどうかに、最終的にはかかっていた。ここでの鍵となる転換は、オスロ合意だった。アメリカ政府の後援のもと、1993年にホワイトハウスの芝生で調印されたイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)とのあいだの協定だ。オスロ合意は、それまでの数十年間をかけて確立された植民地主義の実践に、重度に立脚したものだった。1970年代以来、イスラエルは西岸とガザ地区をみずから行政管理するパレスチナ人の勢力を見つけ出す試みを行ってきた――イスラエルの占領をパレスチナ人に代理させることで、パレスチナの人々とイスラエル軍のあいだの日常的な接触は最小化されうるだろう[という思惑によって]。こうした初期の試みは第一次インティファーダ――1987年に(ガザ地区で)始まった大規模は民衆蜂起――のあいだに崩壊した。そして第一次インティファーダに終わりをもたらしたのが、オスロ合意だった。
オスロ合意下で、PLOは新たな政治体――パレスチナ自治政府(PA)と呼ばれる――を構成することに同意し、それには西岸とガザ地区の断片化したエリアでの限定的な権力が与えられることになっていた。パレスチナ自治政府は、その存続のために外部の資金に完全に依存するものだった――とりわけ貸付、援助、そしてイスラエルによって徴税されその後自治政府(PA)に付託される輸入税に。こうした資金源の大半は、突き詰めれば西側諸国とイスラエルに由来するものであったため、自治政府(PA)はすぐさま政治的な従属状態におちいった。くわえて、イスラエルはパレスチナの経済と資源、そして人々と物品の運動への完全な統制を保持していた。2007年にガザと西岸とに領土が分割されると、自治政府は西岸のラマッラーに本部を設置した。現在、自治政府の長はマフムード・アッバース(Mahmoud Abbas)である。[6]
一般にはそのように提示されているにもかかわらず、オスロ合意とそれに続く交渉は、平和とも、パレスチナの自由への道とも、一切何の関係もない。イスラエルの入植地が西岸で爆発的に拡大したのも、アパルトヘイトの壁が建設されたのも、現在のパレスチナ人の生活を支配している綿密な移動制限が出来上がったのも、オスロ合意のもとでのことだ。オスロ合意が何に役立ったのかといえば、パレスチナの人口の重要な部分――難民とイスラエル内のパレスチナ人市民――を政治闘争の外側に放り出すことであり、パレスチナ問題を、西岸とガザ地区の領土の細片をめぐる交渉へと切り詰めることだった。オスロ合意のもっとも重要な成果は、より広い中東地域へのイスラエルの統合に対して、パレスチナ人の是認を提供したことだ。アラブの諸政府――ヨルダンとエジプトを首領とする――が、アメリカの傘のもとでイスラエルとの関係を恭々しく正常化する道を切り開いたのだ。
現在ガザを取り囲んでいる移動制限、障壁、検問所、軍事的緩衝地帯が出現したのはオスロ合意以後のことだ。その意味では、今日のガザの野外監獄は、それ自体がオスロ合意のプロセスによる創造物であることになる。オスロでの交渉と今日私たちが目撃しているジェノサイドのあいだには、それらを直接に結びつける一本の糸が存在しているのだ。ありうる紛争後(post-war)のシナリオについて進行している現在の議論を考える際、このことを銘記しておくことは決定的に重要だ。イスラエルの戦略には極端な暴力の断続的な使用がつねに含まれていたが、それは国際的支持を受けた交渉による偽物の約束と一対の組になったものだったのだ。これら一対の道具は同一のプロセスの一部であり、パレスチナの人々に対する継続的な断片化と収奪を再強化するために働くものだ。アメリカが舵をとった戦後の交渉は、それがいかなるものであれ、パレスチナ人の生命と土地を引き続きイスラエルが支配することを確実にする似たり寄ったりの試みが、そこで間違いなく見られることになる。
考えを前に進める
アメリカのグローバル権力において、石油の豊富な中東が戦略的中心を占めていることを考えれば、イスラエルが、一人当たりのGDPで見れば世界で13番目に富裕な経済であるにもかかわらず(イギリス、ドイツ、日本よりも上位だ)、なぜ累積で世界最大のアメリカの外国援助受領国であるのかも説明がつく。それはまた、アメリカ(およびイギリス)における二党体制[民主党/共和党(保守党/労働党)]でのイスラエル支援の理由も説明する。実際2021年に――トランプ大統領時代で、現在の戦争がはじまる以前――イスラエルは、世界のほかのすべての国を合わせたよりも多くの額のアメリカの海外軍事融資を受け取った。そして決定的に重要なことだが、この八か月間で明白になったように、アメリカによる支援は、財政的・物質的な支援をはるかに超えたものであり、アメリカは世界の舞台でイスラエルを政治的に防衛するうえで、最後のバックネットとして機能している。[7]
見てきたように、こうしたアメリカのイスラエルとの同盟関係は、パレスチナの人々からの[土地や財産の]収奪とたまたま同時に生じているわけではなく、まさにそのなかにこそ根拠をもっているのである。アメリカが中東全土で権力を強化するなかでイスラエルがかくも破格の役割を演じたのは、その入植型植民地としての性質ゆえだ。そしてこれこそが、中東全体――いまや世界でもっとも社会的に極分化し、経済的な不均衡を有し、紛争の被害を受けている地域――での政治的変化を推し進めるうえで、パレスチナの闘争がかくも核心的な部分であることの理由だ。そして逆に、だからこそパレスチナのための闘争は、中東地域でのその他の進歩的な社会闘争の成功(および失敗)と緊密に結び合わされている。
こうした地域内部のダイナミクスの中心的な軸は、依然としてイスラエルと湾岸諸国のあいだのつながりだ。オスロ合意につづく二十年間、アメリカの中東戦略は、イスラエルと湾岸諸国との経済的・政治的統合を強調しつづけることだった。このプロセスにおける主要な前進は2020年のアブラハム合意(Abraham Accords)によって生じたが、そこではアラブ首長国連邦(UAE)とバハレーンが、イスラエルとの関係を正常化することに同意した。アブラハム合意が道を舗装したことで、2022年にはUAE・イスラエル間のFTAが締結され、それはイスラエルがアラブ国家とのあいだで初めて結んだFTAとなった。2020年にはたったの1億5000万ドルだったイスラエル・UAE間の貿易額は、2022年に25億ドルを越えた。スーダンとモロッコも似たような合意に到達したが、それはアメリカによる強い誘導によって前進したものだ。[8]
アブラハム合意によって、現在五つのアラブ諸国がイスラエルと公式の外交関係を有している。これらの国々を合わせた人口は、アラブ世界全体のおよそ40%にあたり、そこには中東の政治・経済における主導的国家も含まれている。しかし決定的な問いは依然として残っている――これらのクラブに、サウジアラビアはいつ加わるのだろうか? サウジアラビアの承諾がなければUAEとバハレーンがアブラハム合意に賛同することはありえなかっただろうけれども、サウジ王室はこれまでのところ、イスラエルとのつながりを公式に正常化していない――ここ数年間、この二つの国家のあいだの会合や非公式のつながりは過剰なほどであったけれども。
現在のジェノサイドのただなかで、サウジアラビアとイスラエルの関係正常化の取引がアメリカによる戦後情勢の計画にとっての主要な目標であることは、疑問の余地がない。もしラマッラーのパレスチナ自治政府からなんらかのゴーサインを受け取ったならば(ひょっとすると、西岸におかれたパレスチナ人の疑似的国家の国際的承認と結びつける形で)、サウジアラビア政府がそのような結果に合意する可能性は非常に高い――そしてそのことはおそらく、バイデン政権にとっても大きな含意を持ってきた。このシナリオには、明らかに重大な障害が存在している。ガザのパレスチナ人たちは降伏を拒絶しつづけており、戦争が終わったあとでガザがどのように行政管理されることになるのかも未決定だから。しかし、主要な正常化国――UAE、エジプト、モロッコ――をリーダーとした多国籍のアラブ勢力がガザ地区をコントロールするという現在のアメリカのプランは、サウジ・イスラエル間の関係正常化へと繋げられる可能性がある。
鋭い敵対関係や地政的な緊張がグローバルな規模で(とりわけ中国とのあいだで)生じてきていることを考えれば、中東におけるアメリカの利害にとって、湾岸諸国とイスラエルとを結びつけることがますます重要なものになってきている。アメリカの中東での優位性を奪いとる準備のできた「大国」は他に存在しないけれども、近年、地域全体でのアメリカの政治的・経済的・軍事的な影響力は、比較的に減少してきた。このことのひとつの兆候は、湾岸諸国と中国/東アジアのあいだで相互依存関係が増大していることであり、それはいまや中東の原油輸出だけにはとどまらない。こうした文脈のなかでは――そしてアメリカ権力のうちにイスラエルが占める長期的な地位を考えれば――、アメリカ国家が舵をとる正常化プロセスは、それがどのようなものであれ、中東でのアメリカの首位性を再主張するものになり、潜在的には、その地域での中国の影響力に対する決定的に重要な梃子として機能するようになるだろう。
それでも、戦後のシナリオに関する現在進行形の議論にもかかわらず、これまでの76年間は、パレスチナの人々の堅固さ[その場を動かないこと]と抵抗を永久に消し去ろうとする試みは失敗することを、繰り返し証明してきた。パレスチナは現在、1960年代以来目にしたことがないほどのグローバルな政治的目覚めの、先端部に位置している。現在パレスチナの状況に対する意識が高まっているなかで、私たちの分析は、ガザ地区でのイスラエルによる残虐行為への当座的な反対を超え出ていかなければならない。中東における帝国的利害への効果的な異議申し立ては、いかなるものであれ、パレスチナ解放のための闘争がその中心部に位置しており、私たちの運動は、こうしたより広域的なダイナミクスをより良く究明しなければならない――とりわけ湾岸君主国の中軸的な役割を。私たちにはまた、化石資本主義(fossil capitalism)の歴史において、そして現在の気候正義のための闘争において、中東がどのような位置を占めているのかをより深く理解しなければならない。パレスチナ問題を、これらの現実から分離することはできないのだ。この意味で、パレスチナの人々が現在ガザ地区で行っている生存のための法外な戦いは、惑星の未来のための闘いの最先端の断面をあらわしている。
アーダム・ハニーヤAdam Hanieh は、トランスナショナル研究所のリサーチフェローであり、エクセター大学アラブ・イスラーム研究所の政治経済学・グローバル開発学の教授。彼の最新刊『原油資本主義:石油、企業権力、世界市場の形成 Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market』は2024年9月にVerso Booksから刊行される。
翻訳:中村峻太郎
©Transnational Institute, Creative Commons Licence: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 licence
イラスト:Fourate Chahal El Rekaby
公開日:2024年8月10日
最終更新日:2026年3月9日
[1] この節で語られたこれらの点についての更なる説明と記述については、私の近刊Clude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market (Verso Books, 2024)を参照のこと。
[2] アラブの従属政権――今日のエジプト、ヨルダン、モロッコのような――は、みずからの国境内部での政治運動による異議申し立てに繰り返し直面しており、下からの圧力に配慮し対応することを常に強いられている。
[3] 示唆に富む事実だが、この引用の原文が見られるのは、イスラエルの在アメリカ大使マイケル・オレン(Michael Oren)による「究極の同盟国(The Ultimate Ally)」という題の記事である。
[4] 二次的ボイコットとは、イスラエルで投資を受けた企業(たとえばMicrosoft)が、アラブの市場からの排除に直面することを意味した。
[5] QIZs、MEFTA、そしてイスラエルの正常化に関するさらなる議論は、Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East (Haymarket Books, 2013)(特にpp. 36–38)のなかで行っている。
[6] 2006年、パレスチナ立法評議会(Palestinian Legislative Council)の選挙は132被選議席中74を取得したハマース(Hamas)の圧勝に終わった。国民統一政府がはじめハマースとファタハ(Fatah)――パレスチナ自治政府を統制する優勢なパレスチナ人の政党――のあいだで設立された。しかしこの政府はハマースが2007年にガザ地区の支配権を握ったのちに、ファタハによって解体された。 それ以来、別々の政府(authorities)がガザと西岸に存在してきた。
[7] 直接的な軍事・財政援助以外にも、おおくの種類の支援が存在している――たとえば、アメリカは何十億ドルもの貸付保証をイスラエルに影響しており、そのことでイスラエルは世界市場においてより安く借用することが可能になっている。この十年間でそうした保証を受けているのはたったの六か国しかないが、イスラエルはそのうちのひとつだ(ウクライナ、イラク、ヨルダン、チュニジア、エジプトなど)。.
[8] スーダンの場合では、アメリカが12億ドルの貸付を提供し、同国をテロリズム支援国リストから外すことに同意した(正常化の合意はまだ批准されていないが)。モロッコに関しては、同国がイスラエルと関係を正常化させることと引き換えに、アメリカは同国の西サハラをめぐる主権を認めた。